2019年12月25日(水)午後3時~午後5時(会場:三鷹SOHOパイロットオフィス会議
室、参加者:狸吉、致智望、山勘、恵比寿っさん、ジョンレノ・ホツマ、本屋学問)
今年最後の例会も、全員元気に集いました。安倍内閣の政権運営を巡って侃々諤々の
議論あり、音楽や能楽の「間」(ま)について、音のない瞬間、空間をどう解釈する
か、まさに禅問答のような会話もありました。この高尚さが本会の“本懐”でもあり
ます。その後の忘年会でも、これまた白熱の議論でした。
来年も変わらぬ談論風発が生まれることを願っています。どうぞ、良いお年を。
(今月の書感)
「『国家の衰退』からいかに脱するか」(致智望)/「誰が科学を殺すのか 科学技
術立国「崩壊」の衝撃」(恵比寿っさん)/「図説 挑発の画家 フェルメールの謎と
魅力」(狸吉)/「ビジュアル物理全史─ビッグバンから量子的復活まで」(ジョン
レノ・ホツマ)/「聴衆の誕生」(本屋学問)/「漢帝国-400年の興亡」(山勘)
(今月のネットエッセイ)
「令和の“ひきこもりびと”」(山勘)
「国家の衰退」からいかに脱するか/大前研一(小学館 本体1,500円)
本書は、下記3章から成る、安倍政権による国内の現状、外交の現状、将来への施策提案、の3つのテーマを著者特有の毒舌を以て、構成されている。問題点を箇条書き的に上げて、それぞれに現状解説と有るべき姿を記述する構成なので、私が強く印象に残る箇所をかい摘んで本書感とした。その点、主観的観点を拭うことは出来ない点をご承知置き頂きたい。
第一章 劣化する政治 副題 : 安倍政権「愚策の研究」
第二章 空転する外交 副題 : 自国第一主義にどう対応するか
第三章 次なる戦略 副題 : 日本「再起動」のための処方箋
の3章から構成されている。
第一章は、安倍政権の愚策と言える部分を箇条書き化している、ここに全てを記すことは出来ない、愚策の代表と思える部分をかい摘まんで記すことにする。
「矛盾だらけの軽減税率」、ポイント還元などの「哲学なき増税」の欺瞞丸出しは、支離滅裂であり、二の句が継げない。政治家が票を数えながら、お手盛りしている姿が目に浮かぶと言う。今、軽減税率やポイント還元で景気対策をやっている余裕はないはず、そもそも日本の税制は、税法と言う税務署の恣意的発想から成るもので、徴税は税務署の胸三寸、その点にメスを入れないで、増税が必要とは欺瞞と言う。この点、私見ではあるが、経営に携わる身としては良くぞ言ってくれた、との思いがつのる。
次に、「アベノミクスの牽引役」とは、無駄な政策にいくら税金を積むのか、著者の提言である。
本来、禁じ手である「財政ファイナンス」を続け、未来への投資ではなく、未来からカネを借りて浪費する。これは、政治家の劣化であり、役人の劣化そのもの。未来投資会議と言って、有識者を集め諮問会議などもあるが、財界人や政府に近い大学教授などの提灯持ちを集めても、何の意味も無い会議と言う。
働き方改革なども矛盾だらけ、終身雇用などは時代遅れの発想で、企業を縛って死ねと言っているようなもの。この点、私も同感であり、企業経営のガバナンスビリテイーのありかた、人材活用の在り方など全く理解していない。高い位置から権力で指図すべき事でない。
「同一労働同一賃金」とは何事か、それを言うなら「同一生産性同一賃金」「同一成果同一賃金」でないのか。アベノミクスなるもの7年経過して、2%成長の目標は、達成出来ていない。ピント外れの政策を今後も続けるのか。
その他、新卒一括採用の矛盾、などが手厳しく述べられている。
鳴り物入りのマイナンバー制度は、何処へ行ったか、そこに哲学が無いなら何をやっても成功しないと言う。その原因を著者は、こと細かく具体的に述べている。
異次元金融緩和に付いて、国債と株でフォアグラ状態の日銀は「内部爆発する」と言う。米学者のトンデモ理論を日銀は実践中で、その実態を克明に記述している。安倍政治の残念政策、一位がアベノミクス、2位が外交と言って、第一章を締めくくっている。
次に、第二章 空転する外交 副題 「自国第一主義」にどう対するか。
この章は、米中関係、台湾の現状、そして北朝鮮と韓国、日本、米国の問題。複雑に絡む日韓関係の現状回析。そして、日本の置かれた位置から、日本の在り方についての見解がのべられている。
先ず、日米関係について。トランプに対する判断基準は、全てカネ次第のトランプ小劇場と見るべきこと、その茶番劇を読み解くというのがある。台湾と日本は、兵器を買ってくれるお客さん、北朝鮮は自分が大統領である間に核実験やアメリカに届くミサイルの実験をやってくれなければそれで良いとする。国民を飽きさせずに、来年の大統領選に勝てれば良いのである。しかし、そのカードも細って来ている、今ではツイター小劇場と化し、もし再選されれば、「後は野となれ山となれ」大統領職そっちのけで、ファミリービジネスに精を出すに違いないと言う。
習近平は、香港、台湾、シンガポールに触手していることから、ユナイテッドステーツ・オブ・チャイナとし、北京を盟主とした連邦制が良いと台湾で公演したこしが有ったと言う。以来中国は「連邦」と言う言葉を封印してしまった。そして、香港の暴動騒動から台湾はより距離を置くように成ってきていると言う。
韓国に付いて、トランプと文、この二人のトンデモ大統領が起こす激震はただ事では無い。韓国内では、瀬取りをする北朝鮮の漁船は助けるが、自国のマグロ漁船は助けないと言う巷の噂があり、GSOMIAの破棄など誰が見ても理解出来ない事が罷り通る。この次元の低い問題に、カリカリしないで冷静にほうって置くのが良い、国交断絶などの強硬策も言われるがそれは得策でないと。
その他、ロシアとの北方問題も記されている、日本にとってあまり意味のない二島先行返還などは、選挙対策に利用する姿がみえみえである。それよりも、平和条約の締結を主眼とした交渉を進めるべきであると。
第三章 次なる戦略 日本「再起動」のための処方箋
この章では、大前流の大胆な改革案が述べられている。選挙制度改革、万年野党の改革、地方議会改革などが提案されている。この中に、省庁再々編というのが有って、特に興味を引くテーマなので述べることにする。
高齢省を新設し高齢者向けBI(最低所得補償)の導入を図るというもの。日本の人口1/4以上が高齢者と言う超高齢者社会なのだから、世界に先駆けてリタイヤーした人の生活保障問題を専門に担当する役所「高齢省」「シニア省」と言うものを創設する必要がある。そして高齢者向けBIの導入することで、年金の3割を貯蓄に回す、などと言うことをなくし、市場にそのカネを循環するようにする。「死ぬ瞬間が最も金持ち」と言う、おかしな状況は無くなるはず。
文科省解体と言うのがある、教育改革を実行するビジョンも能力も無い監督官庁、AI時代の教育は「答えを見出す力」の育成が急務である。上から教えるティーチャーで無く、生徒に考えさせるのが、将来に向ける教育である。北欧を中心に20年以上前から既に実施されていると言う。大前研一の息子は、20歳の時に、世界的コンピューター企業から、難しい仕事を自宅で受託し、月に200万円稼いでいたと言う。
と言う具合に、本書には、多肢に渡り改革案が示されていて、現代日本の為政者向けハウツー書の様相である、言ってみれば学生のアンチョコ的なもの、政治家さん! ここらで、カリカリ来て欲しいものだ。と思うのは私だけか。
(致智望 2019年12月13日)

プロローグ お家芸の材料科学で周回遅れ/論文数が示す日本の転落
第1章 企業の「失われた30年」
第2章 「選択と集中」でゆがむ大学
第3章 「改革病」の源流を探る
第4章 海外の潮流
エピローグ
あとがき
本書は18年から19年にかけて毎日新聞に掲載された「守りの科学技術立国」を再編成・加筆したもの。
GDP当たりの論文数はラトビアやトルコと同じくらい。データ上、日本は科学技術立国とは言えない。主要20か国の中で日本が唯一、02年ごろから停滞または減少している。
フラッシュメモリーの生みの親(東芝)はなぜ敗北したかについて、経営戦略の不在を指摘する。東芝に限らず日本の大手企業の多くは、技術的な優位性があればビジネスも優位に立てるという思い込みから、同じ失敗を繰り返す。70~80年代の成功体験が忘れられない。で経営の課題を全て技術の問題として解決しようとするところに問題がある。時代の先を読む発明やアイディアを具現化できる優秀な技術者集団に恵まれながら、ビジネスに勝てなかった東芝の姿は日本の産業界全体に重なる。
1章では凋落する日本企業の研究開発の現状を追い、2章では大学の研究の疲弊を述べている。
政府はアカデミーの研究について「選択と集中」を推進、これにより特定分野にトップダウンで資金を投入し「費用対効果」を上げようとしているので、本来求められるべき基礎研究が薄められていると。即ち、日本の科学研究力が世界の中で相対的に力を失っている現状を示している。
3章では大学の法人化(竹中主導)や「経済のための科学」が強調され、いわば改革による病が生じていると説く。
4章では学ぶべき海外の動きを紹介して、日本の後退への警鐘としている。特に覇権争いを繰り広げる米国と中国は科学技術分野でも二強体制を確固たるものにして、両国に加え欧州の最近の動きを紹介している。
中国は世界最大の開口球面電波望遠鏡「天眼」(Φ=500m)を完成。米国運用のアレシボ(Φ=300m)を大きい。
天文学の大型施設は国際協力でなければ難しいのに! ブラックホールの研究などに使われるが、既にパルサー44個を発見するなど成果が出ている。まだ、データ処理が追い付かないが「全く未知な物体を捉える」のが目標。研究者も破格の待遇で集めて
いる。北京航空航天大の「ビッグバン宇宙論元素起源国際研究センター」所長に梶野敏貴国立天文台教授を就任させている。
梶野は「海外ハイレベル人財招致計画(千人計画)」の対象者である。梶野は就任理由を「米国も魅力だが教授職の任期は2年。イタリヤは経済的に予算不安に対し、中国は経済順調で予算も潤沢」と。中国ではプライバシーより利便性が求められていて(個人的には、民主主義の国では想像外!と常に思っている)IT分野の発展が著しい。科学分野での論文数も米国を抜いて1位(2016年)となった。米国は独創的な企業が育つ風土がある。そして最もユニークなのは「多様性に富む」(ハルシオンハウスのK・ダッグルCEO)でベンチャー企業がどんどん育っている。スエーデンでは女性が働きやすい研究環境づくりが進んでいるという。
「基礎研究への投資は未来への投資」ありふれた言葉だが、いま日本国に必要なのはこの言葉ではなかろうか。
(恵比寿っさん 2019年12月21日)
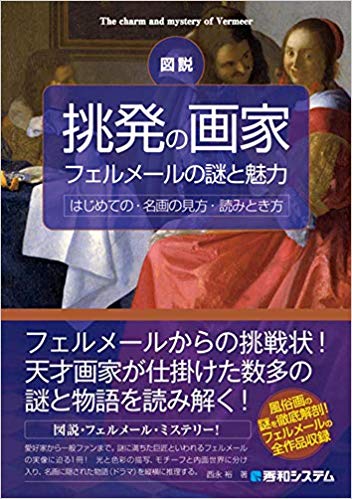
かの有名なフェルメール作品の解説書だが、単なる作品解説ではない。初めから終わりまで一組の男女、男性は絵画の専門家(男性のロゴで表示)、女性(これもロゴで表示)はその相手役という設定で話が進行していく。先生役の男性(著者自身であろう)は、フェルメールはどの絵にも謎を潜ませ、「さあ、この謎を解いてみろ」と人々を挑発しているという視点で解説を進めていく。見出しを見ただけで思わず引きずり込まれてしまう巧みな構成だ。
例えば「西洋絵画史から二百年も消えていたフェルメール」の見出しの下に、女性「フェルメールってその生涯のこととか、わかっていないことが多いんでしょう?」。男性「そうなんだ。存命中は活動していたデルフトを中心に結構高い評価を得ていたんだけど、作品数が非常に少ないこともあって、18世紀になると急速に忘れ去られて、19世紀後半に再発見されて再び評価されるまで約200年近く、彼の存在も作品も姿を消したような状態...、という具合に話が進行していく。
「フェルメールの素性は売春宿の主だった!?」という、スキャンダラスな見出しには、思わず「どれどれ」と身を乗り出してしまう。先を読めばフェルメールは家業の宿屋を引き継ぎ、宿屋にとって娼婦の斡旋は仕事の一部だったのだが。
また著者は文中の男性の口を通じ、「『眠る女』は大いなる失敗作」と断じる見識も披歴している。まるでこの二人と一緒にフェルメールの絵を鑑賞しながら、二人の掛け合いを聞いているような気分だ。
本書にはフェルメールの全作品が掲載され、これだけで絵と解説を楽しめるようになっている。解説はテーマごとに7章に分かれているが、各章は4~11の小見出しに分かれており、とてもすべては書ききれない。参考のため章立てを記す。
口絵1 全作品リスト、口絵2 風俗画の謎カタログ、口絵3 フェルメールの意外な素顔? 、プロローグ「フェルメールの魅力」そのものが謎!? 、第1章 オランダ絵画の黄金時代に幕引きをしたフェルメール? 、第2章 近代絵画を先取りした天才の"謎掛け風俗画"、第3章 想像力を挑発する絵画"フェルメールからの挑戦状!"、第4章 初期だけの"ワインで誘惑"作品の深い謎、第5章 謎だらけの音楽の絵とフェルメールの特異性とは? 、第6章 風俗画を究めた傑作群に秘められたドラマ! 、第7章 エピローグ・衰える創作力と風俗画最後の傑作
この著者には「図説絵画の変革」、「図説名画の誕生」など何冊も著書があるとのこと。これらも是非読んでみたい。
(狸吉 2019年12月21日)

前書きの最初に、「知識の島が大きくなるにつれ、島が謎と接する面は広がる。重要な理論が覆されるとき、それまで確固たる知識と思われていたものはその座を降り、知識と謎の接し方も変化する。こうして改めて発見された謎に、自分の卑小さや居心地の悪さを感じることもあるが、それは真実を手にするための代価だ。独創的な科学者、哲学者、そして詩人は、この島の海岸で華々しく活動する」。 -W.マーク・リチャードソン、「懐疑論者の驚異の念」、「サイエンス」誌よりと、序文にありました。
この言葉が、私自身、古代の歴史の中で、新しい発見があったとき、認める・認めない(今までの立場上認めるわけにいかない)ということにも当てはまると思いました。
前書きに「物理学の範囲」、「本書の目的と記載について」が詳細に書かれており、「目次」が年代順に250項目並んでいます。 その前書きの「物理学の範囲」から、幾つか抜粋してみました。
現代の物理学界をリードする物理の専門家の団体、米国物理学会は、1899年、物理学の知識を向上させ、広める使命を帯びた36人の物理学者によって設立された。
私たちの周囲の世界、内側の世界、私たちを超えた世界を理解するためには、物理学がきわめて重要である。それは、最も基本的で根本的な科学だ。物理学は、相対性理論や弦理論などの概念で想像力に挑み、コンピュータやレーザーなどの、暮らしを変える偉大な発見へと導く。物理学は、最も大きな銀河から、最も小さな素粒子に至るまで、宇宙のすべてを研究する。さらに、化学、海洋学、地震学、そして天文学など、ほかの多くの科学の基礎でもある。
物理学の発見は、しばしば新しい技術をもたらし、哲学や世界観まで変えてしまうこともある。たとえば、多くの物理学者にとって、ハイゼンベルクの不確定性原理は、物理的宇宙は決定論的な存在ではなく、確率が奇妙な具合に集まったものだという宇宙観を裏付けるものだ。また、電磁気の理解の向上は、無線、テレビ、そしてコンピュータをもたらし、熱力学の理解は、自動車の発明につながった。
物理学の範囲は、遠い昔から固定されていたわけでもないし、容易に境界が決められるものでもない。私は物理学の範囲をかなり広くとらえ、技術や応用物理、天体に関する知識の向上、そして、むしろ哲学に属するかもしれない話題もいくつか取り上げている。
1964年に発表された、「神の粒子」と呼ばれる素粒子の仮説の次に、1965年に発売されて全米を熱狂に巻き込んだ、とてもよく弾むスーパーボールが載っている物理学の本など。いつの日か、すべての銀河を引き裂き、宇宙を恐怖のビッグリップでズタズタにしてしまうかもしれない、謎のダークマターについても、また、量子力学を生み出した黒体放射の法則について。
さらに、宇宙人とのコミュニケーションに関するフェルミのパラドックスについて思い巡らせ、アフリカで発見された、20億年にわたって働いていたらしい有史以前の原子炉について考えてみる。そして、世界で最も黒い塗料の開発競争の話。黒い自動車の塗料の100倍以上暗いそうだ! この「究極の黒の塗料が、太陽エネルギーのより効率的な収集や、超高感度の光学装置の設計に利用される日が、いつか来るかもしれない。
宇宙の小さな片隅で、ソフトウェアと数学のルールを使って、生物のような振舞いをシミュレートできるコンピュータを、人類はすでに作り出している。ひょっとすると、やがては実在そのものをシミュレートできるかもしれない。そして、宇宙のどこか別の場所で、人類よりも高度に発達した生命体が、すでにそうしている可能性だってある。と、纏めています。
本文に目を通してみると、中身が即、理解できる出来ないは別にして、分かりやすい配置になっています。
それぞれの項目について、 紀元前~1600年代、1700年代、1800年代~現在~未来の年代別に並んでおり、1ページに1項目、250項目を網羅している。
どの項目も、写真・イラストを含めて1ページに短くまとめられているので、テーマの全容が掻い摘んで概略を知ることができる。
学生時代に習ったことや、漠然と覚えていたこと、名前は聞いたことはあったが、はっきりしないかったことなどが思い起されて良いと思った次第です。
ただ、後半の方は、最新の項目が多く、聞き慣れない、あるいは、全く聞いたことも無かったような項目も多く含まれています。
紀元前138億年 ビッグバン、 ~紀元前3000年 日時計、 紀元前2500年 トラス、 紀元前1850年アーチ、 ~紀元前250年 サイフォン、アルキメデスの原理、 紀元前230年 滑車、 50年 歯車、 1132年 大砲、 1150年 永久機関、 1338年 砂時計、 1543年 地動説、 1608年 望遠鏡 リッペルハイ、ガリレイ、 1609年 ケプラーの惑星運動の法則、 1610年 土星の環の発見、 1638年 落下物の加速 ガリレイ、 1643年 気圧計 トリチェリ、 1644年 運動量の保存 デカルト、 1660年 フックの弾性の法則、 ~1738年 ベルヌーイの定理、 1783年 ブラックホール、~~~と続いています
そして、2007年にHAARPが登場します。
その後は、2008年 世界一黒い塗料、 2009年 大型ハドロン衝突型加速器、
その後、360億年後 宇宙のビッグリップ、 1000億年後 宇宙の孤立、 100兆年後 宇宙の消失、
100兆年以降 量子的復活で締めくくられています。
以前から気になっていた「HAARP」についての記載内容を取り上げてみました。
「HAARP」についての著者は、
オリヴァー・ヘヴィサイド(1850-1925)、アーサー・エドウィン・ケネリー(1861-1939)、グリェルモ・マルコーニ侯爵(1874-1937)の3名。
陰謀説を主張する人々によれば、高周波活性オーロラ調査プログラム、略してHAARPは、究極の極秘ミサイル防衛装置、世界中の天気や通信を妨害する手段、あるいは、数百万の人々の精神をコントロールするものだそうだ。だが実のところ、HAARPはそのような恐ろしいものではない。とはいえ、やはり興味深いことには違いない。
HAARPは、アメリカ空軍、アメリカ海軍、国防高等研究計画局(DARPA)などが出資する実験的なプロジェクトだ。その目的は、大気の最外層のひとつ、電離圈の研究の促進である。アラスカの35エーカー(4000 m2)の平地に設置された180本のアンテナ・アレイは2007年にフル稼働に達した。HAARPは、高周波送信システムによって、360万ワットの電波を、地上約80kmから始まる電離圈の内部へと送る。その後、電離圈をこのようにして加熱した結果、どのような影響が生じたかを、地上のHAARP施設にあるさまざまな高感度装置によって研究する。
電離圈は、民間の通信にも軍事通信にも影響を及ぼすため、科学者たちが電離圈の研究に関心を抱いているのもうなずける。大気のこの領域では、太陽光によって荷電粒子が生じる。
電離圏の下部で反応を引き起こすようにHAARPの信号を調節し、オーロラ電流を発生させ、低周波を地球に送り返すことができる。低周波は海中深くまで届くため、海軍が潜水艦隊に方向を指示するために利用できる可能性がある一潜水艦がいかに深く潜っていようとも。
地震兵器になりうることも分かった気がします。しかし、開発に携わっている方は、兵器という認識はなく、自然現象の理解を解明しているという立場でいるためのギャップであるような気がしました。
(ジョンレノ・ホツマ 2019年12月21日)
 著者は東京大学で美学芸術学を学び、その後母校で教鞭を取りながらとくに音楽分野で評論活動を続け、現在は東京音楽大学教授を務める。本書は、1989年度の第11回「サントリー学芸賞」を受賞した。
著者は東京大学で美学芸術学を学び、その後母校で教鞭を取りながらとくに音楽分野で評論活動を続け、現在は東京音楽大学教授を務める。本書は、1989年度の第11回「サントリー学芸賞」を受賞した。私たちが音楽を語るとき、「クラシック音楽」、「ポピュラー音楽」という分けかたをするが、同じ分類がドイツ語にもあるそうで、それを訳すと「真面目な音楽」と「娯楽音楽」という2分法になる。そして一般的には、芸術音楽や真面目な音楽は"高級"で、娯楽音楽や民俗音楽は"低級"と解釈されるが、本書によればこのような分類方法は最近になってからのことらしい。
クラシックのコンサートは、今でこそ聴衆は静かに厳粛に耳を傾けるのが当たり前だが、モーツァルトやベートーヴェンが活躍した18世紀、客が騒がしくて演奏ができないとハイドンがいったとか、演奏中も飲食したりトランプに興じてほとんど音楽を聴いていないとか、演奏会場に煙草の煙が立ち込めたという記録が残っているそうだ。また、ある演奏会では事前に歌詞を書いたものが配られたが、それは演奏中も騒がしくて歌詞を聞き取れないだろうという配慮からだったそうだ。
その後、19世紀になると芸術を哲学と同じように精神と感覚、感性を統合するものだと考えた音楽美学者たちが、世俗的欲望や刹那的喜びを表現する音楽など自分たちの要求に合わない種類の音楽は低級だとして切り捨てた。そして19世紀になると、クラシック音楽が誕生した18世紀にはそうした価値の違いがなかった音楽のカテゴリーが歴然と分けられ、「独創性」、「作品」、「天才」といった概念が確立したという。バッハもベートーヴェンもモーツァルトも神格化され、偶像化されたが、彼らとて作品の出来不出来や欲望も嫉妬もあった。
バッハが給料の高い仕事に動かされて教会を移った話、妻子あるハイドンが宮廷楽長時代にソプラノ歌手と不倫した話、モーツァルトが借金しまくった話、ベートーヴェンが自分の楽譜をランク付けして売った話...、大作曲家の実像は、一般庶民とほとんど変わらなかった。
ピアニストのグレン・グールドは、ある時期から公開演奏を一切しなくなり、それが彼の精神性とも重なってさらなる伝説を生んだが、本書によれば同じ曲をテンポや表現を変えて何回も録音し、最も出来の良い部分を継ぎ合わせて聴き手の好みに合った音楽を提供するという試みをしたそうだ。
最近の若いクラシックファンのなかには、サティやマーラーやブルックナーは知っていても、ベートーヴェンやモーツァルトなどいわば古典をほとんど聞いたことがない者も多いそうだが、教養としてクラシック音楽を身に付けるのでなければ、それはそれで一向にかまわないと著者はいう。もちろん、どんな分野であれ、知識があったほうがより深く楽しめることは確かだが。
ピアノ演奏家を否定する「自動ピアノ」の出現や、レコード、CDの発明もあった。現代作曲家ジョン・ケージは「4分33秒」という作品で、楽器は何でも良いがその時間はまったく音を出さないという手法を世に問うた。演奏者はその間、ストップウォッチを持ってステージに立ち、"演奏"を終えると一礼して退場する。
文化も歴史も人間がつくってきたものである。だから、価値の前提が変われば価値観も変わる。価値観自体の生成と変容にかかわる歴史的プロセスやそこに働いた力学、メカニズムを一歩引いて冷静に分析し、検証する視点を確保することが、これからの音楽文化を理解していくうえで大切だと本書はいう。
普遍性、変わらないことも大切だが、音楽芸術ももっと気楽に、クラシック音楽だろうが能楽だろうがオペラだろうが、肩肘張らずに軽く聴いてみよう。本書の内容も表現もとても難解で、簡単に紹介することは難しいが、本当はそんなことがいいたかったのではないだろうか。
(本屋学問 2019年12月22日)

中国は4000年の歴史を持つといわれるが、その中で「漢帝国」は400年の歴史を持つ。しかし、中国は「漢字」「漢民族」で代表される国家であり、「漢帝国」は「古典中国」である。夏、殷(商)、周の時代を経て秦が中国を統一し、漢がこれを継ぐ。
楚の項羽を破った漢の劉邦が紀元前202年に中国を統一。武帝で最盛期を迎える。一時期、王莽に政権を簒奪されるが、紀元後25年に洪武帝が再統一(後漢)。前漢200年、後漢200年、合わせて400年余りの歴史を刻む。
漢は、220年に魏に滅ぼされるが、中国史上最長の統一帝国となる。かくして漢は「古典中国」となったが、その政治と文化の支柱は儒教であり、中国は「古典国家」であるとともに「儒教国家」でもあった。その「古典国家」「儒教国家」は、いかにして形成されたのか。その興亡の歴史をたどる。-これが本書のあらすじである。
著者は、早稲田大学理事・教授。専門の「古典中国」で三国志はじめ多くの著作を持つ。本書の内容は壮大な漢帝国の歴史だが、そこから掬すべきエッセンスは、「古典中国」となった漢帝国がその後の中国に、そして近代中国に何を与えたかであろうーと著者は言う。
掬すべきエッセンスは本書に盛りだくさんだ。名門出で驕慢・冷酷な項羽と農民出身で親分肌の劉邦の攻防。漢家が取り入れた「黄老思想」-中国の祖とされる伝説の黄帝と老子の思想による政治。その「黄老」に取って代わった「儒教」は「天帝」「皇帝」の権威を定着させ、中央集権政治を支えた。儒教官吏と宦官の熾烈な抗争。項羽・劉邦・王莽・武帝・文帝ら際立つキャラクター。「四面楚歌」で落涙する項羽。功臣を処分する劉邦の孤独。寛容政治の文帝は母への孝養で「中国24孝」の1人に数えられる。残忍な「人豚」の刑で知られる后太后は中国三悪女に数えられる。
終章で筆者は言う。最後の中華帝国である清は、辛亥革命によって終焉を迎えた。辛亥革命は、各地域、省が独立するかたちで実現した。それは中央集権的な官僚制による「古典中国」の解体であった。それによってもたらされたかに見えた近代化は西欧の民主主義とは無縁だった。辛亥革命後も、漢の時代と同様の地方自治か中央集権かという議論が残った。中国の近代化・欧米化が日本のように進まなかった理由には、「古典中国」の影響力が近代にまで及んでいたことがある。
ヘーゲルは、中国を「持続の帝国」と呼んだと言う。「古典中国」から変わらない官僚制を停滞とみた。中国には、西洋や日本の中世におけるような封建諸侯が存在せず、豪族など有力者は一族を挙げて高級官僚排出を目指した。「古典中国」はすべての権力が国家に収斂された。その手段が科挙をはじめとする官僚登用制度だった。
中国の近代文学の祖となった魯迅は、「狂人日記」で「儒教が人を食った」と書いた。「古典中国」の中核に置かれた儒教は、教義を変えながらも時の権力を擁護し、中国の制度や文化を支配し続けた。そして「儒教」は、一時、隋の時代に「仏教」に敗れたが、「道教」「仏教」の挑戦を退け続けて「古典中国」「儒教国家」中国を支え続けた、と本書はいう。
(山勘 2019年12月23日)
このほど、元農林水産次官が、自立できずにひきこもり、暴力を振るう長男を刺殺した事件の判決が出た。懲役8年の求刑に対して6年の実刑となった。弁護側はこれより短い刑期と執行猶予を求めたが通じなかった。この事件は、単純で残虐な子殺し事件とは同一視できないものの、事件の根本原因は被害者が"自立"できていなかったことにあろう。
一般的に"ひきこもり"は良くないこと、好ましくない状態として否定的に認識されている。そのひきこもりが、今、中高年齢層で増えているという。その面倒を見る親も高齢化する。80歳の親が50歳のひきこもりの子の世話をする"8050問題"は、いわばひきこもりの老々介護である。深刻な問題だが、世間の目を隠れる家族の孤立化などで、その実態はなかなか把握できないようだ。
内閣府調査によると、40~64歳の中高年のひきこもりの人は全国に推計で約61万3000人と推計される。厚労省調査で、20歳から64歳までを対象にした5歳刻みで「ひきこもりの状態になった年齢をみると、60~64歳が最も多く、断トツの1位である。60代に入った途端にひきこもりになるのである。しかしこれを鵜呑みにして信用していいのだろうか。
ちなみに、厚労省によると、ひきこもりとは、「自室や家からほとんど出ない。出ても趣味の用事や近所のコンビニ程度。これを6カ月以上続けること」だという。また同省調べで「ひきこもりになったきっかけ」を見ると、「退職した」ことが理由の断トツ1位で、これに「人間関係がうまくいかなかった」「病気」などと続く。
世の荒波をくぐって生きてきたはずの中高年者の多くが、退職と同時にひきこもりになるというのはどういうことだろう。あるいは、中高年者のひきこもりには、それなりのレーゾンデートル(存在理由)があるのだろうか。あるいは、従来のひきこもりを越えた意味のある中高年の新たな"ひきこもりびと"が出てきているのではなかろうか。
そもそもの問題は、自立とは何か、ということである。一般的な社会生活を送り、仕事をして収入を得られれば本物の"自立"ということになろうが、それを中高年の"ひきこもりびと"に求めていいのだろうか。一歩進めて考えれば、"ひきこもりびと"には、それにふさわしい別建ての"自立の仕方と生き方"があるのではないだろうか。
そして「退職」ひきこもりを、単純に「退職して社会との接点を失った」と解釈するのは、それこそ単純すぎるだろう。退職して、「これからはのんびりしよう」とひきこもる人もいるだろう。これをひきこもりとして問題視していいのだろうか。ひきこもりがちな友人に聞いたら、「テレビの前が私の毎日の定位置だ」と笑う人やら、「出かけるとカネがかかるからなるべく出かけない」と言った人もいる。
そういう"ずぼら系"ひきこもりだけでなく、読書や創作、インターネット世界でつながるなど、"まじめ系"のひきこもりが生まれつつあるのではないだろうか。昔から洋の東西にかかわらず精神貴族の隠遁生活者がいる。これからは、そういう"ひきこもりびと"、令和の新時代にふさわしい積極的で新しい"ひきこもりびと"が増えるのではないだろうか。
(山勘 2019年12月23日)