2018年10月29日(月)午後3時~午後5時(会場:三鷹SOHOパイロットオフィス会議室、参加者:狸吉、山勘、恵比寿っさん、ジョンレノ・ホツマ、本屋学問)
今回は、折からの流感ケアのために致智望さんが大事を取ってお休みでした。8月投稿の「日本人の知らないトランプのアメリカ」は、引き続き11月の例会で発表をよろしくお願いします。
今回も、書感には習近平の中国、日本人の原点、江戸時代末期の世田谷代官の日記、エッセイも大相撲、言論の自由問題などユニークなテーマが並び、充実しています。次回も変わらぬ談論風発の話題をよろしくお願いします。
(今月の書感)
「習近平帝国の暗号2035」(恵比寿っさん)/「世田谷代官が見た幕末の江戸 日記が語るもう一つの維新」(狸吉)/「日本人とは何か 神話の世界から近代まで、その行動原理を探る」(山勘)
(今月のネットエッセイ)
「伝統」(本屋学問)/「縦置きモニター画面のノートパソコン」(ジョンレノ・ホツマ)/「コトを荒立てる国、荒立てない国」(山勘)/「『言論の自由』に制限あり?」(山勘)

日本経済新聞編集委員兼論説委員
宮城県仙台市生まれ。早稲田大学第一文学部卒。
1987年日本経済新聞社入社。政治部などを経て98年から3年間、北京駐在。首相官邸キャップ、政治部次長の後、東日本大震災の際、震災特別取材班総括デスクとして仙台に半年ほど駐在。2012年中国総局長として北京へ。
2014年ボーン・上田記念国際記者賞受賞。現在現職。
著書に「習近平の権力闘争」、「中国共産党 闇の中の決戦」(いずれも日本経済新聞出版社)
はじめに
脅し――首を吊った将軍、席を立った胡春華
党主席への狭き道――習近平コードを解くカギ
金正恩が習近平帝国を滅ぼす
対米外交の蹉跌、新型の「韜光養晦」へ
独裁と強権の罠――突如、姿を消す有力者たち
新たな主役らへの厳しい目――2035年までの生き残りゲーム
おわりに
昨年の共産党大会で2035年までに世界で最も革新的な国家の1つになるという習の基本方針が示された。50年には強国となるというのに、なぜ半端な数字?と思ったので飛びついた(笑)。反腐敗運動と軍掌握で文革のような武闘闘争(著者はこうはいってないけど)を繰り広げて、今や鄧小平を抜いて毛沢東に迫る権威を手に入れた習近平が、不安定とはいいながら、世界一の人民大国をどのような方向へ導こうとしているのか、カギがあるように思ったから。
10月革命で成立したソ連は91年に崩壊、74歳だった。中国の寿命がそれと同じなら23年=習の2期10年任期切れとなる。
後継者を立てなかった習は、その時点で「ソ連を反面教師として新中国を永らえさせるには習の力が必要」と言わせたい。
2035年までに現代化国家の建設を終えるという超長期の工程表だと著者は言う。35年は82歳(毛の死亡年齢)なので、それもにおわせているという。
とはいえ、経済成長が減速しているし、あちこちには地雷が埋まっている。長い習時代を宣言した巨大国家には、なお多くの死角があると著者は説く。第1章、2章では、盟友の王岐山(中国共産党中央規律検査委員会書記)の活躍(140万人を処分)で今の地位があることが紹介され、次は「党中央委員会主席」だ、これは毛沢東の地位の復活で、鄧小平の集団指導体制の否定である。共青団への露骨な圧力も顕著である。
既に暗号を解読していた人間がいる。スティーブ・バノンである。そして「世界一の経済大国になろうとしている。そして、世界の覇権国を目指している。我々への警告だ」と。
第3章では、毛沢東が金日成に対して、国境は鴨緑江だといったと北は主張(現行は遼河)。以前は、血友国家だった北と中国も今や非常に危険な関係。中国は米国よりも北を危険視している。何せ核を持ち、短距離であればミサイルも使える武力。
第4章では、新型の韜光養晦を指摘し、対米関係の安定を最優先しているという。いずれ米国をしのぐ大国にあるという魂胆があるからだ(著者はここまで言ってない)。
第5章では一進一退の日中関係に触れ、中国はあくまで「外交より内政重視」の政治であるという。これは昔から変わってませんね(笑)。
第6、7章では、まだまだ権力闘争は終わったわけではないことを指摘している。35年までにはまだまだ長い生き残り闘争があり得ることを推定している。
著者は、中国本土に情報源を持っているジャーナリストなので、説得力のある根拠が随所に示されていて面白いです。
全体の感想としては、我々は国家の成長につれて「民主化」が進むと考えがちであるが、この国はそれがあり得ないということを示しているように思ったことです。
(恵比寿っさん 2018年10月22)

260年余の長期政権を維持した徳川幕府もようやく終わりを迎える時代、江戸の中心からやや離れた世田谷領の代官、大場与一・美佐夫妻は克明な日記をつけていた。著者はこの膨大な日記を読み解き、現代の我々に分かるよう再構築してくれた。代官は武士ではあるが下級武士、今日では中間管理職というべきか。それだけに下々の暮らしにも目が行き届き、過去を知る絶好の史料となっている。本書を読むと幕末の息吹を感じ取ることができる
本書は次の章立ての通り、明治維新の発端から成就まで、約10年間の動乱の世の記録である。
序 章:桜田門外の変の衝撃~維新のはじまり
第一章:大場家と世田谷領~いくつもの顔を持つ代官
第二章:江戸の混乱に巻き込まれる~開戦危機
第三章:大場家断絶の危機~鉄砲を持った農民たち
第四章:関東の騒乱と世田谷~幕府の消滅
第五章:明治維新と大場家~消えいく江戸
おわりに
まず安政元年(1854年)元旦の日記が紹介されている。原文は「朝少々くもり、四ツ頃より天気 一例之通り、吉例相済む、宗八初め上町の者、例に出候事」とある。同時代の人々は、これだけで分かったであろうが、現代の我々にはさっぱり分からぬ。
引き続き「吉例とは大場家で毎年おこなわれる恒例の行事のこと。元旦の場合は、家族のうち男性は袴・羽織、女性は掻取(かいどり)という礼服を着用し、神棚に向かって拝む仕来りであった。掻取とは帯を締めた上から掛けて着る長小袖のことである。その後、大根の輪切りと里芋の入った雑煮を神棚に供えた」と原文の詳細な解説があり、やっと理解できる。
与一の死後も美佐は日記を書き続けて毎年一冊にまとめ、後の世に32冊の日記を残した。歴史の貴重な資料が時空を超えて蘇ったのは、正に著者のお陰である。膨大な文書を読み解き、興味ある記録に解説を加えた著者に感謝したい。
三日の日記は「一吉例相済む、九ツ頃に村々役人共礼に出る、吸物・酒・肴二種出し候事」と維新前夜の平穏な日々を描いている。ところがこの二ヵ月後、主君として仕えていた大老井伊直弼が暗殺され、大場家も幕末の動乱に巻き込まれてゆく。
その渦中の第二章では、大場家が史上有名な「和宮降嫁」の助郷人足を命じられたこと、第三章では、暴徒の反乱に備えて、農民に鉄砲を持たせ射撃訓練をしたことなどが記されている。またこの章では、与一の死によりお家断絶の危機に直面したこと、それを死後相続という非常手段で乗り越えたことが記されている。
慶応元年(1865年)から始まる第四章では、関東一円で吹き荒れた農民一揆に触れている。翌年5月には、江戸市中の米屋が打ち壊され、数日間無政府状態となった。大場家でも暴徒鎮圧の準備はしたが、幸いにも世田谷領への侵入は無かった。しかし、幕府の長州征伐御用金の負担は重くのしかかった。
最後の第五章では、幕府の消滅を描いている。官軍の江戸城総攻撃を前にして、主戦派・恭順派の論争が起こるが、将軍慶喜は恭順の態度を崩さず、総攻撃は回避された。この騒ぎの中で大場家の当主、弘之介は祝言を挙げている。この章では彰義隊の反乱と壊滅、戊辰戦争と大場家の関わりなどについて述べている。本書は明治天皇の上京拝見と日記を記した美佐の死で終わる。
本書を読み一見何事も無く無事太平に過ぎた江戸時代が、実は激動の時代であったことを知った。大場家断絶の危機や、長州征伐御用金供出のやり取り等、まるでその時代に生きたように、手に汗握る思いで読み終えた。
(狸吉 2018年10月26日)
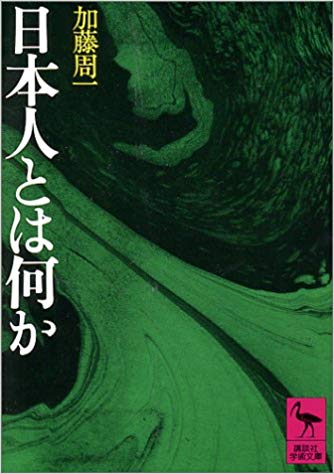
本書は、著者他界の2年前に上下二巻で刊行された名著を、今回一巻にまとめて再刊された。
いきなりだが、津田左右吉博士は、日本の特質を次のように指摘している。①日本と同じ人種・民族はいない、②日本人は遊牧生活をしたことがない、③日本人は基本的に農業生活だった、④島国である日本は異民族との闘争がなかった。これが日本人の“骨格”だというのであろう
平安前期までの日本は、ほとんど中国文化の取り入れに明け暮れた。その中で本当に創造的な仕事といえるのは、仮名の発明くらいである。そして、日本は中国の律令制を学んだが、科挙抜きで導入し、大化の改新で中央集権国家を形成した。科挙を導入していたら漢字文化に抱き込まれて庶民は文字も読めず、いまに至るまで中国にがんじがらめにされていたかもしれない。
仏教は、ブッダが生まれた紀元前5世紀から、中国、韓国を経て変質しながら6世紀初頭に日本に伝来した。日本はその仏教を、道教、儒教を含んだ三教合一的な仏教として受け入れた。そして足利時代になると、武士には禅宗、農民には真宗、商人には日蓮宗が浸透した。
武士の時代は、「公田」に対する「名田」、すなわち所有者「名主」の「名を付した田」の時代であり、それを束ねたのが「大名」、それを耕したのが、班田の支給が滞り、逃亡した農民であった。そして、盗賊の横行にそなえる自警団として武士が台頭し、清盛の登場で「公地公民」と決別した。清盛の死とともに頼朝の登場となる。彼は、六十余州総追捕使になって、事実上の支配権を得た。
こうして、武家革命と日本式法治国家が成立する。まず「承久の乱で、守護・地頭の人事権をめぐり、頼朝によって任ぜられた執権北条義時と、人事権の奪回を図る後鳥羽上皇が正面衝突する。この乱に勝利してはじめて武家による全国支配が確立する。
やがて下剋上の時代となり、守護・地頭制度の腐敗が進んでいた鎌倉幕府は、新田義貞の攻撃であっけなく崩壊する。鎌倉幕府に代わる足利幕府の特色は、土地所有に代わる貨幣経済の掌握だった。渡来銭・明銭を独占して、全国支配を進めた。
武力の戦国時代から、学問の江戸時代になると、学問も、「僧侶と公家」の独占から「民間学者」が活躍する時代となった。浅見絅斎(けいさい)は、朱子学に基づいて統治における天皇の正統性を理論づけた。鈴木昭三は、「仏法即世法」と説き、「仏法は世間法に異ならず。世間法は仏法に異ならず」と説いた。石田梅岩は、「本然の性」すなわち「本性」の通りに生きれば天理にかなう生き方になるとした。
富永仲基は、「前説の上に出ようと加える」ことや「権威づけようと、絶対的権威の言葉にさらに加える」といった儒学や朱子学解釈の「加上」を批判した。山片蟠桃は、地動説や無神論を説いた。鎌田柳泓(りゅうおう)も、無神論や進化論的思想を説いた。この進化論的思考はダーウィンの「種の起源」の40年ほど前である。
和算の歴史では、江戸時代初期の毛利重能にはじまり、綺羅星のごとく輩出する。中に関孝和がおり、本田利明がいる。日本の和算は、わずか半世紀で微積分学まで進み、世界のトップに躍り出た。江戸時代の思想の流れは、そもまま明治維新につながる。
本書は、読み物的にもおもしろく、日本人の軌跡を見事に俯瞰している。
(山勘 2018年10月28日)
大相撲で一時代を築いた元横綱の貴乃花親方が、現在の日本相撲協会の体質に愛想を尽かしてか退職届を出した。日本相撲協会の大胆な組織改革をやってくれると期待していた大勢のファンは、さぞがっかりしたことだろう。もちろん、協会側も貴乃花親方に対していいたいことはあるだろうし、これを受けて協会の広報部長が何とも歯切れの悪い会見をしていたが、それで思い出したことがある。
2007年だったか講談社の「週刊現代」が当時の現役横綱、朝青龍らの八百長相撲を告発する特集をしたことで、日本相撲協会と20人近い力士が講談社と記事を書いた著者を名誉棄損で訴え、裁判は東京地裁、東京高裁さらには最高裁まで持ち込まれた。この前代未聞の八百長相撲裁判は、結果的には事実無根だったのか証拠不十分だったのか、いずれにしても講談社側が敗けて全国紙に謝罪広告を出し、協会に5,000万円近い賠償金を支払ったが、その後が実に面白い展開になった。
最高裁の判決が出た後、プロ野球の賭博事件を捜査していた警視庁が証拠品として押収した、野球賭博に関係した力士の携帯電話のメール履歴を調べていると、あろうことか10人以上の現役力士がかかわった八百長相撲の明白な証拠が出てきたのである。別件とはいえ世の中にはこんなことがあるもので、本当に?事実は小説より奇なり”になった。
警視庁が摘発した八百長相撲の実態と週刊現代が告発したケースは別のものだが、問題は大相撲という日本伝統の国技に八百長が存在したという紛れもない事実である。この?神聖な”世界でそんなことはあるはずがないと信じていた多くのファンの心は、見事に裏切られてしまった。もっとも、この黒い噂は以前からあって、1980年代にも小学館の「週刊ポスト」が八百長問題のキャンペーンを張ったことがあり、まさに?火のない所に煙は立たぬ”、人間どうしのことだからどの世界でもあり得る話である。
警視庁がどんな意図でこの八百長事件の詳細を公表したのかはわからないが、証拠調べも調査もろくにせず、相撲協会の主張を鵜呑みにして無罪放免した裁判官たちの判断は明らかに間違っていた。「週刊現代」の記事は大筋で正しかったわけで、もし裁判官たちが無能でないのなら一種の組織的職務怠慢、職務不履行である。
警視庁に赤っ恥をかかされて、裁判所の権威はまったく地に落ちた。本来なら自らの無知と不明を恥じて謝罪すべきだが、当事者たちは微塵もそう思ってはいない。まさに?蛙の面に小便”、すっかり硬直して良心も正義感もこれっぽっちも持ち合わせない現在の日本の司法は、裁判所の建物は立派でもその中身はせいぜいがこんな程度なのだろう。それに新聞系始め大方の御用マスコミは、この事件を真正面から取り上げる姿勢はほとんど見せなかったようだ。社会的影響の大きさを考えたのかもしれない。
八百長相撲は野球賭博と違い原則的には罪に問われないそうで、一方が依頼しても相手が応じなければ成立せず、金銭授受の証拠を掴むのも容易ではない。しかし、思いもよらぬ警視庁の援護射撃に意を強くした講談社は、一連の裁判の敗訴で受けた名誉回復と賠償金の返還を求めて、改めて相撲協会と八百長力士を詐欺で警視庁に告訴した。
"一事不再理”の原則からすれば裁判をやり直すことはないだろうが、講談社にしてみれば5,000万円は大金だ。この際、当事者である力士はもちろん、理事長始め相撲協会幹部や裁判官、弁護士たちが身銭を切って講談社に返却すべきではないのか。そのくらいの覚悟がなければ、軽々に全面否定したり断罪すべきではないし、こんな杜撰な裁判がまかり通る世の中に法律はいらない。関係者たちは、今日の裁判制度をあまりにも舐めている。
伝統と改革は表裏一体である。世界最古の木造建築といわれる世界遺産の法隆寺も、ほとんど知られていないが強度が必要な部分は鉄材で補強して保存している。大相撲も同じで、ときには時代に合った組織改革が必要だ。しかし、伝統に胡坐をかいて批判を受け入れる謙虚さも自浄作用もないのなら、いつしか贔屓筋にもファンにも見放されて消滅するしかない。私は相撲にもまったく興味がないので、伝統が消えても少しも困らない。むしろ、相撲中継の15日間を毎日、世界中のテニスの試合や大好きな落語や吉本新喜劇を中継してくれたらよいと願っている。
と書いていたら、テレビで若い女性が東京地裁のトイレで男性裁判官を棒で殴ったというニュースをやっていた。普通なら少し頭のオカシな人がと想像するところだが、何となくその加害者に同情してしまった。ひょっとしたら理不尽な判決に腹が立って、思い切り不満をぶつけたのかもしれないから。
(本屋学問 2018年10月10日)

先日、ノートパソコンを持ち運んだ先で、うっかり滑り落してしまいました。そんな衝撃もなかったので、その時は何も気にしていませんでした。しばらくして、調べることがあり、電源を入れたら、モニター画面の一部しか映らず、いろいろトライしたがダメでその時、壊れたことを知りました。
購入して2年半しか経っていないので延長保証期間内であると、購入先に持ち込み調べてもらったところ、本体は壊れていないが、モニターが壊れてしまっていると報告を受けました。
残念ながら、モニターは延長保証の対象外で実費がかかるとのこと。ここで修理するよりも新規に購入した方が安くつくと言われました。
それには、現在パソコンに入っているデータを取り出すために、モニター用のディスプレイ画面を購入される方法が一番確実で手っ取り早いのではないかと教えてくれました。ディスプレイは1.1万円ぐらいからあるからとのことでした。
早速、その足で店頭にあったディスプレイを見ましたがほとんどがゲーム用のため大型で使いづらいと思い、価格COMで調べることにしました。
そこで、縦横どちらでも使える15インチのモニターがあることを知り、早速手配しました。厚さは1㎝ほどで何とか現在のノートパソコンのモニターの上に乗せて貼り合わせたようにして急場をしのぎました。
その後、非常に細かい字で書かれた小さな説明書を読み、縦置きに設定することが出来ました。
今は、このモニター画面をノートパソコンの右側に置いて使っています。
多少使い勝手が悪くとも、例えば、ワード画面の縦書きA4が、スクロールする必要もなく、全体が確認できることに感激しました。
添付図はモニター画面を縦置きにした、A4縦書きのワード画面です。
どこかのメーカーが、ノートパソコンでもモニター画面を縦置き・横置きどちらにもできる機種を作ってくれないものかと願っているのは私一人でしょうか。
(ジョンレノ・ホツマ 2018年10月18日)
国には、コトを荒立てる国と、荒立てない国がある。「国」を「民族」と言い換えてもいい。歴史的事実を忘れてはならないが、自国の歴史から意図的に選択した歴史事実と歴史認識にしがみついて、コトを荒立て続けるような国がある。わが国は歴史的にもコトを荒立てない国と言っていいだろう。その日本人の真情にうったえるエピソードに出会った。
戦後50年ほどたったころ、天皇、皇后両陛下の訪英が日英間の外交課題になった。その折りに問題になったのは、旧日本軍による英国人捕虜の強制労働だった。それが今年7月に公開された英公文書で明らかになった。朝日新聞(10月10日)によると、1993年9月に訪日したメージャー英首相(当時)に、細川護熙首相(同)は、「日本により苦しみを味わったすべての英国人に、繰り返し深い反省とお詫びの念を表明したい」と謝罪した。
これに対してメージャー首相は、こう答えたという。「問題は重要だが、調子(キー)を低く抑えたい。拡声器(メガホン)を使わず、非公式協議で解決を探りたい。この件は強い感情を呼び起こしたが、燃え上がらせるべきではない」と。この発言は、歴史的事実と外交上の命題を秤量した政治家の見識だろう。日英両国が、そういう外交上の5年におよぶ努力を重ねた結果、1998年5月、天皇、皇后両陛下の訪英が実現した。
以前、私は『「争い」に弱い日本人』というエッセーを書いた。そこで「どうも日本人という民族は「争い」を好まない民族なのではないか。西洋と比べてみると、日本には宗教同士で殺し合った歴史がない。わが国には、織田信長の比叡山焼き討ちなど例外的な狂気もあるが、西洋における過去の宗教戦争や現代のアルカイダやタリバンなどのような民族的な狂気はない」と書いた。今ならIS(イスラム国)も加えなければなるまい。
そしてこの、コトを荒立てない国、日本の民族性は外交の場面でもいまだに生きている。むずかしいトランプ米大統領に寄り添う安倍首相の真情もそれではないか。ついでに言えば、日本のリベラル寄りのマスコミは、戦前の韓国における「従軍慰安婦」や「韓国人強制連行・徴用工」問題を“自虐史観”的に取り上げて日本の責任を言う。また国内的にも、こうしたマスコミは反安保、反基地、反原発を主張する。極端に左寄りの論陣は、コトを荒立てる国を支援するとともに、自国までコトを荒立てる国にする恐れがある。
コトを荒立てる国は世界を不穏にし、争いを呼び、未来の展望に待ったをかけることになる。ただし、いたずらにコトを荒立ててはならないが、コト無かれ主義ではやっていけないことも確かである。国の実力と利害の錯綜する現下の国際社会においては、コトを荒立てない見識とともに、歴史認識と外交上の命題を秤量する政治家の見識が求められ、国家の“立ち位置”を明らかにすることがますます重要になってくる。
(山勘 2018年10月28日)
皮肉なことに、雑誌「新潮45」は、休刊に追い込まれてから有名になった。それまでこの雑誌を知らなかった人が多かったことに驚いた。「そんな雑誌があったのか」とか、「45とはどういう意味か」といった声など、身近でだいぶ聴いた。こうした同誌の知名度の低さは、“論壇誌”の衰退という今日的な状況を物語っている。
同誌は、杉田水脈衆院議員の、LGBTを含む性的少数者は(子供をつくらないから)「生産性がない」とする論文を載せたことが発端で世論のバッシングを受け、休刊(実際は廃刊?)に追い込まれた。杉田氏は、発言に対する非難だけでなく、人格批判の声まであびた。
杉田議員と意見を同じにする者もいるわけだが、世論が沸騰する中でそれを言えば世論の袋叩きにあうのは目に見えている。杉田議員の主張を掲載した同誌編集長の言い分もあるはずだが、それさえ聞こえてこない。
新潮社の佐藤社長も、同誌の立場を弁明することなく、早々と、唐突に、謝罪に出た。性的少数者には触れず、世の中全体に?謝罪した。それによると、ここ数年、同誌の発行部数が低迷していて、部数増を狙った編集上の無理が生じ、「常識を逸脱した偏見と認識不足に満ちた表現」(杉田水脈論文)を掲載してしまったと詫びている。
断っておくが、ここで杉田発言を擁護するつもりはない。しかし、今回の「新潮45問題」を見ていると、リベラルに比べて右翼の発言がしにくい世の中になってきたという印象はぬぐえない。大げさに言えば、「言論の自由」とは何だろうという素朴な疑問である。
たまたま、「言論の自由」に関して、内田樹神戸女学院大名誉教授は、ブログ上で、「言論の自由」には「言論の自由の場を踏みにじる自由」と「呪詛する自由」は含まれないと私は思う、と言っている。教授の言い分は、要するに乱暴な言説や呪詛するような言説は「言論の自由」のラチ外だということである。自由にも“領域”や“制限”があり、そこから排除されるべき自由、“ラチ外の自由”があることになる。本来、自由であるべき“自由”に、道徳的な規範とか、別の基準を用いて“制限”を加えるわけである。
したがって、杉田水脈論文?を掲載した「新潮45」は、雑誌の部数増を焦るあまり、この手の“ラチ外の言論の自由”に走ったものであり、その編集姿勢は、ネット社会における“ラチ外の言論の自由”による攻撃でやられたと言うことになる。
普遍的な姿勢を期待されるマスコミも、とりわけテレビはその“ラチ外の表現の自由”による過熱した世論に左右されて腰が定まらない。ネットを中心とした匿名社会における「言論の自由」は、まさに「ラチ外の言論の自由」を謳歌している。
そこで、根本的な問題は、「言論の自由」に“規制枠”があっていいのかということである。新潮45はけしからんと言って休刊、廃刊に追い込み、それで「事足れり」としていいのかという問題である。フェイクニュースが飛び交うルール無視の世の中で、伝統ある?極右の(あるいは極左の)言論を封じる動きが強まっていいのかという問題である。右も左もあって言論の幅が広いことが民主主義の基盤ではないか。
(山勘 2018年10月28日)