2017年9月28日(木)午後3時~午後5時(会場:三鷹SOHOパイロットオフィス会議室、参加者:狸吉、致智望、山勘、恵比寿っさん、ジョンレノ・ホツマ、本屋学問)
8月は夏休みのため2か月ぶりの例会でしたが、皆さん元気に全員集合でした。書感6本、ネットエッセイ10本と、いつもの倍近い投稿数になり、皆さんの更なる意気込みを感じます。国内経済、政治問題、国際問題まで、いつもながら広いジャンルの話題
が提供されました。奇しくも衆議院の解散が行なわれた日となり、北朝鮮問題はじめ厳しくなる国際情勢や、これからの日本経済は一体どうなっていくのでしょうか。10月も活発な投稿と議論をお待ちします。
(今月の書感)
「どアホノミクスとトラパンノミクス」(致智望)/「肺炎がいやなら、のどを鍛えなさい」(恵比寿っさん)/「検察との闘い」(本屋学問)/「遺伝子組み換えのねじ曲げられた真実(Altered Genes, Twisted Truth)私たちはどのように騙されてきたのか?」(ジョンレノ・ホツマ)/「日中もし戦わば」(山勘)/「米中もし戦わば 戦争の地政学」(山勘)
(今月のネットエッセイ)
「2%物価上昇の公約」(致智望)/「アホノミクス─安倍経済」(致智望)/「サービス」(本屋学問)/「ジョージ・オーウェルの未来小説を読む」(狸吉)/「モノ言わぬ日本人」(山勘)/「やたらにうるさい喋り方」(山勘)/「喧嘩勝負は“気合い”で決まる」(山勘)/「攻撃の気持ちを起こさせない備え」(山勘)/「子供を鍛える?「孫子の兵法」」(山勘)/「“新衆愚政治”の時代?」(山勘
どアホノミクスとトラパンノミクス/浜 矩子(毎日新聞出版 本体1,000円)
 本書は、お馴染みの浜矩子の著書であります。安倍とトランプ、この二人は良く似ているがやっぱり違う、これは同じ穴の貉の同床異夢。これがこの二人の人間関係で、貉退治を試みなければならない。「ア」の字や「ど」の字を語らずに済む時に向かってと言っている。この切り口が本書の論調の始まりであります。
本書は、お馴染みの浜矩子の著書であります。安倍とトランプ、この二人は良く似ているがやっぱり違う、これは同じ穴の貉の同床異夢。これがこの二人の人間関係で、貉退治を試みなければならない。「ア」の字や「ど」の字を語らずに済む時に向かってと言っている。この切り口が本書の論調の始まりであります。
トランプの言っている「アメリカ・ファースト」の保護主義的な通商政策は、輸入品に高関税をかけたり、輸入数量制限を行って急増する輸入を抑えることで、鎖国状態をつくりつつ需要を増やすのだから、インフレ経済が進み不動産バブルの発生へと繋がるのは当たり前と言います。
結果として、自分をホワイトハウスに送りこんでくれた白人労働者への恩義など、忘却の彼方にとばしてしまう。拡張主義的財政大盤振る舞いと大企業優先の減税予算、明らかな矛盾であり、資金需要が強くなり、高金利へと走りだす結果となるから、彼の嫌うドル高へと向かい、アメリカ経済の体力をむしばむ結果となり、彼の政策は矛盾だらけと言う。「アメリカ・ファースト」と言うアメリカンドリームの概念を時代錯誤どころか時代不適合的幻覚症とコキオロシテいます。
アメリカの次に世界の覇権国は無い。中国も国内事情が厳しく、政治経済の先行きに不安を抱いた裕福層は、カネを国外に持ち出すから人民元の為替相場は下落する。それに嫌気して元は益々国外流出が激しくなる。それにも関わらずトランプから為替操作と言われるのだから、トランプは全く解ってない。いまや覇権主義の時代で無い、その世界状況を解ろうとしない、実にアホな大将がアホノミクスと言う。
そして、両者の共通点は、幼児的凶暴性、とにかく二人とも良く似ていて、「黙れ」とか「すわれ」という類の言葉を言ってしまう。この「我慢出来ない」性癖は、大人で無いことの証で、そもそも、国民に対して「丁寧に説明する」と言う言い方、この姿勢がいけない。説明でなく、ご報告申し上げる姿勢、そしてお伺いを立てると言うのが、基本姿勢でなければならない。これはもう、驕り以外の何ものでもないのだ。
2017年版安倍首相の施政方針演説と言うのがあり、そこには、財政健全化への言及が全くなくなった。「2020年まだに基礎的財政収支を黒字にする」と言う目標が全く語られなかったことは極めて重要で、公的債務の実績減を達成し、既成事実を作り上げようと試みる。この魂胆には、注意して掛からねばならない。
安倍さんのブレーンである浜田も感心したと言う、シムズ理論と言うのがある。これは、解り易く言うと意図的無責任財政のすすめで、インフレを起こすことで債務負担を軽減すると言う論法に尽きるといいます。これは、悪くすると国家がデフォルトつまり国家破産につながると言う事で、では、その国家破産を防ぐために何が起こるか、それには統制経済化の始り、国民に全てをおっ被せると言う事。
日銀がマイナス金利などの金融政策を次々と打ち出す理由は、追い詰められてアタフタしている、金融政策に名を借りた財政ファイナンスの成れの果てと言います。
世界で出口政策をとらない、語りもしないのは、日銀だけ。国債発行残高の4割を日銀が持つと言うから、著者の憂いも只ならぬものと感じさせられる書であります。
(致知望 2017年9月5日)
 1957年、福島県生まれ横浜育ち。北里大学医学部卒業。医学博士。
1957年、福島県生まれ横浜育ち。北里大学医学部卒業。医学博士。現在、医療法人西山耳鼻咽喉科医院理事長(横浜市南区)。
第1章 「最近、よくムセる」は老化のサインだった!
第2章 「のど」を鍛えれば、寿命は10年のびる!
第3章 飲み込み力がアップする8つの「のど体操」
第4章 誤嚥を防ぐ「食べる」ルール九か条
第5章 「のど」の大問題・小問題 お悩み解決Q&A
第6章 人間は「のど」から衰え、「のど」からよみがえる!
おわりに
*1:呼吸時は食道が閉じて気管が開いているが嚥下時はこの筋が喉仏を持ち上げて喉全体をせり上げ喉頭蓋が声帯と気管に蓋をする。著者はこれを奇跡のような連携プレーだという。
飲み込み力がUPする8つの方法から3つを選んで鍛えると効果がある。それは
喉の筋トレ ①ごっくんトレーニング
②シャキア・トレーニング
④風船ふくらまし&吹き戻し
⑤吹き矢
⑥口すぼめ呼吸
⑧喉仏スクワット
「食べる」ルール九か条
第1条 食事に集中、ながら食いは厳禁
第2条 大好きな食べ物ほど注意(激辛、お酒はほどほどに)
第3条 まずは汁物は、実は危ない。むせにくい食事の代表は中華料理(柔らか、まとまり、べたつかない)
第4条 つまり易い6つのキーワード(サラサラ、モチモチ、ベタベタ、ボロボロ、ペラペラ、パサパサ)
第5条 大口で食べず30分以内で食べきる
第6条 適度にかんだら飲み込むべし(よく噛めばムセないは嘘)
第7条 早食いもダメ
第8条 軽くお辞儀する姿勢がムセにくい(上を向いて食べるのは危険)
第9条 小骨が刺さった→病院へ(背中を叩くや水を飲ませるはNG)
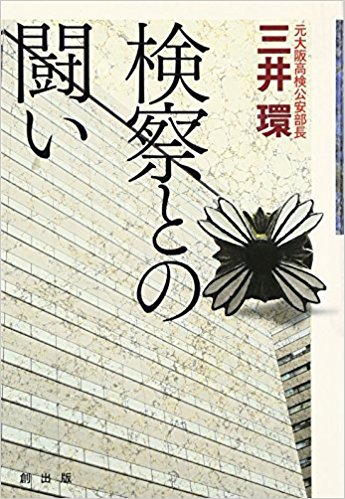
著者は元・大阪高等検察庁公安部長。検察最大のタブーといわれた「裏金問題」を内部告発したため、法務・検察全体の隠蔽工作で逆に犯罪者に仕立て上げられ、1年余の受刑を余儀なくされた。本書は、その顛末を本人が明らかにした手記である。
1999年春、「法務・検察組織の不正義(不正経理)を暴く告発」というタイトルで、検察が組織的に裏金づくりをしているという内容の匿名の告発文書が、大手新聞社や国会議員らに送られた。公私の区別には厳しいはずの検察庁で、「調査活動費」の多くが検察幹部の飲食代やゴルフ代、麻雀代といった遊興費に使われているというのだ。正義の番人があろうことか、税金を使って堂々と賭け麻雀?をしていたことになる。公務員の規範となるべき検察官も、所詮は卑しい“同じ穴の貉(むじな)”だったのである。
世論の厳しい批判に曝されることを恐れた法務省は、全国8地検の次席検事たちを法務省に集め、緊急の対策会議を3度も開いた。現場サイドでは、これを機会に裏金づくりを止めて調査活動費を返上したらという意見も多かったそうだが、法務省は大蔵省(当時)から使途を聞かれてさすがに飲み食いに使ったともいえず、結局は返上しないことにした。当時、法務省全体で約7億円だった調査活動費は、その後名目上は減額されているそうである。
実は著者自身も高知地検や高松地検時代に、この裏金を決済したり裏金で飲み食いしたことを告白しているが、それが全国の検察庁で日常的に行なわれていた。一見、公正に思える検察社会も実際は派閥や情実による生臭い人事が当たり前で、公安専門という職務柄か暴力団関係者とも付き合いがあり、上司や同僚との確執などどちらかといえば傍流を歩いてきた著者としては、思うこともあったのかその後は告発者として現職のまま、実名で新聞や週刊誌、テレビと接触するようになる。
2002年4月、連休明けに朝日新聞に1面トップで告発記事を載せること、当時の民主党の菅直人から、衆議院法務委員会に証人招致することを取り付け、それまで支援してくれていた「週刊朝日」編集長の求めに応じてテレビ朝日「ザ・スクープ」で鳥越俊太郎のインタビューを大阪のホテルで受けることになった4月22日朝、テレビ収録の数時間前に大阪地検特捜部に”口封じ“のために逮捕された。
容疑は、マンション購入で銀行ローンを組むため1週間前に住民票を異動した「公正原本不実記載」、前科調書を検察事務官に指示して入手した「公務員職権乱用」、200万円を無利子で貸した知人から謝礼として私的な飲食接待を受けた「収賄」、退職後に弁護士を開業するために登録免許税軽減措置申請書を受け取った「詐欺」、法律的にはどう考えても微罪でいわば無罪同然のこの事案を、検察は組織防衛ともみ消しをはかるために強権を発動したのである。
本書によれば、同僚の特捜検事たちが訪れた著者の自宅マンションの前には、すでにあの御用新聞の読売の記者が待ち構えていて、さすがに検察は著者やマスコミの動きを把握していたようである。「部長、下手うたはりましたわ」、大阪地検に向かう車のなかで検察事務官がそうつぶやいたという。検事としての著者にまったくスキがなかったかといえば、確かに微妙だったかもしれない。
その後の大阪地裁も高裁も最高裁も、現職検事に対する厳格な司法判断とはいえ、実にいい加減な証拠で強引に有罪にした。著者には気の毒な表現だが、日本の司法がいかに腐り切っているかを如実に示した“好例”である。真に良心や正義感を持つ人なら、裁判官や検事など本当に恥ずかしくてやっていられないのではないか。著者は2年近い刑務所での不便な日常も綴っているが、司法関係者も一度体験入所してみると良い。
本書の後半には、「『小沢VS検察』にみる検察と報道のあり方」と題して、著者はじめ鈴木宗男(国会議員)、安田好弘(弁護士)、上杉隆(ジャーナリスト)、青木理(おさむ、同)、元木昌彦(同)、篠田博之(同)ら、著者を支援してきた人たちが集ったシンポジウムの発言も掲載されている。
小沢一郎議員の政治資金記載不備問題での検察の雑な捜査や、大手マスコミの的外れな報道を厳しく批判しているが、大手紙と権力との癒着はなくならず、冤罪を生む日本の土壌風土はますます深刻さを増している。地に落ちた日本の司法を根底から正すためには、今こそ国民一人一人の意識向上と、社会全体の意識改革が必要なのではないか。現在の国会議員はあまりにも頼りないから。
(本屋学問 2017年9月21日)

著者は、スティーブン・M・ドルーカー(Steven M.Druker)という人物で、公益のために活動する弁護士。ドルーカーが始めた訴訟によって、米食品医薬品局(FDA)は遺伝子組み換え食品に関するファイルを裁判所に提出せざるをえなくなった。その結果、遺伝子組み換え食品のリスクについて、FDAが内部の科学者の警告をもみ消し、真実をゆがめ、連邦法に違反してこの食品を市場に送りこんだ経緯が暴かれた。ドルーカーは、全米研究評議会(NRC)とFDAが開催した食品安全問題パネル討論会に参加したほか、多くの大学で講義し、クリントン大統領の環境評議会の作業グループとの協議にも加わった経験を持つ。
序言を書いたジェーン・グドールは、著者のことを英雄であり、ノーベル賞を受ける資格があると称賛している。
当初、本書に行きつく前に、ロックフェラーという人物が気にかかっていたので、図書館の在庫リストから「マネーハンドラー ロックフェラーの完全支配(アグリスーティカル(食糧・医薬)編 ウィリアム・イングドール著 爲清勝彦訳」を読んでいました。しかし、途中で気が進まずなぜか読むのをやめてしまいました。
原題が、「Seeds of Destruction-Hidden Agenda of Genetic Manipulation(大量殺人種子-遺伝子組み換え操作に隠された陰謀」とあり、ロックフェラーという文字は題名には見当たらなく、出版社(徳間書店)の意図か翻訳者の意図かは知りませんが、原題と違う題名であることを知った。
気を取り直し、「遺伝子組み換え」という表題で図書館の蔵書をチェックし、本書「遺伝子組み換えのねじ曲げられた真実」を、今回、書感に取り上げました。
カバー裏表紙には、多くの著名な生物学者や学術団体が、遺伝子組み換え食品を世に出すためリスクを隠蔽し、真実をゆがめてきた。本書はこの手の込んだ詐欺がどのように行われ、一般国民だけでなく、ビル・クリントンやビル・ゲイツ、バラク・オハマ、その他の明敏で影響力の大きい人物までが騙されたのかを克明に描く。とあり、決定的なごまかしはバイオ産業ではなく科学界主流派からきているということを本書から知った。
科学者らが、真実に対する責任を放棄したことでもたらされた立証責任の転嫁が無ければ、遺伝子組み換え食品の事業は前進できなかったし商品化されなかった。
科学界主流派の不正ごまかしが問題の核心である。
遺伝子組み換え食品を製造するモンサントや他の多国籍企業の違法行為に注目し、これらの企業に総ての問題の責任があると見なしがちだが、科学界の主流派が基本的な事実について政府と国民を組織的に欺いてお膳立てをしないかぎり、遺伝子組み換え食品の商品化は不可能であったことも解明している。
この不正行為が成功し、広がった懸念が実質的に鎮められていなければ、利潤を追求するこれらの企業が遺伝子組み換え食品の開発に必要な巨額の資金を投資したかどうか疑わしい。
ただ、本書は、私には知らない専門用語(委員会名、組織名、財団、アルファベットの略語など固有名詞)の連続で、その都度読み返さなければ前後関係がつかめず、まだ読み切ったという感覚には程遠いものです。
情報の出典は詳しく列記されており唯々感心するばかりでした。
本書を通じて、遺伝子組み換えの真実が浸透し、世界中から廃止される方向に向けられたら、こんなに素晴らしいことはないと思いました。しかし、そのためには、誰が読んでも平易で取っつき易い文章であったらと思いました。一つ一つの文章が格調高く、やたら長いので、注意しながら読まなければならなかった。小目次も省いており、読み直すとき、目的の場所を探すのが大変で、 巻末に索引とか、本文中の専門用語の説明の頁があったらと恨めしく思いました。
「遺伝子組み換え」という言葉は「従来からの掛け合わせによる品種改良」と、何が違うのかそれほど気にかけていない人が多いように見受けられます。
遺伝子組み換え生物とは、例えば畑の雑草を取り除くために除草剤を撒いても、大豆には耐除草剤の遺伝子が組み込まれているため、大豆には影響がなく雑草だけが枯れて、農作業を楽にするのが目的であった。しかし、大豆の表面には農薬・雑草剤が付着している。
あるいは、害虫を殺す遺伝子を組み込んでいる場合は、殺虫剤を噴霧することなく害虫が寄り付かない。いくら、人間には害はないと言われても、そのもの自体が間接的であっても最終的に人間の口に入っていくわけになる。
私自身、遺伝子組み換え食品(大豆・トウモロコシなど)そのものや、それを使った加工食品(調味料や添加物含む)は、取るべきでないという認識は持っています。しかし、まわりには、無頓着な人が多く、「遺伝子組み換え食品」という言葉から、疑いを持たず品種改良の一種で、なぜだめなのかの理由も気にしていない方がおられるのが現状ではないでしょうか。何かの機会にでも分かりやすく説明出来たらと思っていたからです。
そこで、本書の中から、遺伝子組み換え生物が危険と認められながら、握りつぶされた事実の幾つかを列記してみます。調査過程は複雑すぎるので省略します。
遺伝子組み換え作物の多くが自分で昆虫を撃退する殺虫成分「Bt」をつくるように設計。噴霧薬として使われてきた。遺伝子操作された植物で造られた殺虫成分「Bt」入りタンパク質は水路や水中生物にも有害。殺虫成分「Bt」入りトウモロコシの場合、ミジンコに食べさせると健康状態の悪化、高い死亡率、生殖活動の減少、ハチが花粉を探す能力も損なわせるかもしれないことを発見。また、駆除対象の害虫が殺虫成分「Bt」への抵抗性を持つ害虫が増えることになった。
「フレーバーセーバートマト」 成熟した後に収穫しても輸送中、固さが保たれるよう熟れ過ぎにならないよう「風味長持ちトマト」と名付けられた。大半は青いうちに収穫されるものより風味が強いのが特徴。PG酵素という果実を徐々に柔らかくしていくタンパク質の遺伝子組み換え作物であった。実験で一部のラットの胃に病変(出血)が生じた。20匹のうち7匹が2週間以内で死んだ。
実際には蔓についたまま熟すのではなく干からびたため中止となったが、テスト結果については知らされることはなかった。
「トリプトファンという補助食品」(タンパク質の構成要素となるアミノ酸の一種)天然には乳製品や大豆、魚類、獣肉に含まれて、気持ちを安静にして、睡眠をもたらす神経伝達物質セロトニンなどに関係している。補助食品として、不眠、月経前緊張症、ストレス、うつ病などに効果があったが、EMSという好酸球増加・筋肉痛症候群という激烈な筋肉痛が発症し、発症者は5千~1万人、1500人が生涯障害を持ったと推定された。原因は日本の昭和電工の作ったトリプトファンに致死的な原因があることがつかめたが、遺伝子を改変された細菌によるものか精製工程によるものかテストせず、FDAは米国のバイオ産業を守るためにこの情報を隠したように見える。
「モンサントのグリホサート(除草剤)耐性大豆」をマウス 肝臓と膵臓の機能乱れ、睾丸機能も変化 発表したら追放された。
「モンサント NK603トウモロコシ」 (ラウンドアップ除草剤を施しても耐える)ラット肝臓と腎臓に毒による障害、さらに脳下垂体、乳房組織にも発症
等々
以下に、本書の目次を参考までに
遺伝子組み換えのねじ曲げられた真実 目次
第1章 科学の政治化 そして幻想の制度化
第2章 膨張するバイオテクノロジー産業の野望 強まった政治性
第3章 惨事の隠蔽工作 遺伝子組み換え食品による致死的中毒はどう覆い隠されてきたか
第4章 遺伝子、巧妙さ、不誠実さ 生命のソフトウエアを書き直し、事実も書き直す
第5章 不法エントリー 遺伝子組み換え食品の販売許可を強引に進めた米国政府の詐欺
第6章 グローバル化する異常な規制 カナダ、EUなどでも無視された科学と健全な政策
第7章 環境保護の崩壊 多重のリスク、最低レベルの警戒
第8章 米国メディアの機能不全 隠蔽と不正の従順な共犯者
第9章 リスクについての体系的な嘘 見過ごし、異常、怠慢
第10章 収穫された不安データ GMOの研究はどのようにして安全性の証明に失敗し、代わりに市場から追放すべきとの確証を持ったのか
第11章 見過ごされたコンピューター科学の教訓 複雑な情報システムの変更がもたらす避けがたいリスク
第12章 基礎のない基礎的推定 農業生物学を支える誤解
第13章 科学者が「情報操作のプロ」に退化 遺伝子工学の最も悪質な突然変異
第14章 新しい方向性と広がる地平線 遺伝子工学を捨て、安全かつ持続可能で賢明な農業形態へ
読んでいるうち、小保方晴子さんのSTAP細胞の発見をつぶしにかかったのは、自分たちの領域が安泰でなくなり、割り込まれることを防ぐ立場の人が働いたように思えてきた。そういう利害関係の世界の存在があることを垣間見た気がしました。
(ジョンレノ・ホツマ 2017年9月22日)
日中もし戦わば/マイケル・グリーン・張宇燕・春原剛・富坂聡(文春文庫 本体830円)
表紙オビに、本文中の4氏の発言から拾ったこんなコメントがある。『自衛隊を尖閣に駐留させれば、それは「宣戦布告」です』張宇燕(中国社会科学院世界経済政治研究所所長)。『中国がアジアで「覇権」を求め、日本に「上から目線」で命令するのは困る』春原剛(日本経済研究センターグローバル研究室室長)。『米国は、サイバー攻撃の「主要な被告人」は中国だと断じています』マイケル・グリーン(米戦略国際問題研究所日本部長)。『中国共産党は民族解放軍の「暴走」をコントロールできるのか』富阪聡(ジャーナリスト)。本書は2011年刊であるが、今に通じるコメントである。
本誌冒頭の「緊急座談会」では、(2011年の)「ここ数カ月」における中国によるサイバー攻撃の例として、グーグルやロッキード・マーチン、三菱重工業、日本の国会(参議院)などへの例を挙げ、3氏が問題視し、張氏が反論しつつも受けに回っている。
また、3・11東日本大震災時における米軍による見事な支援、日米軍の連携、とりわけロジスティックス(兵站)の実戦的実践が中国に脅威をあたえた事実が語られ、それに比べて時の民主党政権の右往左往ぶりが語られる。いま読み返せば貴重な反省材料である。
本論では、注目される論点の一つとして、尖閣諸島について、米国は日米安保条約で守るべき対象だとしているが、一方で米国は、現在の日本による実効支配は「管理」しているということであり、「所有」していることとは違うと考えているフシがあり、もし紛争がエスカレートして、中国が尖閣に上陸して居座ることがあれば、米国は領土問題に対する不介入の立場で、「外交的解決」を日中双方に望むという態度に出る可能性もあるのではないかという指摘があり、考えさせられる。
さらに衝撃的なのは、本書の「はじめに」紹介している、本誌が刊行される直前の2011年10月、香港誌「亜州週刊」に掲載された、同誌編集長のコラム「中国と日本が最終的に戦争になったらどうなるか」という論考である。それは、日中戦争になれば、「日本は尖閣諸島や東シナ海で中国の原子力潜水艦や高精度ミサイルによって(日本の艦船は)全滅」し、米の第七艦隊が参戦して対中攻撃を敢行しても「中国は中性子爆弾で米空母を殲滅」し、両国が「核戦争というパンドラの箱」を開ければ、「双方が全滅して終わるだろう」というのである。
最終章では、「第5のシナリオ 日中激突リアルシミュレーション」として、①尖閣問題、②朝鮮半島問題、③台湾海峡危機、④米中直接対決、について論じている。
①尖閣問題では、状況が悪化して中国のステルス戦闘機「殲20」が飛来したら自衛隊F15ではかなわないと言う。自衛隊は、いまだに中国に「かなわない」と思わせる戦闘機群を持たない。
②朝鮮半島問題では、金正男は「自分の食い扶持」が問題なので、立ち行かなくなればどこかに何かをドンと撃つ可能性はある」という指摘も今につながる。
③台湾海峡危機では、1996年の中国による台湾沖のミサイル演習では、米国の空母機動部隊派遣で収まったが、今度米国がそれをやれば中国は「引けない」とみて「米中共倒れ」になると言う。
④米中直接対決では、中国が日本を「人質」にとる、すなわち「東京に核爆弾を落とすぞ」と言った場合に、米本土への核攻撃を恐れて中国に核攻撃をしないかもしれない。その時日本は「逃げ道」をどこに求めるか。高度の外交テクニックと共に、タブー扱いの「原発と核抑止力の話」も考えなければならないのでは、と提言する。
本書は8年前の刊行だが、いたずらに流れる年月を味方にますます強大化する中国の足跡と、世界制覇ではなく、確実にアジアの覇権を狙う中国の脅威を知る貴重な一書である。
(山勘 2017年9月25日)
米中もし戦わば 戦争の地政学/ピーター・ナヴァロ著・赤根洋子訳(文芸春秋 本体2,095円)
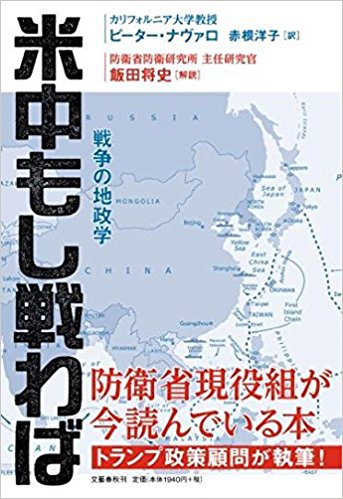
本書の原題は「クローチング・タイガー」(這いよる虎)である。もちろん虎とは中国のことだ。著者は米国の著名な経済学者で、現トランプ政権寄りの対中強硬派だというが、本書は、米国の一流の専門家たちの分析をふんだんに引用しながら、論理的に冷静に記述されている。
本書は、「はじめに」問題提起があり、次いで全6部、全45章が続き、最後に、謝辞、ソースノート、解説となる。6部のテーマは、①中国は何を狙っているのか?②どれだけの軍事力を持っているのか?③引き金となるのはどこか?④戦場では何が起きるのか?⑤交渉の余地はあるのか?⑥力による平和への道、となっている。
中国は、対艦弾道ミサイルによる米太平洋艦隊の駆逐、地球高軌道ミサイルなどによる米の人工衛星撃墜を目指している。中国最南端の海南島には、巨大地下原子力潜水艦基地がある。中国本土で全長5000キロ超の「地下長城」の開発が進み、大量の核弾頭ミサイルが保管され、米国と日本など連合国を標的にしている。こうして攻撃能力を急速に開発しながら、中国は「平和的台頭を望んでいるだけだ」と主張する。
第1部 中国は何を狙っているのか?
第1章 米中戦争が起きる確率は、非常に高いという。世界史を概観すると、1500年以降、新興国家が既成の大国と対峙した15例のうち11例、すなわち70%以上の確率で戦争が起きている。
第2章 中国は「屈辱の100年」という。その間、フランス、ドイツ、イギリス、日本、ロシア、アメリカに侵略され続けてきた。それ以前の中国はアジアの超大国で、ビルマ(現ミャンマー)、ベトナム、ネパール、韓国などの周辺国は朝貢する従属国だった。台湾も征服した。
第3章 世界一の経済大国となった中国は、輸出依存、海上輸送路依存の大国となり、とりわけ中国が輸入する石油の70%が通るマラッカ海峡を重視している。同海峡は、マレー半島とインドネシアのスマトラ島の間の全長800キロの海峡。狭く、浅く、海賊が跋扈する。
第4章 米国が過去にやってきた禁輸措置の歴史、アメリカ海軍の現在の能力、ペンタゴンが中国有事の際に実行すると表明している「戦略的意図」から、中国は米国の禁輸措置を恐れる。
第5章 中国共産党の武力侵略は、1950年の、チベット、新疆ウイグル自治区の征服をもって始まった。その後、朝鮮戦争、ベトナム独立支援、インド侵攻、中ソ国境紛争、南シナ海西沙諸島(英語名パラセル諸島)占領、ベトナム侵攻、南沙諸島(スプラトリー諸島)紛争など。尖閣諸島では1895年以来日本の施政下にあるが、1060年代末に石油や天然ガスの埋蔵が判明してから中国が領有権を主張し始めて両国間の論争が続いている。
一方米国は、朝鮮戦争、ベトナム戦争、アフガニスタン戦争、イラク、ボスニア、カンボジア、リビア、セルビア、シリアを空爆し、チリ、ドミニカ共和国、グアテマラ、イラン、コソボなどに介入。
米中は共に暴力的で核武装した軍事超大国である。武力行使では共に相容れない正当化の主張を繰り返し、経済交流を拡大しながらにらみ合っている。解決の難しい難問である。
第6章 軍事費は中国より米国の方が多い。中国の軍事費は急速に拡大して2000億ドルを超える勢いだが、米国のそれは3倍以上である。中国の過去10年間の対GDP比は2%程度だが、米国のそれは4%近い。
しかし、第1に、米軍は世界規模で戦力投射しているが中国軍はアジア地域だけである。第2に、中国における軍事費は安い人件費、安い製造コストで使い手がある。第3に中国は、軍事研究や兵器開発にほとんど費用をかけない。そのわけは、必要な情報・データをペンタゴンや防衛民間企業から盗み出すハッカーのスキルが高いからである。第4に、購入したテクノロジーなどを模倣するリバースエンジニアリングで模倣品を製造し、世界に売り出す。ロシアの最新鋭戦闘機スホーイの模造品を世界に売り出してロシアの売り上げに打撃を与えた。空母艦載戦闘機Su‐33の模造を非難された時は「オリジナルより性能が良い」と抗弁した。
第7章 第1列島線は、千島列島から日本、沖縄、台湾(中間点)を通り、ボルネオまで。第2列島線は、本州からサイパン、グアム(中間点)を通りインドネシアまで。
第1列島線は中国海軍の行動を束縛する。第2列島線は太平洋の戦略拠点として立ちはだかる。この束縛を打破して、第3段階は2050年までに世界の制海権を握るのが、草葉の陰の劉華清提督の三段階構想だ。
第8章 中国の、「空母キラー」と自称する対艦弾道ミサイルは、大気圏を落下しながら空母や駆逐艦など大海原の小さな目標をロックオンし、追尾しながら回避行動まで取れると言われる。破壊する対象に比べて安価な兵器を「非対称兵器」と呼ぶ。通常は、巡航ミサイル、ディーゼル電気方式潜水艦、機雷や地雷などだが、空母を狙う対艦弾道ミサイルもそのひとつに過ぎない。
第9章 ミサイルは、①発射距離、②発射方式、③ロケット燃料、で分類される。①戦略ミサイル:射程距離は5000から1万5000キロ。長距離弾道弾(ICBM)はこれ。②戦術ミサイル:射程距離は通常300キロ以下。スカッドミサイルがこれ。通常弾頭、核弾頭、化学兵器、何でも搭載できる。③戦域ミサイル:射程距離は①②の中間。300キロから3000キロ以上。「戦域(ある国が属する地域)内の目標を攻撃するもの」。中国が日本などアジア地域の国を攻撃するとすればこれを使う。これらが地下トンネルに収納される。トラック・鉄道路線が走り、ミサイルや発射装置を最高時速100キロで運び、15分で発射現場に到着して準備完了できる。
第10章 2014年に最初の試験が行われた極超音速滑空ミサイルは、マッハ10、つまり音速の10倍、時速1万2000キロで、迎撃困難な新型ミサイルである。新型のDF-31Bミサイルも危険。中国の急峻な山岳地帯での移動・隠匿を考慮した特別使用の大陸間弾道ミサイルである。紛争時に位置を追尾・攻撃するのは困難。
米空母戦闘群と基地が中国の通常型ミサイルで攻撃されたらどう対処するか。ペンタゴンとホワイトハウスの直面する厄介な問題。これについて「エアシーバトル派」と「オプショア・コントロール派」が論戦。前者は中国本土への攻撃を容認。後者は海上封鎖と経済制裁で中国の攻撃に対抗しようという立場。
第11章 第2次世界大戦以降、米の軍艦が沈没または深刻なダメージを被った80%は機雷によるものだった。中国は今、5万発の機雷を保有しているという。種類は30以上。接触機雷、磁気機雷、音響機雷、水圧機雷、遠隔操作機雷、自走機雷、ロケット推進式上昇機雷などがある。うち、ロケット推進式上昇機雷は、深水1800メートルの深海で、内臓コンピュータが軍用艦の通過に固有の音響的、電気的、磁気的、圧力的特徴を感知し、時速280キロで目標に向かう。
第12章 弾道ミサイルを搭載した中国の潜水艦は現在、シアトルやシカゴ、ニューヨークなど米の諸都市を核弾頭で攻撃する能力を持っているという。米の抑止力・報復攻撃の3本柱は、①地上発射大陸間弾道ミサイル、②長距離爆撃機、③弾道ミサイル搭載原子力潜水艦だが、確実な破壊力を有しているのは③の原子力潜水艦である。
第13章 中国はヨーロッパの手に入れた。米や日本やベトナムの海軍艦艇を破壊する能力を持った通常型ディーゼル電気方式潜水艦の場合は、スランス、ドイツ、ロシアの最新軍事技術を導入している。
第14章 中国の「遼寧」は、米軍には危険をもたらさない。小型空母で新型電子機器や兵器はほとんど搭載されていない。しかし、022紅稗型ミサイル艦は、全長45メートルの小型艦だが、ステルス性に優れ、巡航ミサイル2発を搭載し、時速75キロの、接近阻止戦略に最適の艦艇である。その中国ミサイル艦100隻が、米の空母戦闘群に「一斉射撃」を浴びせ、同時に対艦弾道ミサイル、地上発射巡航ミサイル、攻撃型潜水艦の魚雷やミサイルが襲い掛かったら数で圧倒される。その中国ミサイル艦はオーストラリアの設計図を元に建造したものである。フランス製ディーゼルエンジンを搭載した軍艦から発射されるロシア製ミサイルである。
第15章 中国は2大戦略で空軍近代化プログラムを進めてきた。一方の戦略は、ビンテージものの航空機の退役、もう一方は米のF‐22やF‐35に匹敵する新鋭第5世代戦闘機の開発である。米議会は、経済的理由からF‐22の製造を200機足らずで中止した。反対に中国は、F‐22とF‐35のコピーバージョンの製造を急ピッチで進めている。例えば成都J‐20はF‐22とF‐35の要素を併せ持つ多用途戦闘機で、J‐31はF‐35を思わせる。
第16章 中国に、人工衛星兵器の威力を見せたのは1991年の第1次湾岸戦争だった。中国は、米の人工衛星を攻撃するための「暗殺者の棍棒」の開発に励んできた。目的は、「宇宙空間にある米国の目と耳を拒絶し、退化させ、欺き、妨害し、破壊する」ことである。中国の対衛星兵器は「ハード・キル(直接攻撃)」と「ソフト・キル(誘導かく乱)」の2つのカテゴリーに分類できる。
第17章 中国では、国がハッカー育成に力を入れている。技術系の私立学校や「ハッカー専門学校」、ハルビン工業大学などでサイバースパイ活動に必要な工学や数学の高等教育を受ける。魅力的な進路は外国、米国の大学だ。人民解放軍のサイバー部隊は10万人。上海のATP1部隊はエリート・ハッカー部隊で、ここだけで米などの主要産業140社以上のセキュリティシステムに不正にアクセスしている。
第18章 心理戦、メディア戦、法律戦を「三戦」と呼ぶ。「心理戦」は、相手国を脅したり、混乱させて反撃の意思をくじくことであり、そのために外交圧力、風評、嘘、嫌がらせなどで不快感を表明し、覇権を主張し、威嚇する。「メディア戦」は、国内外の世論を誘導し、騙されやすいメディア視聴者に中国側のストーリーを受け入れさせることである。「法律戦」は、国際秩序・ルールを都合よく曲げる、書き換えることである。
第19章 中国の軍事力は、最初の国土と自国の経済的利益を純粋に守るところから、今では近代的で攻撃的な軍事力へと危険な変貌を遂げ、いずれは世界的に展開する軍事力を持つだろう。現状変更意図を持つ中国の軍事力は増大を続け、紛争を起こす可能性も増大を続ける。
第20章 戦争が起きる可能性は、当事国の利益が大きいほど高くなる。この原則に基づけば、米中戦争の引き金になりそうなものの筆頭は台湾である。台湾は、戦略地政学的には第1列島線の中央にある。これを失えば中国は西太平洋の第1列島線内に閉じ込められてしまう。米国にとっては、台湾は第一列島線で唯一発展した部分であり、米がここから立ち去ることは、中国海軍が、ほとんど自由に太平洋に出ていける門を開くことになる。
第21章 北朝鮮が崩壊しないのは中国のおかげ。北朝鮮が輸入するエネルギーの90%、食料の45%を供給している。中国は命綱でこれが切れれば崩壊する。中国が、核戦争に巻き込まれる恐れのある北朝鮮にテコ入れするのは、北朝鮮が崩壊したり韓国と和解した場合、この国は民主的な米韓側に付くだろうということである。
第22章 「日本の核武装」は「日本が中国に乗り換える」シナリオより悪い。残るは「ぶれない同盟国」シナリオだが、これがマシかどうかは、日米の軍事同盟強化に中国がどう反応するかにかかっている。「ぶれない同盟国」は平和に貢献する。中国は探りを入れ、弱点を見つければ前進してくる。進んでみて相手が強いと見れば撤退する。カギは、米国のアジアに対する熱意と決意である。
第23章 南シナ海は、世界有数の豊かな漁場であり、海底にはペルシャ湾に匹敵する石油、天然ガスが眠る。インド洋への玄関口であり、日本や韓国への石油の大半がここを通過する。米中戦争の火種になりそうな場所は、南シナ海の、1つは西沙諸島であり、これはべトナムとの紛争地である。いま1つは、南沙諸島であり、フィリピンとの紛争地である。ベトナムは、日本やフィリピンのように米の核の傘に入りたいと考えている。しかし米と安全保障条約を結べばそれ自体が戦争の引き金になりかねない。
第24章 南沙諸島は、上記の各国沿岸から近い、戦略的に重要な海域に位置し、40万平方キロメートル以上にわたって島々が点在する。最も近い島でも中国大陸からは950キロ以上離れている。南沙諸島の40以上の島々に、5カ国(中国、マレーシア、フィリピン、台湾、ベトナム)の軍隊が駐留する。極小の面積に、ペリポート、飛行場、埠頭や港、砲座があり、要塞化している。特に中国が1994年にフィリピンから奪取したミスチーフ環礁は、5階建てのコンクリート製掩蔽壕や八角形の高床式建物3棟が、ずらりと並んだ対空砲に守られている。本格的な駐屯地だ。
第25章 中国は、「航行と上空通過の自由は、排他的経済水域内でも制限される」という従来にない立場を取っている。対米国「三戦」の一手である。中国は「閉じられた海」を実現しようとし、米国はそれを容認できない。台湾独立が中国の譲れない一線だとすれば、航行と上空通過の自由は米国にとって譲れない一線である。
第26章 中国が奪取したチベットは、インドの水源地帯の多くを支配している。タイ、ラオス、カンボジア、ベトナムで海に出るメコン川、ミャンマーを流れるサルウィン川、10の大河の源流である。インドを流れるプラフマプトラ川の水量の60%を、流れを変えて水量の減り続けている黄河に引き込みたいという中国の意図にインドは怯えている。プラフマプトラ川は、ヒマラヤ山脈からチベットを東へ3000キロ流れ、アルナーチャル・プラデーシュに出て、Uターンしてインドのガンジスと合流し、最後はバングラデシュでベンガル湾に注ぐ。
第27章 「政権の内憂が、戦争という外患の引き金を引く」というロジックは、国際関係理論として認められており、「陽動外交政策」とか「陽動戦争」などと呼ばれる。国内的には、イデオロギーよりもずっと単純でしばしば残酷な独裁主義、対外的には中国的なナショナリズムで、外部に敵役を作る作戦を取る。中国マスコミ的には、過去を反省せず再び軍国主義化する日本、中国固有の南シナ海の島々を狙う野蛮なフィリピン、石油や天然ガスを狙う裏切り者ベトナム、領土分割を狙う悪辣な米帝。
第28章 中国政府も中国共産党も民主的な組織ではないが、官僚、産業、軍、地方からの幅広い利権圧力の影響を受けている。この「派閥の弊害」が、エスカレーションの危険が高いボトムアップの行動や決定につながる恐れがある。「地方官僚はまず行動を起こし、北京が反応しなければ続行する。必要なこと以外はいっさい中央に報告しない」と言う。
第29章 現在の中国におけるロシア大統領ウラディミール・プーチンの評価は、ロシアの偉大な英雄で「プーチン大帝」などとも呼ばれる、この元ソ連KGB長官に関する本が飛ぶように売れて、よくベストセラーになるという。露の選択は米国主導の「バランス連合」に加入して世界の安定と平和に貢献することだろう。しかし露は、クリミア併合後、反対の方向、中国の腕の中へと進んでいるようだ。
第30章 現在は、米軍の方が技術的に優れている。しかし中国はその差を急速に縮めている。中国は、サイバースパイ作戦、伝統的なスパイ作戦、外国製兵器のリバースエンジニアリングを組み合わせて外国の軍事技術を盗み出している。さらに、ボーイング、キャタピラー、GE,ゼネラルモーターなど、米国の製造業の多くが中国に拠点を移しており、「軍民両用」の技術が中国軍に転用されている。
サイバースパイ行為の結果、中国は米国のアジアの航空支配の要である第5世代戦闘機と同等の戦闘機を手に入れ、大量のドローンを生産し、イージス戦闘管理システムを盗み出した。さらに中国は、冷戦時代スタイルの従来型のスパイ行為で、弾道ミサイルや巡航ミサイルの技術を盗み出し、大量生産されたそれらのミサイルは、米艦船、前進基地、諸都市に向けられている。
現在、中国の領空を防衛しているのは世界最強のロシア製防空システムである。他にオーストラリア、フランス、ドイツなどの技術で最新の潜水艦、ヘリコプター、ミサイル艦を製造している。中国の戦略は、米のイージス搭載艦を目がけて、対艦弾道・低高度巡航・高高度超音速ミサイルを大量に異方向から発射する。
第31章 第1列島線上の主要な基地は、中国第2砲兵部隊がすでに標準を合わせている。日本で本土の佐世保及び横須賀、横田、沖縄の加手納、トリイステーション基地。基地は固定されているので、繰り返しミサイルで攻撃される。滑走路上の航空機だけではなく、弾薬庫、燃料タンク、兵站支援施設などの壊滅で、列島線上の作戦継続機能が失われる。
第32章 アジアの米軍施設が中国に攻撃されたらどう対処するか。1つ目(選択肢1)は「エアシーバトル」戦略で、反撃を視野に入れている。これはペンタゴンの総合評価局が唱える戦略。2つ目(選択肢2)は、「オフショア・コントロール」戦略で、海上封鎖によって中国の世界通商路を断つというもの。米国国防総合大学のハメスらの唱える戦略。3つ目(選択肢3)は、以上の2つの戦略を組み合わせた「ハイブリッド」戦略がある。これは両戦略の「最良部分」を組み合わせるか、「最悪部分」を組み合わせるかという問題がある。
第33章 海上封鎖の実行では、チョークポイント(隘路)はマラッカ海峡だけではない。北端は北海道とサハリンに挟まれた宗谷海峡。沖縄と宮古島の間の宮古海峡(幅300キロ)。台湾とフィリピンの間のルソン海峡がある。これで中国は太平洋への出口を塞がれる。インド洋への出口は、マラッカ海峡以外に、これと同程度に危険なスンダ海峡とロンボク海峡(いずれもインドネシア)がある。
第34章 米中間で通常戦争が勃発した場合、3つの選択肢、①短期戦 ②長期戦 ③核戦争、について考える。望ましいのは①だが、最も実現の可能性が低い。③は論外だ。セカンドベストな選択肢は②となる。つまり、はっきりと決着がつかなかった朝鮮戦争の再来である。そして冷戦時代が来るかもしれない。
第35章 米軍はアジアから撤退すべきか。米軍が撤退すれば、韓国は自前の核兵器を開発する。日本は即座に大量に製造できる。中国の正気を戻す核戦争の道を選ぶかもしれない。米国の目的は、米国の将来の経済的発展と安全保障を確かなものにすることであり、そのために必要なものがアジアにおける米のプレゼンスである。
第36章 クリントン米大統領は、中国のWTO加盟を支持するよう議会に要求した。世界人口の5分の1の市場に、米国の労働者が作った米国の製品を、米国の会社が販売できる、と言った。しかし米産業界のクリントン支持者たちは一斉に生産拠点を中国に移していった。そして、米国内では7万の工場が閉鎖され、失業者・非正規雇用労働者は2500万人を超え、米の貿易赤字は年間3000億ドルに達した。現在の対中赤字は数兆ドルに達している。中国に平和への期待を寄せないほうがいい。逆に、経済的関与を削減することが中国の軍事力増強を抑える選択肢かもしれない。
第37章 軍事衝突が起きても、経済・金融で依存度の高い中国に対する経済制裁は取れない。取れば当然、軍事衝突の可能性が高まる。
第38章 米中双方に確実な核報復能力がある場合、戦略的安定が生まれる一方で、代理戦争やより低次元の通常戦争が起き得る。中国が、アジアから米国を撤退させられる軍事力があると合理的結論に達し、米国が経済的、道徳的、国家安全上、撤退は不可と合理的結論に達すれば、第3次世界大戦となる。
第39章 冷戦中に核爆弾が1つも落ちなかった理由の1つは米ソが対話に前向きだったこと。米大統領とソ連書記長がホットラインでつながり、公海上では両国の海軍司令官が定期連絡を取っていた。さらに米ソ間では、互いの衛星ネットワークには手を出さない暗黙の了解があった。両国が重ねた条約交渉が両国の核軍備の驚くべき透明性につながり、核軍縮を革命的に前進させた。残念ながら現在、米中間にこのような「エスカレーション遮断機」はない。米中が交渉によって平和への道を探ることは難しい。
第40章 「大取引」で平和は訪れるか。大取引すなわち、¥米国は台湾の防衛を放棄する。それと引き換えに、中国は東シナ海・南シナ海におけるその他の領土要求をすべて放棄するとともに、米軍がアジアに駐留し続ける権利をも認める」ことはあり得ない。中国は、台湾と引き替えに尖閣諸島を放棄したり、南シナ海の問題で譲歩したりはしない。攻撃的で不透明な中国と実りある交渉は困難で、大取引は実行不可能、だとすれば、残るのは「力による平和」以外にないと思われる。
第41章 「米中戦争は起きるか」という大問題に対する最終回答は、米国とアジアの同盟諸国が取るべき方策を検討し、総合国力の連合によって平和を構築できるかどうかにかかっている。ブルーメンタールらは、これまでの米国の戦争は、決断力と意思を疑問視されて起きた。だから、強力な軍隊と同盟関係を構築し、敵に米国は本気だ。最後は武力を用いると信じさせろと言う。
第42章 中国の経済力の背景をまとめれば、①中国は、通貨操作、違法な輸出補助金、知的財産権侵害、自国市場の保護など、数々の不公正な貿易方法。②経済成長と強力な製造基盤が軍事力強化をもたらした。③経済力と軍事力を背景に貿易や領土問題などで近隣アジア諸国を威圧してきた。④2001年に中国がWTOに加盟し米国市場に自由に参入して以来、米国は7万カ所以上の製造工場を失い、経済成長率は半分以下に縮小した。⑤逆に米国は、経済成長の減速と製造基盤の弱体化により、自国の安全保障とアジア同盟諸国への条約義務を遂行する軍事力の維持が困難になりつつある。
とすれば、米国の安全保障とアジアの平和のためには、中国製品への依存度を減らすことである。逆に言えば、まず必要なことは、米国経済の健全化だ。これは米国国民と政府の努力で成し遂げられることだし、中国政府はそれをどうすることもできない。
第43章 「軍事力による平和」を考えれば、中国の軍事力を上回ることである。米国の戦略三本柱は、①圧倒的な制空権・制海権を持つ空母戦闘群、②第1・第2列島線上の数カ所の大規模基地、③戦場の状況認識を行う人工衛星システム、の3つである。中国の戦略三本柱は、米国の三本柱を破壊する戦略である。①米の空母戦闘群と基地を破壊する安価な非対称兵器の備蓄、②将来的に米国のそれを凌ぐ空母戦闘群の生産、③人工衛星システムC4ISRの打破。
アジアの米軍基地は、「強化」が必要だ。燃料タンクや兵器庫を地下深部に移動させる。航空機をサイロに収納する。コンクリートと鉄筋で滑走路や建物や兵舎や埠頭を要塞化する。アジアの基地を小規模の基地に分散する。人工衛星資産も、宇宙通信中継点の数を大幅に増やし、そのサイズを小さくする。
抑止力の鍵は、潜水艦戦と機雷戦である。チョーク・ポイントに攻撃用潜水艦を並べ、水中「長城」を構築する。同時に機雷戦能力を向上させる。さらに、第5世代の戦闘機F‐35や現在空軍が開発中の長距離攻撃爆撃機を大量に増産することである。F‐35ジェット戦闘機をアジア地域全体に分散・配備する必要がある。そして長距離攻撃爆撃機は、空母戦闘群や基地が破壊された時の保険としてだけでなく、無人の大陸間弾道ミサイルに代わる、はるかに安全な兵器でもある。
第44章 米国は同盟国を守り抜かなければならない。米国は、自国の経済的及び安全保障上の利益を守るためにアジアの同盟諸国を必要としている。そしてアジアの同盟諸国は、中国の拡張主義から自国を防衛するため、米国の安全保障の傘を必要としている。
第45章 中国の脅威を直視する。中国の現状変更的意図、急激な軍事力増強、次第にエスカレートする侵略行為を合理的に判断すべきだ。しかし民主主義の性質と利害の競合でその合意は容易ではない。たとえば米国の製造業界は真っ二つに割れる。一方の側には、中国の不法な輸出補助金によって大打撃を被っている無数の中小企業がいて、中国に通貨操作をやめさせろ、相殺関税などで救済策を取るべきだと主張する。一方には、アップル、ボーイング、キャタピラー、ゼネラルモーターズ、IBMといった、米国に本部を置く一握りの多国籍企業がいて、中国で生産した製品を中国の助成で有利に輸出している。同盟関係を守るためには、「中国はアジアの安全保障にとって大きな脅威となり得る」という政治的合意が必要だ。
中国は、経済の高度成長とともに石油など感慨資源への依存度を高めてきた。そして世界第2位となった経済力と、米国に拮抗する軍事力を背景に、アジアの多くの国々に対して領土侵攻と権益拡大の野心をむき出しにしている。その具体的な実例は本書が示すように枚挙にいとまがない。いま顕著な中国の狙いは、資源確保のために必要な中東やアフリカに向かうチョーク・ポイント(隘路)のマラッカ海峡の通商路確保であり、尖閣と東シナ海にまたがる海底石油の確保である。特に尖閣は、海底石油の埋蔵が発表された1968年以降、猛烈に所有権を主張し始めた。
その先には、台湾の奪回があり、米国による対中国包囲網の第1列島線、そして第2列島線の打破がある。そのために中国は、着々と軍事力の増強を図っている。現在は米軍の方が技術的に優れている。しかし中国はその差を急速に縮めている。
その中国の近代兵器はすべて、サイバースパイ作戦と外国製兵器のリバースエンジニアリングで米露及び欧州先進国から“盗み出し”た軍事技術によって開発・製造されたものである。中国の領空を防衛しているのは世界最強のロシア製防空システムである。他にオーストラリア、フランス、ドイツなどの技術で最新の潜水艦、ヘリコプター、ミサイル艦を製造している。そして中国は、米国の第5世代戦闘機と同等の戦闘機を手に入れ、弾道ミサイルや巡航ミサイルの技術を盗み出し、大量のドローンを生産し、イージス戦闘管理システムを構築し、大量生産している。それらの兵器は、米艦船、前進基地、諸都市に向けられている。
米のイージス搭載艦に向けては、対艦弾道・低高度巡航・高高度超音速ミサイルと言う「非対象兵器」(艦船など高価な兵器に対してミサイル、魚雷など安価な兵器)を大量に異方向から発射するというもので、そうなれば米の誇るアジアにおける空母戦闘群の戦力喪失につながりかねない。
本書の示す方向は、「軍事力による平和」である。中国の軍事力を上回ることである。米国の戦略三本柱は、①圧倒的な制空権・制海権を持つ空母戦闘群、②第1・第2列島線上の数カ所の大規模基地、③戦場の状況認識を行う人工衛星システム、の3つである。中国の戦略三本柱は、米国の三本柱を破壊する戦略である。①米の空母戦闘群と基地を破壊する安価な非対称兵器の備蓄、②将来的に米国のそれを凌ぐ空母戦闘群の生産、③米国の人工衛星システムの破壊とかく乱、である。
こうした中国に対する抑止力の鍵は、潜水艦戦と機雷戦である。チョーク・ポイントに攻撃用潜水艦を並べ、水中「長城」を構築する。同時に機雷戦能力を向上させる。さらに、第5世代の戦闘機F‐35や現在空軍が開発中の長距離攻撃爆撃機を大量に増産することである。F‐35ジェット戦闘機をアジア地域全体に分散・配備する必要がある。そして長距離攻撃爆撃機は、空母戦闘群や基地が破壊された時の保険としてだけでなく、無人の大陸間弾道ミサイルに代わる、はるかに安全な兵器でもある。
さらに、アジアの米軍基地は、「強化」が必要だ。燃料タンクや兵器庫を地下深部に移動させる。航空機をサイロに収納する。コンクリートと鉄筋で滑走路や建物や兵舎や埠頭を要塞化する。アジアの基地を小規模の基地に分散する。人工衛星資産も、宇宙通信中継点の数を大幅に増やし、そのサイズを小さくするなど、防衛体制の見直しも指摘する。
そして、何よりも大事なのは、米国が同盟国を守り抜かなければならないということだと本書は言う。米国は、自国の経済的及び安全保障上の利益を守るためにアジアの同盟諸国を必要としている。そしてアジアの同盟諸国は、中国の拡張主義から自国を防衛するため、米国の安全保障の傘を必要としている、ということである。
結論的に言えることは、米国が同盟国を本気で守る姿勢を示し、同盟国の信頼を得られるならば、中国がうかつに手を出すことを抑止できると本書は言う。その大事な原点を軽視しがちな米国ファーストのトランプ氏が大統領になった今こそ、米国の対中戦略の建て直しが迫られている。2017年版防衛白書は、核ミサイル開発を進める北朝鮮と海洋活動を拡大する中国に焦点を当てて、緊迫化する日本周辺の安全保障環境を分析している。本書はまさに今読まれるべき一書と言えよう。
2%物価上昇の公約
最近の安倍首相は、2%物価上昇の公約実現に焦り始め、働き方改革と称する怪しげな政策を言打ち出した。同一労働同一賃金、最低賃金の引き上げ、時間外労働の上限規制などである。この「聞こえの良い政策」は建前ベースとしか考えられない。
我々ハイテク技術を以て経営に携わる企業に、同一労働同一賃金などは、理想論であって現実不可能な手法なのだ。そんなことは、何十年も前から言い古された戯言で、今に至っても悩み続けている問題だ。
理由は単純明快、正確な成果評価を誰がやるのか。評価する者が評価される者より優れていなければ出来る事ではない、神のみが出来る所業と考える。
若き天才的社員の業績評価をゴマすり出世の爺達に出来ると思っているところに、事の進まない原因がある。この単純な原則を理解出来ない筈はない、単純であるからこそ勘ぐられるのだ。
安倍さんの本音は何処にあるのか。最低賃金の引き上げ策についても、ついてこられない企業はつぶれて貰う、生産性の高い企業にその労働力を移すと言うことが、既にブループリントとしてあると言うから、それならそうと言うべきで、言わないところが安倍流の様な気がする。
人間の思考、所業に付いて、簡単に善悪、良非の差、など評価出来るものではない。我々は何十年来苦労してきたテーマである。その程度の政策しか考えられないところが、既に見透かされていて、労組は反対するのだ。
それに対して、更に低レベルな意見には失望する、折角の首相の提案を無にした労組連は、勝手な奴らでケシカランと頓珍漢な批評をする評論家や新聞記事をみるに至り、本気で問題提起し論議する気があるのか、時間の浪費を楽しむ、井戸端会議、お茶のみ話の域を出ない。情けない知識層としか言いようがない。
一度、業績不振に陥った日立製作所であるが蘇りの機運である。流石日本の産業源流と言われる日立製作所だと思う。社会インフラに経営の軸足を置くと言う。その日立が、最も困難な東京電力の会長職、社長職を引き受けると言う、この火中の栗を拾うことの意義を考えてみる。
放っておけない義侠心と考えるが、それも有るだろう。しかし、日立は自社に原発建設の事業をかかえている。私の考え過ぎかも知れないが、これはリスクを選択し将来の肥やしと考える経営戦略かも、どちらにしても凄いことである。社会貢献を考えた営業戦略とするなら、これは「経営の芸術に値する」の一言で誰も多くを語る資格は無い。
そもそも、前述の「働き方改革」もそうであるが、政府のやる事は親方日の丸で組織を運営する者にガバナビリティーが無い。だから、何をやってもうまく行かない、嘗ての東芝再建に尽くした土光さんのような優れた人物は、滅多に出現するものでは無いと思うが。しかし、いざと言う時に現れるのが、我が日本国政界であり、企業界と思うが如何なものか。
私は、日立製作所の所業に「喝采あれ」とエールを贈る者である。
アホノミクス─安倍経済
日本の経済は、貿易立国として成り立っている。だから為替も円安でなければならない。
安倍ノミクスは、成功していると言うが、円安で株高になり、円高で株安となる、この流れは、不自然であり、今の世界経済における日本の実態である。この現実からみてアベノミクスは、世界経済の潮流に只乗っているだけと考える。
虎の子政策たるアベノミクスは反映されておらず、たまたまの幸運をみすかされ、政策を信用していない、だから企業は、利益を内部留保に積み増し、個人は蓄財に励むのであり、実経済市場にカネが出回らない。
今のドル高/円安は、何時まで続くかを考えてみたい。2018年には、アメリカの中間選挙がある、そこでトランプ政権は有権者の審判を受けるので、公約通り対日貿易赤字を減らす必要がある。そのために、最も手っ取り早い方策が円高である。そうなると当然、日本の株価は下がる。そして、アメリカの金利が上がる、すると新興国の経済に打撃を与え、ドルを持った投資家軍団は、そのドルを引き上げて日本めがけて円買に向かう。すると、円は更に上昇する。これが今の世界経済の筋書と考える。
この現象は、現時点でも気が付かない程度に進行していると言われている。ドルが世界経済の基軸通貨であるがための宿命なのだ。その宿命を断ち切りたいのがトランプのアメリカ・ファーストと考える。
トランプの政策を米国民は支持するのか、基軸通貨を守りつつアメリカの繁栄を維持すると考えるのが民主党の考えだが、それとて難しいのが一般論である。
アメリカの将来像を考えるとトランプの言うアメリカ・ファーストは妥当であり、他に選択しは無いと言うのがネイティブ層の発想のようだ。
加えるに、トランプの白人優先主義や品の無い道言から来る問題も無視出来ず、やがては、アメリカのドル破綻への道を辿らざるを得ないであろう。
ロシアなどが虎視眈々とその時を狙うのも肯ける。せめて私の生存中は起こってほしくないものだ。
(致知望 2017年9月6日)
昨年6月、100歳になった岳父を飛行機に乗せて長女が嫁いだ高知に行くことがあった。羽田空港の受付で妻が父の百寿のことや今回の旅行の目的などを話し、まだ普通に歩けるが安全を考えて搭乗口まで車椅子を借りた。機内に乗り込むまで女性の係員が父に付き添い、実に親切に応対してくれた。
1時間の快適な空の旅を終えて高知空港に着くと、出口で車椅子を用意して待っていてくれた全日空の客室乗務員が、「蛍観られるといいですね。お孫さんと素敵な時間をお過ごしください」と手書きしたジャンボ機のビニールの玩具を父に手渡してくれた。羽田空港で何気なく話したことが、クルーにちゃんと伝わっていたのである。さすがに父は照れくさそうだったが、普段は鈍感な私も、この細やかな心配りにはすっかり感激してしまった。しかも、帰りの便は満席でなかったためか、私たちの席をわざわざ搭乗口近くに変更してくれていた。数か月後、父はその忘れ得ぬ思い出とともに冥土に旅立った。
先日、インターネットニュースを見ていたら、やはり国内のエアラインであった似たような話が紹介されていた。「お連れ様はどちらですか?」というタイトルの、西日本新聞の記者が書いたコラムである。
半世紀以上連れ添った伴侶に先立たれた男性が、故郷である佐賀県唐津市の寺に妻の骨を納めるため、羽田空港から九州に向かった。遺骨を機内に持ち込めることは知っていたが、収めたバッグがかなり大きく、念のため搭乗手続きの際に中身を伝えた。
機内に入り男性が棚にバッグをしまって座席に着くと、客室乗務員がやってきてこういったそうだ。「隣の席を空けております。お連れ様はどちらですか?」。搭乗手続きで説明したことが機内に伝わっていたのだ。男性が「上の棚です」というと、乗務員はバッグごと下ろしてシートベルトを締めてくれた。飛行中には「お連れ様の分です」と飲み物も出してくれたという。
「最後に2人でいい“旅行”ができた」と男性。その表情を見ていたら、こちらも温かい気持になった。記事はこう結んでいるが、おそらく記者の知人か誰かの話らしく、遺骨の扱いは実際どこでも制限が多いので、この話を信用しない人がいるかもしれない。しかし、私の数少ない体験からは、日本のエアラインのスタッフたちは皆、このような気持でサービスにあたっていることは想像に難くない。
一方、離島の空港で専用設備も規則にもないという理由で、車椅子の乗客を自力でタラップを上がらせたエアラインの職員のことが話題になったが、もしこの話が本当だとしたらおそらく例外中の例外だ。まったく融通の利かない、思いやりのかけらもない人間もたまにはいる。
鉄道でもレストランでも、デパートでもホテルでも、日本人の他人に対する心配りは世界一といわれている。改めて“オ・モ・テ・ナ・シ”などと喧伝しなくても、日本人は昔から当たり前のようにそうしてきたのである。もっとも、それをおせっかいと受け取り、構わないでほしいという人もいるので一概にはいえないが。
アメリカの大手航空会社が定員オーバーの乗客を無理やり引きずり降ろすシーンが紹介されて、この国の“定評ある”サービスの現実が世界中に知れわたった。人種問題といいセキュリティ問題といい、この地で不愉快な思いをした外国人は数多い。建国して250年の歴史しかない新興国の悲しさである。
最近、経済産業省が製品の品質や性能、安全性などを定めるJIS(日本工業規格)の対象に「サービス分野」を追加することになったそうだ。まだ正式に決まったわけではないが、JIS制定以来70年ぶりの大幅見直しとかで、アメリカを始めとする世界のルールづくりの動きに対応するのが狙いらしいが、現在も世界最高の日本のサービスを、どうして低レベルの国際水準に合わせる必要があるのか。
そんなことよりも、肝心の日本のものづくりや研究教育制度が怪しくなっている。JISも原点に戻って、再び先進工業国家を目指す明確な指針を示すべきではないのか。これでサービス分野も“国際水準”になり下がったら、日本が誇れるものは何もなくなってしまう。
(本屋学問 2017年9月10日)

かの有名な近未来の反ユートピア小説1984年を久しぶりに新訳(高橋和久訳、ハヤカワepi文庫)で再読した。本書はイギリスの作家ジョージ・オーウェルが1948年に発表した、全体主義国家で生きる恐怖を描いている。その国で生まれた子供たちは、幼い頃から独裁者を崇拝し、これに反する思想を持つものを告発するよう教育される。告発された者は秘密警察の手で徹底的に思想改造され、完全に転向したと判定された後に消されるのだ。
小説の主人公(1944年か5年生まれの男性)は、現在の1948年よりずっと以前の記憶を持っているため、政府の発表に疑問を抱く。
この国では政府の発表のみが真実であり、自分の記憶を持つことは犯罪なのだ。主人公は日記をつけるという重大犯罪を行い、それを隠し通していると信じていたが、実は日常的な監視下にあったと知り驚愕する。囚われて陰惨な拷問の末、完全に思想改造され、独裁者を心から愛するようになって処刑されるという、何とも救いの無い物語である。
この著者が本書に先立つ1945年に書いた「動物農場」には、本書の原型とも言うべき状況が描かれている。農場で飼われていた動物たちが人間の農場主を追い出し、理想的な共和国を築こうとするが、その中の豚が独裁者と化し、恐怖政治社会へ変貌していく。ドグマの強制、支配階級の特権、記憶の消去と過去の改竄など、1945年と同じ筋立てだ。
さて、こんな馬鹿げた世界が現代に出現するだろうか?国民学校で軍国主義教育を受け、幼い頭に「神州に生まれた幸せ」をビンタと共に叩き込まれた「ボクラ小国民」は、あのまま育っていたら、家族や知人でも反戦的な者は、容赦なく「非国民」として通報していただろう。振り返れば、ナチス、旧ソ連、赤狩り時代のアメリカ、大日本帝国、ポルポト、イスラム原理国、北朝鮮など皆似ている。国家体制など一人の野心家によって、一夜にして改変可能なのだ。一旦変われば大半の庶民は嬉々として指導者に従い、自分の思想を持つものは危険分子として抹殺される。「お前はどうか?」と問われれば、体制に刃向かう勇気など私には無い。間違いなく付和雷同組の一人であろう。
第二次世界大戦が終わって早や70年余。原爆や敗戦の記憶は拭い去られ、憲法改正を声高に叫ぶ政治屋が現れた。そして彼の意向を「忖度」する役人共が、争って先棒担ぎをする。まるで戦前・戦中の軍部と内務省の再現ではないか!
麻生某が「ナチスに学べ」と言い放ったのはまことに適切である。
この文章を綴っている間に子供時代の悪夢が蘇った。戦後間もない小学校の教室で同級生と口喧嘩をしていたら、突然周りの一人が立ち上がり、私を指差して「こいつは友達を侮辱した。査問委員会に掛けろ!」と金切り声を上げた。初めて聞く言葉で、意味も知らなかったが、その言葉の持つ禍々しさにゾッとした。恐らくその子の家庭は、当時流行の左翼思想にかぶれ、日常そのような言葉が飛び交っていたのだろう。
それにしてもジョージ・オーウェルの洞察力の何と鋭いことか! 著者に内心の卑怯な部分を指摘されたようで、少々気が重くなった。
(狸吉 2017年9月13日)
このところ、言葉や話し方に関係したことを書くことが多い。最近とみに日本人の言葉や話し方の乱れが気になるからだ。特に若い人がそうだ―などと気になりだしたのは、後期高齢者になったことと無縁ではない、と思っていたのだが、それだけではなさそうだ。日本の社会全体の言語レベルが“劣化”しつつあるのではないかと思わせる調査結果が出た。
先ごろ発表された、文化庁による「国語に関する世論調査」の結果だ。それによると、ちかごろの日本人は、議論を避ける人が増えているという。意見が異なる場合も「事を荒立てたくない」と考えて議論を避ける人の割合が6割を超え、友人や同僚との間でも「人間関係優先」で、「空気を読む」傾向が強まり、自分の意見を主張しない人が増えているという。
いきなり年寄りの思い出話だが、われわれ後期高齢者の若かったサラリーマン時代はよく飲んだ。議論もしたし喧嘩もした。酔えば会社のこと、上司のこと、政治や経済やで勝手なネツを吹いたものだ。私の場合は、いまだにその傾向を引きずっている。
それにしてもわれわれの若い頃、昭和30~50年代までは、今のサラリーマンや組織人には考えられないほど自由な物言いができた時代だった。そうしてやりあった言葉の応酬、人の言葉で傷ついたこと、傷つけたこと、教わったこと、教えた(ハズの)こと、その数々が脳裏の奥底に貯め込まれている。言葉の応酬は人生そのものだ。それを文化庁の調査結果のように、空気を読んで自分の意見を主張しないというのでは、生きる意味も生きた証しも残らないことになりはしないか。高齢者は、その、言葉にまぶされて熟成された思い出を、奥底のフタを開けて取り出し、なつかしくしゃぶるのだ。
そんな回顧談ですまない昨今の問題は、文化庁の調査結果と逆に、匿名性の強いネット社会の広がりの中で、鋭く他人を誹謗中傷する傾向も強まっていることだ。マスコミ界、とりわけテレビなどでは無責任な極論をはく論者や芸能人などの“露出度”が高まっている。なぜこの両極端の分離現象が起きているのだろうか。
この強気の側の“跳ね返り現象”を、文化庁調査が示す、圧倒的に多い弱気の側の日本人の、抑圧された不満を代弁する“作用”と見るか、日本人の言語意識の二極化ないし二層化と見るべきか、いずれにしても喜べない傾向、憂慮すべき言語意識の“劣化”傾向ではないか。言うべき意見をまっすぐ言えないということはこれからの日本にとって大問題ではないか。
先のエッセイ「やたらにうるさい喋り方」で、評論家・加瀬英明氏の言葉を引用した。『中国語では、かならず「私」がそう思う。「私」がそう考える、と言います。(中略)日本では「私」と言うと、押しつけがましくなるから、自己主張をできるだけ抑えて、「私」という言葉を、なるべく省くようにする。「私」を前面に押し出すと、卑しくなるからです』という言葉だ。「明治維新から見た日本の軌跡、中韓の悲劇」(加瀬英明、石平共著、ビジネス社)。
この言葉を、ほこるべき日本人の美徳として引用したのだが、北朝鮮問題をはじめ現下のただならぬ緊迫した国際情勢のもとでは、加瀬氏には申し訳ないが日本人の美徳の“か弱さ”を思わずにはいられない。
個々の日本人が、節度をもって正当に意見を言うべきであり、それは国際人の加瀬氏にとっても言わずもがなの話であり、それをやらなくなっては、先のエッセイ「“新衆愚政治”の時代?」の到来を招いて、昨今の英米のように、国民が「風向き」に流されるようなことになりかねない。
やたらにうるさい喋り方
いい話から始めると、最近、テレビを漫然と見ていたら、“学校放送コンクール”のような番組があり、女子高生らしき若者が落ち着いた音声と音程で、プロのアナウンサーのように、実に心地よい“語り”をしているのを耳にした。それでまた思ったのだが、近ごろ、テレビのプロであるはずのアナウンサーやナレーターなどが、キーが高くて聞き苦しい発声をする人が増えてきたように思う。とりわけ女性のほうにそれが多く、中学生や高校生のような生硬で高いキーで喋るプロ?が増えてきた。
民放はだいぶ以前からそうだが、近ごろはNHKも民放と同様になってきた。そういうアナウンスに接すると私は、「いい女はそんな声を出さないよ」とか、ひどい場合は「ガキ声を出すな」などとテレビに向かって“悪タレ”を言いながらチャンネルを切り替えることが多い。
この高いキーとともに大声も増えてきた。特にテレビに出てくる有名無名の人から芸能人まで、高いキーと大声で喋りまくる。どうしても聞きたい、見たいと思った座談会などの番組でも、一方的に喋る、人の話の腰を折って喋る、自説を曲げない高いキー・大声などで幻滅させられることが少なくない。特に女性の“識者”にその手合いが多く、私にとってはアノ先生とアノ女史が出たらチャンネルを切る、という数人の有名人もいる。
そんな折りに、渋谷の大型書店で面白い本を見つけた。題名がズバリ「中国人がいつも大声で喋るのはなんでなのか?」という本である。私の友人たちの間でも、中国人の大声がよく話題に出る。なんで中国人は、辺りかまわず大声で喋るのかなー、というわけだ。
この本は、日中間の親近感を高めるための、中国の学生たちによる「日本語作文コンクール受賞作品集」である(2013年、日本信報刊)。61編が収まっているが、なんとそのなかの17編が、中国人自身の「大声」について書いている。どうやら「日本」を体験した中国の若者たち、気の付く若者たちは、日本人に比べて自分たち中国人が常に大声で喋っているという事実に気づくらしい。
17編の作品にはふんだんに実例が出てくる。たとえば中国のバスの中で、バスが停車せずにバス停を行き過ぎたことで、乗客のおばあさんと運転手がバスを止めて大声で延々と罵り合う。しかしこれは中国では当たり前の光景だ、などといった例である。この本を読む限りでは、総じて自分たちの「大声」を反省し、日本的・社会的なマナーを学ぼうとする中国の謙虚な若者が増えているようだ。
バスの話を書いたのは若い女子学生だが、こんなことも書いている。すなわち、日本人は「私」をあまり強く主張しないが、中国人は「我」を強く主張すると言い、自己主張が強く、自分の利益や立場を主張し、それを相手に認めさせようと根気よく主張するなどと、民族的な特性を語っている。
この後、これも偶然たまたま読んだ本が「明治維新から見た日本の軌跡、中韓の悲劇」(加瀬英明、石平共著、ビジネス社)という対談集である。その中で加瀬氏がこんな話をしている。『中国語では、かならず「私」がそう思う。「私」がそう考える、と言います。(中略)日本では「私」と言うと、押しつけがましくなるから、自己主張をできるだけ抑えて、「私」という言葉を、なるべく省くようにする。「私」を前面に押し出すと、卑しくなるからです』と言っている。
話を戻すと、冒頭に言ったように、近ごろ日本人の喋り方もやたらにうるさい。中国人の心ある若者たちの範となる日本人のマナーを失いたくないものだ。
(山勘 2017年9月25日)
北のボンボンが、やたらにICBMもどきのミサイルを打ち上げる。だんだんと手の付けられない無法者になってきたようだ。北が図に乗って米国の鼻先までICBMを打ち込めば、おそらくトランプの米国はB1爆撃機などで反撃に出るだろう。
米国と北朝鮮の対立を喧嘩勝負と言っては語弊があろうが、心理的なやり取りでは喧嘩勝負に通じるものがある。喧嘩には大小あり、個人的な口喧嘩から国と国の喧嘩、すなわち戦争まである。ところがこの喧嘩、大小にかかわらず勝負の決め手はどうやら“気合い”らしい。
喧嘩勝負に勝つための「ゲーム理論」に、「マッドマン・セオリー」というのがあるという。「米中もし戦わば」(文藝春秋刊)に教わった。その事例を後で紹介するが、たしかに、喧嘩勝負は気迫で相手を呑むか逆に呑まれるか、一瞬の“気合い”で決まる、といったところがある。
これは何十年か前にテレビで見た、高名な2人の作家が対談した時の話である。名前は伏せておくが、論議が紛糾して激高した一方が、「信義のためなら(と言ったか)、その窓から飛び降りられるか」と迫ったところ、一方が目をぱちくりさせて答えに窮した場面があった。おもわず笑ってしまったが、これが斬り合いなら一瞬にして「勝負あった」とも感じられた。
これは最近、何かの週刊誌で読んだ話だが、広域暴力団山口組から神戸山口組が分裂し、そこからまた分裂した3番目の何とか組の何とか組長の話である。その組長は韓国系(親の代から帰化している?日本人)だが、30代か40代の壮年で、分裂の経緯やヤクザ社会の掟や政治や人生論などを語っている。インタビュアーはヤクザ社会に強い溝口敦さんで、その組長の話がいちいち筋が通っていて実に小気味よく、人間的な魅力を感じさせる組長だ。
親父さんも極道だったらしいが、その親父さんに教わったひとつのエピソードが面白い。警察の取調室での対処法である。相手がヤクザ者とあれば、取り調べ方も荒くなり、殴る蹴るとまではいかないにしても“物理的作用”を用いる場面がけっこう出てくる。
そんな取り調べを受けたら、「半端なマネをやるんじゃネー」とか怒鳴り上げて、ドアや窓ガラスを頭で叩き割れと教えられたという。額を割って血だらけになれば取調官のほうが気を呑まれておとなしくなる。そうなればコッチのもんだ、という寸法だ。これも“気合い”である。
ここで本当に言いたかったのは、国同士の大喧嘩、すなわち戦争での“気合い”である。「米中もし戦わば」にある「マッドマン・セオリー」の例だが、ニクソン元米大統領が、泥沼のベトナム戦争を終結させるためのパリ和平会議でこの手を使ったという。
すなわち、ニクソンが、常軌を逸した怒りっぽい態度を装って北ベトナムに米側の条件を飲ませようという作戦だ。そのためにニクソンは側近を使って敵側に耳打ちするという事前工作をした。ニクソンは言った。彼らに口を滑らすだけでいい。「お願いだ。ニクソンが反共に凝り固まってることは知っているだろう。彼は怒り出すと手がつけられない。彼なら核ボタンを押しかねない」とな-。それだけでホーチミン自身がパリに飛んできて和平を申し出るだろう、と。結果はまさにその通りとなった。
同書に、戦争を回避するには、「米国とその同盟国には、必要とあらば通常戦争を戦う覚悟も、やむを得ない場合は核兵器の使用も辞さない覚悟もある」と敵に信じさせなければならない、とある。確かにそうだろう。その意味で「マッドマン・セオリー」は大いにトランプ大統領向きだと思われるのだが、その“気合い”を入れた脅しに、北のボンボンがビビるかどうかは疑問である。
(山勘 2017年9月25日)
書きたいのは朝日新聞の社説についての“雑感”だが、その前に、「日中もし戦わば」(マイケル・グリーン、張宇燕、春原剛、富阪聡共著 文藝春秋刊)を“まくら”に使いたい。この本のまとめの部分で、本書を主導したジャーナリスト・富阪聡氏(社会学者とでも呼ぶべき識者)がこう言っている。
「国防上、相手よりも大きな力を有することは理想だが、本来、相手に攻撃の気持ちを起こさせない程度の備えがあれば、必要以上に国民が不安に感じることはないはずだ」と。まさにその通りであろう。さらに「中国人民軍の不透明さは、信頼を醸成して均衡を図り、ウイン・ウインになることを妨げている」と現実を指摘する。そこまでは頷ける。しかし続いて、「そこに(軍拡競争に)力を注ぎ疲弊するよりも、中国を説得してウイン・ウインの道を模索する方がすっと建設的であり、また現実的だ」となると素直に頷くわけにはいかなくなる。それは自己矛盾である。中国人民軍が不透明で、中国を説得することが困難で、建設的でも現実的でもない。それが現実であり対中戦略の前提ではないか。
これとよく似た論理を展開するのが朝日新聞(8月19日)の社説だ。それは、日米双方の外務・防衛担当の閣僚会合(8月17日)について、「日米2+2 外交の姿が見えない」と指摘したもの。冒頭では「ミサイル発射を繰り返す北朝鮮に対し、日米の結束を示すことが抑止効果を持ちうることは理解できる」と、日米安保への“理解”を示したうえで、朝日らしい“懸念”を陳開する。
最初に、会談の内容が「自衛隊の役割強化に傾斜」し過ぎていると言い、次いで日本側が「次々と手形を切った」と言う。すなわち「防衛大綱の改定」、陸上配備型の「イージス・アショアの導入」、そして「情報収集・偵察・訓練の探求」である。代わりに日本側は、「核の傘」と「日米安保条約の尖閣諸島への適用」の再確認をしただけと言う。つまり今回の会談内容は“片務的”だというわけだ。
そして、グアムが北のミサイル攻撃を受けた場合、集団的自衛権を行使できる「存立危機事態」にあたりうると小野寺防衛相は発言した(8月10日)が、マティス米国務長官は今月、「戦争の悲劇は壊滅的になる」と述べ、「北朝鮮との軍事衝突が招く危険性を指摘した」と言う。つまり、米の“慎重さ”に対比させて日本の“勇み足”を問題にしたいらしい。
で、この朝日社説の結論は、いま日本は、「米朝間の緊張をやわらげ、北朝鮮の核実験とミサイル発射の「凍結」に向けて対話局面への転換をはかる努力が求められている」と結ぶ。この論理、「日米安保」への理解から「外交重視」に持っていくところは、富阪氏の論理展開によく似ている。
朝日に言われるまでもなく関係国はいま「対話局面への転換」努力を続けている。朝日が「巻き込む外交を」しろと言う中国やロシアへの働き掛けもしているわけだが、彼らの“本気度”に不安があり、なによりも北朝鮮の不透明さは、富阪氏が指摘する中国共産軍の不透明さの比ではない。
その北朝鮮を、核保有を認めるなどという危険な大幅譲歩をすることなく説得する難しさは素人でもわかる。ついでに挙げれば、近刊「米中もし戦わば」(ピーター・ナヴァロ著 赤根洋子訳 文芸春秋)では、多くの専門家の見解を検証し、400頁を費やした冷静な分析の結果、問題の解決は「力による平和」以外にないと結論づけている。
(山勘 2017年9月25日)
だれでも知っている「孫子の兵法」は、子供とは無縁の“戦略・謀略”だと思うが、売れっ子ライター斎藤孝明大教授の「こども孫子の兵法」(日本図書センター刊)が売れているという。その内容は、たとえば「まず相手のことより自分のこと。負けないための準備をしっかりしよう」と教える。孫子の教えるあの有名な「彼を知り己を知れば百戦して危うからず」である。
孫子の兵法に対して、こちらはあまり知られてはいないが、日本古来の兵法書と言われる「闘戦経」がある。「孫子」の方は、「兵(戦い)は詭道(きどう=いつわる、あざむく)なり」と教える。戦いに勝つためには何でもありの権謀術数「詭譎(きけつ=だます、あざむく)」を駆使しろと教える。これに対して闘戦経の基本理念は「真鋭」である。真鋭とは、真心の力を持つ正攻法の鋭さである。
そんな孫子の兵法を、喧嘩をしてはいけませんと親に教えられ、運動会の危ない種目は廃止されるような“安全第一”の環境で、戦うことを知らずに育つ現代の子供たちに教える意味があるのだろうか。子供社会の良き観察者であり教育者である斎藤教授だけに執筆の意図が理解できかねる。
10年以上も前の小さな話だが、忘れられない記憶がある。親戚筋の集まりで従兄と「戦略・戦術」の話になり、私は、知人の大学教授の「闘戦経」に関する研究論文など読まされていたので、闘戦経の話を出したのだが、従兄が「何だそれは」と聞き返したところで、その場にいたこれも親戚の若いお母さんが、傍らの中学生だったか小学生だったかの息子に「調べてやって」と言った。息子は「うん」と答えて電子辞書(のようなもの)を取り出した。そんな耳慣れない「用語」が出ているものかと思っていたら、息子はたちまち闘戦経を検索して得意そうに意味も分からない(であろう)内容を読み上げた。母親も満足そうに微笑んでいる。何かがおかしい、何かが間違っていると感じたものだ。
最近出た本に「クラウド時代の思考術」(ウィリアム・パウンドストーン著 森夏樹訳 青土社)がある。本書に関する新聞の書評で、東大教授・佐倉統氏は、・グーグルが教えてくれなかったこと、それは、・適切な「検索」には、知識・能力が必要だということ、・ネット社会の発達でダニング=クルーガー効果=能力の低い人ほど自分を過大評価するという現象が生じていること、・だれでもたくさん情報を集めて勉強したような気になること、・偏向した自分の意見を補強する材料を手に入れるだけになる恐れ、・逆に科学的知識の豊富な人ほど自分の政治的イデオロギーに適して解釈を下す傾向、・新聞やテレビなどプロの編集によるマスメディアの重要性を強調していること、などのポイントを指摘している。(佐倉教授の説明に少し余計な字句を加えていることをお許し願いたい)。ネットで仕入れた情報で理屈をこねる頭でっかちの子供(や大人)が増える現代の風潮を突いて痛快だ。
われわれ後期高齢者は、戦中戦後の混乱の中で子供時代を過ごした。しかし今思えば夢のような時代だった。腹を空かしながらも外に飛び出していろいろな遊びに夢中になっていた。喧嘩もした。その遊びの場が子供なりの人間関係の習得と体力養成の場だったと思う。
さらに、江戸時代の商家などでは、子弟の養育方針として「三つ心、六つ躾、九つ言葉、十二文(ふみ)、十五理(ことわり)」という教えがあったという。年齢と共に習得すべき徳目の順番だ。ところが現代は、幼いころに身に着けるべき「心」も「躾」も「言葉」さえも教え込まれず、早くから「文」と「理(ことわり)」をテスト用の知識として詰め込まれているように見える。それをネット社会が加速する。なにか日本人として大事なものを時代の隅に置き忘れてきたような気がしてならない。
(山勘 2017年9月25日)
8月某日、NHKテレビで、「オイコノミアお笑い総選挙」という番組を見た。3組のお笑いコンビが芸を披露し、どの組が一番面白かったかを競うゲームだ。番組の目的はまじめなもので、いろいろな方式があるという「多数決」の“実験”だ。ゲームを主導するのは、著書「多数決を疑う」を持つ坂井豊貴慶大教授で、教え子の慶大生10数人が“お笑い芸”のデキを投票で判定するのである。
ゲームの結果、普通の「多数決」による判定では、A組が1位になった。ところが「決選投票付き多数決」(上位2組で決選投票をする方式。政党の党首選などでよくやるアレである)では、B組が1位になった。それはB組が3位票を大幅に取り込んだ結果である。さらに「ボルダルール」(1位に3点、2位に2点、3位に1点とウエイトづけをする集計方式)では、C組が1位になった。それは、2位・2点と評価された得点の総計が他より多かったためである。要するに、多数決の方法を替えれば、3組のお笑いコンビそれぞれに優勝のチャンスが巡ってくるというわけだ。
こうなると、民主主義の同義語とさえ言える「多数決」の信頼性が極めて怪しくなってくる。中でも「単純な多数決」はよく使われる物事の決め方ではあるが、この多数決による決定も、しばしばおかしな結論を出すことがあるということは、誰でも知っている。とはいえ、民主主義の政治体制のもとで、国民が政策を選択する手段は、最終的には多数決以外にないだろう。
この多数決方式の政治で、最初に失敗したのが民主主義発祥の地、古代ギリシアの都市国家アテネだった。政治に疎く知識に欠ける市民層まで政策決定に直接参加させて、最後は政治がメチャクチャになった。アテネの例は、いま世界的に問われている「衆愚政治」の先駆けだったと言える。
“愚かな大衆による政治”とは嫌な言葉だが、ギリシア以来、歴史的に改良・工夫を重ねてきた現代の民主主義社会において、いま指摘されている問題が、その「衆愚政治」であるというのは皮肉だ。それには、現代社会の、選択と判断に迷うほどの大量情報や誤った情報の流通、意図的な情報操作、そして複雑・多様な利益誘導などによって、個人や集団の判断が“誤作動”を起こし、結果的に、政治や政策判断において“衆愚性”を露呈する危険性が格段に高まっているという背景がある。
その現代における“衆愚性”発揮の代表的な例が、誤解を恐れずに言えば英国のEU離脱であり、米国のトランプ大統領誕生である。両国における「多数決」の方式は違うが、両国民が大いに疑問のある結果を選択してしまったことは確かである。
英仏の例に匹敵するわが国の大問題はこれから迎える憲法改正だろう。安倍政権の取り組みがどうなるか予断を許さないが、やるとなれば、最終的に国民投票によって合意の形成を迫られることになる。“愚民性”を露呈することのない国民の判断が必要になる。
そのために危惧されるのは、国民の知性だけでなく政治家の資質だ。国会議員による低レベルの“滑稽談”が続発する現状は情けない。国として正しい合意形成を行うためには、国民の知識・常識・判断力の向上の前に、政治家の資質・政策・リーダーシップが問われよう。「国民の声」を低姿勢で聞き、「国民の目線」にすり寄るだけの低レベルで無能な政治家が増えている現状は問題だ。
(山勘 2017年9月25日)