2017年7月26日(水)午後3時~午後5時(会場:三鷹SOHOパイロットオフィス会議室、参加者:狸吉、致智望、山勘、恵比寿っさん、ジョンレノ・ホツマ、本屋学問)
梅雨明け宣言してからのほうが雨模様の天気ですが、例会は全員参加が続き、意気込みも盛んで、大変喜ばしいことです。書感7本、ネットエッセイ3本と、制限時間一杯を使って今回も談論風発でした。アベノミクス失敗と政治家の失態は、毎回やり玉に上げられています。「天然ゴム」「ウイルス」「トランプドル」「たたら」と、やや趣の異なるテーマも紹介され、話は尽きませんでした。
例会後は、女性陣も交えて恒例の暑気払いでした。いつもながら美味しい料理と天下の美酒で、心行くまで音楽を、美術を、酒を、そして人生を語りました。また忘年会をお楽しみに。
(今月の書感)
「『あの国』はなぜ、日本が好きなのか─歴史秘話…そして彼らは『親日国』になった!」(本屋学問)/「アメリカに食い潰される日本経済」(致智望)/「天然ゴムの歴史─ヘベア樹の世界一周オデッセイから『交通化社会』へ」(狸吉)/「生物はウイルスが進化させた─巨大ウイルスが語る新たな生命像」(恵比寿っさん)/「人はどのように鉄を作ってきたか」(ジョンレノ・ホツマ)/「日本列島創生論─地方は国家の希望なり」(山勘 2017年7月24日)「トランプドルの衝撃」(ジョンレノ・ホツマ)
(今月のネットエッセイ)
「民度」(本屋学問)/「小池知事は都民の信頼を保てるか」(山勘)/「人生おさらばの一言」(山勘)
 本書に登場する国は実に63か国、紹介文に「意外な絆で結ばれていた世界と日本、日本人も知らない歴史秘話…」とあり、やや牽強付会的な絆もないわけではないが、よくもこれだけ日本とかかわりのある国の逸話を集めたものだと感心する。
本書に登場する国は実に63か国、紹介文に「意外な絆で結ばれていた世界と日本、日本人も知らない歴史秘話…」とあり、やや牽強付会的な絆もないわけではないが、よくもこれだけ日本とかかわりのある国の逸話を集めたものだと感心する。
同じように植民地支配を受けたのに、韓国と違って国民の大多数が親日だという台湾は、近代化とは無縁だったこの島に鉄道や道路、上下水道をつくり、産業を発展させた日本の貢献が大きい。それと同時に、統治以前の台湾と韓国が歩んできた歴史がそれぞれに異なるという実情も知る必要がある。
イスラエルには、“命のビザ”で有名な外交官杉原千畝の勇気を称えた「スギハラ通り」があるが、ヨーロッパからソ連経由で逃れてきた多数のユダヤ難民を、南満州鉄道を使ってハルビンまで無償で輸送した特務機関長、樋口季一郎将軍の名も忘れてはならない。「ヒグチルート」と呼ばれたこの“命の道”も、戦後ユダヤ人団体の働きかけで彼を戦犯から救った。
ポーランドは日露戦争の日本の勝利でロシアの圧政から解放され、ロシア軍に召集されていた数千人の兵士は日本が手厚く保護、無事帰還させた。第1次世界大戦当時、戦場となった祖国からシベリアに脱出した20万人ものポーランド人に救いの手を差し伸べたのも日本だった。ウラジオストク在住ポーランド人は孤児救済委員会を立ち上げ、アメリカ始め列強に支援を求めるが拒否され、日本だけが約800人の孤児を迎え入れたという。
同じく日露戦争後、日本は武器の供与や経済援助でフィンランドのロシアからの独立を支援し、フィンランドとスウェーデンとの領土問題を平和的に“大岡裁き”したのが、発足したばかりの国際連盟の事務次長、新渡戸稲造だった。
アルゼンチンとの関係も日露戦争と縁がある。開戦前に艦艇が不足したとき、アルゼンチンが発注していた2隻の軍艦を日本が譲り受け、結果的に日本海海戦に勝利する。さらにアルゼンチンは第2次世界大戦で対日参戦を拒み続け、戦後は大量の救援物資を送ってくれたという。
世界有数の原油大国イランは長くイギリスに搾取され、1951年に石油施設の国有化を宣言する。激怒したイギリスはペルシャ湾に艦隊を派遣して海上封鎖し、国際石油資本(メジャー)とともにイランを国際石油市場から締め出した。そのとき、果敢にもイラン原油買付けに動いたのが日本の出光興産である。社長の出光佐三は、国際問題に発展する危険も熟慮したうえでイランの窮地を救った。その後、1979年にイラン革命が起こったときも、日本はアメリカに追随せずイランから原油を買い続けた。イランにとって日本はまさに救世主となった。
セルビア(旧ユーゴスラビア)と日本は明治時代から友好関係にあり、戦後も東欧諸国のなかでは最も早く国交回復した。その意外な理由が、蚊取り線香の原料である除虫菊である。原産地はセルビアで、元々日本には存在しない。「金鳥」の創業者、上山栄一郎はこの除虫菊から殺虫液を開発し、セルビア産除虫菊の生産量を伸ばして友好関係をさらに発展させた。彼は後に同国から大阪駐在名誉領事の称号を授与されている。
350年にわたるオランダの支配からインドネシアを解放し、戦後再び植民地化を目指したオランダに対する独立戦争に従軍した旧日本兵は約2000名、うち1000名が戦死した。彼らは国立英雄墓地に手厚く葬られ、「世界一好きな国は」という問いにインドネシア人は今も70%が「日本」と答えるそうである。
親日国は多いが、その筆頭は何といってもトルコだ。1890年に親善来日したトルコの軍艦が帰路の熊野灘で台風に遭い、和歌山県串本町沖で沈没した。乗員656名は絶望かと思われたが、地元民の必死の努力で69名が救助され、犠牲者を埋葬し、生存者と遺品は日本の軍艦で送り返した。この話は「エルトゥールル号事件」としてトルコの教科書に載っているが、さらに感動的なエピソードがある。
1985年にイラン・イラク戦争が勃発、当時のイラクのフセイン大統領は「イラン上空を飛ぶすべての航空機を撃墜する」と宣言した。攻撃までの猶予は48時間、各国は自国民保護に奔走するが、日本は航空機を確保できず(日本航空労働組合は危険を理由に要請を拒否、自衛隊機派遣は社会党が反対したとか)、イラン在住の日本人215人が取り残された。このとき、危険を顧みず救援機2機をテヘランに飛ばし、時間切れ寸前で日本人を救出してくれたのがトルコだった。2013年、日本はトルコが150年間実現できなかったボスポラス海峡横断トンネルの難事業を9年かけて完成させ、その恩に報いた。
阪神淡路大震災や東日本大震災など日本が大きな自然災害に見舞われるたびに、世界各国が温かい支援の手を差し伸べてくれた。しかし、その厚意は現在の日本国や日本人に対してというより、かつて日本人が行なってきた博愛精神に基づく崇高で毅然とした行為に対する返礼ともいえる。まさに“情は人のためならず”、大国のご機嫌ばかり伺い、低次元の国益や効率だけを求めがちな今の日本は、真底肝に銘じるべきである。
最後に、本書に使われている「送り仮名」について。1973年に内閣が「行なう」を「行う」表記に制定して「な」を送らなくなり、現在は公文書も教科書もマスコミもこれが主流である。もちろん、どちらも正しいが、「行った」(おこなった)を「いった」と誤読しやすいので、私は必ず「な」を送るようにしている。本書も執筆陣の年齢からか別の理由からか「行なう」と表記していて、久しぶりに気心の知れた友人に会ったようなホッとした気分になった。
(本屋学問 2017年7月14日)
アメリカに食い潰される日本経済/副島隆彦(徳間書店 本体1600円)
 本書は、米国大統領にトランプが就任した後、シリア空爆が行われて間もなくの頃に発売された書である。著者の福島隆彦については、既に拙い書感に何度か執筆しているので省略する。
本書は、米国大統領にトランプが就任した後、シリア空爆が行われて間もなくの頃に発売された書である。著者の福島隆彦については、既に拙い書感に何度か執筆しているので省略する。
ドナルド・トランプと言う男は、多くの日本人から金髪ゴリラの恐ろしいおじさんのイメージが強い。こんな男が何故大統領に、と思うと強く動揺が走るが、なるべくしてなったと言うのが著者の意見である。クリントンと比較してみてもクリントン程に恐ろしい魔女のような女と言うのが米国で通説と言うからどっちもどっちで、トランプは品が無いが今の米国の状況から考えると妥当と考えると言うのが著者の意見。
米国の財政赤字が55兆円/年、貿易赤字が90兆円/年、国防費については70兆円/年に対し10%増額すると言う。それが、再建屋トランプの出現である、国防費の増額など何処からカネを出すのか、この辺りの発言がトランプならではのインチキ含みである。この財政赤字金額は、年度毎に発表されるが、今の債務累計額はと言うと、その額は発表されておらず、年度ごとの集計結果でしかない。
集計した数字もボロボロであるが、実態は公表されていない項目が有って、真実はそれほど甘くないはず。だからその政策は、国内問題優先で財政立て直し一本槍、外国のことなど関わりたくないのが本音丸出し。しかし言っている政策は、実現不可能な矛盾だらけだから、環境保護を重視しないなどの本音がでてくる。
こんな酷い財政状況でもやって行けるのは、ドルが基軸通貨であり不足分は印刷出来るからで、財政の実態はどうにもならない状況に至っていると言うのが著者の弁である。
トランプ政権のムニューシン財務長官と言うのは「チョップショップ」の経済運営思想で動いている人である。チョップショップと言うのは、自動車泥棒が盗難高級車を切り分けて利益を出すことから発生した言葉で、トランプ政権とはこのチョップショップのどぎたない大物経営者の談合による景気回復を目指した、経済復興だと著者は言う。このムニューシンの所業に付いて、本書には詳しく述べられているが割愛する。
この悪賢い手法を用いて経済を脱却するしか方法が無いのがトランプの考えてであり、そこまで米国経済は追い込まれていると言える。
このトランプを陰で守っているのがキッシンジャーであり、死去(17年3月)したロックフェラーだったと言うのも以外な思いだ、我々は心しておくべき重要事項かも知れない。
トランプは、ヘリマネ(ヘリコプターマネー)はインチキ理論と言い続けている、FRBのイエレンはヘリマネ派出身の学者である。これから、米国の経済政策はどの方向へ行くのか、本書に結論は述べられていない。
日本は、すでに1000兆円の米国債を買わされ、カルフォルニア100年債を買わされている。すでに米国金融属国となり、これからも金融奴隷を続けて行く気でいるようだ。
この他、米国に利用されそうな恐ろしい話が述べられている。著者は、「年間2000億程度の少額利益だが」とのコメントをつけているがその内容が恐ろしい。イバンカと夫のクシュナーは、アメリカ・ユダヤ人の王朝を築こうとしているという。
ラスベガスの大手カジノを経営するアデルソンとクシュナーが組んでいるという。ラスベガスでは、このアデルソンとウインズ・グループが熾烈な競争をしていて、そのウインズは、日本の中央競馬会の場外馬券売り場は、既にウインズの下請けとなり、看板にはウインズ(WINS)と記されているという。
アデルソン、クシュナーのカジノグループは、遅れをとって焦っている、日本全国に10カ所ぐらいカジノを解禁するだろうといわれている。この様な、トランプを取り巻く、底知れないどぎたない、泥臭い、人間の欲望の法則に合致した、金儲けの能力ある実業家たちのことを書いておかないと綺麗ごとでは済まない世界を知らないままに済んでしまう日本人、これが著者の言う「アメリカに食いつぶされる日本経済」と言いたいように私は思いつつ本書感を記した。
そして、トランプはアメリカの鉄鋼が中国に勝てないことは承知している、石炭がまともな理屈で再生出来ないことも承知している、それを敢えて言っているところにこの男の底知れぬ恐ろしさを読まなければ、と言うことのようだ。
(致知望 2017年7月16日)
天然ゴムの歴史─ヘベア樹の世界一周オデッセイから「交通化社会」へ/こうじや信三(京都大学出版会 2013年 本体2,200円)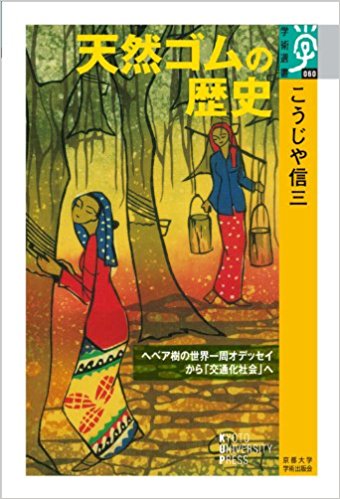
文房具の消しゴム、日用品の輪ゴムやパッキン、車のタイヤ。ゴム製品は今日の生活に無くてはならない。ところで、このゴムの発見から今日の普及まで、壮大な歴史ドラマが存在していることをご存知だろうか?本書はゴムを主体とした高分子化学の専門家であり、かつ外国語に堪能な著者が、多くの文献を読み解き、コンパクトな文庫版に纏め上げたものである。
ウイッカムは目的達成のためには艱難を厭わぬ生来の探険家であったが、行き当たりばったりな性格が災いし、何度も無一文の苦境に追い込まれた。しかし、80歳を超えるまで長生きし、晩年はSirの称号を得て、名誉の上でも経済的にも恵まれたのはもって瞑すべきであろう。このウイッカムの生涯に関する章は、読み進むにつれウイッカムと共にジャングルに分け入り、予想外の不運に見舞われ、思いがけぬ幸運に救われと、手に汗握る気分になる。
(狸吉 2017年7月17日)
生物はウイルスが進化させた─巨大ウイルスが語る新たな生命像/武村政春(講談社ブルーバックス 2017年4月20日第一刷発行 本体980円)

1969年三重県津市生まれ。1998年名古屋大学大学院医学研究科修了。医学博士
名古屋大学助手などを経て、現在、東京理科大学理学部第一部教授。
専門は、巨大ウイルス学、生物教育学、分子生物学、細胞進化学。
著書に『DNA複製の謎に迫る』、『生命のセントラルドグマ』、『タンパク質入門』、『新しいウイルス入門』
『巨大ウイルスと第4のドメイン』(いずれも講談社ブルーバックス)のほか『レプリカ~文化と進化の複製博物館』(工作舎)、『DNAの複製と変容』(新思索社)、『ベーシック生物学』(裳華房)、『マンガでわかる生化学』(オーム社)など多数。趣味は書物の蒐集、読書、ピアノ、落語、妖怪など。
(画像はAmazonから借用しました)
はじめに 巨大ウイルスが問いかける「謎」
第1章 巨大ウイルスのファミリーヒストリー 彼らはどこから来たのか
第2章 巨大ウイルスが作る「根城」 彼らは細胞の中で何をしているのか
第3章 不完全なウイルスたち 生物から遠ざかるのか、近づくのか
第4章 ゆらぐ生命観 ウイルスが私たちを生み出し、進化させてきた!?
おわりに さくいん・参考文献
蛇足だが細菌(生物1~5㎛)とウイルスは全く違う。ウイルスは生物ではない(自分自身で増殖する能力が無く、生きた細胞の中でしか増殖できないので、他の生物を宿主にして自己を複製することでのみ増殖)。
面白いが難しい。読んでも覚えられない。
著者は、これまでのウイルスに対する人びとのイメージを百八十度覆そうという試みであり、挑戦的なことだと述べているのだが、どこがどうなのか私には理解できずに終わった。そして、そのバックグラウンドになっているのはフランスの微生物学者パトリック・フォルテール博士だという。
「ウイルスによる細胞核形成説」(著者の主張、2001年:真核生物の細胞核がウイルスによってもたらされたとしている)を支持してくれているからだという。
この時点での著者の論文はポックスウイルスそのものが細胞核へと変貌したが如く書かれていたというが、未だ学説として定着したわけではなさそう。
私としては、もう少し解明が進んだものと期待していただけに少々残念。
細胞性生物は①細胞からできていること②自己複製すること③自分で代謝活動を行うが、ウイルスは②だけは該当するが①と③の特性は持っていない。ウイルスの基本形はカプシド(タンパク質の一種)で出来た殻が遺伝子の本体である核酸(DNA:遺伝情報の継承と発現を担う高分子生体物質またはRNA:DNAの情報から生命体を作る役割を持つ)を包み込んだものである(一般には正20面体)。
①電子顕微鏡でなければ見えず、ゲノム(生物の遺伝情報の全体)サイズは生物よりも小さい。
②DNAはRNAから進化したが、そのメカニズムは不明。
③ウイルスの本体はウイルス粒子であり、細胞性生物の力を借りて増殖する。
④細胞性生物にとって、ウイルスは進化に重要な役割を果たしてきたパートナーである。
ところが
①巨大ウイルスは光学顕微鏡でも見え、ゲノムサイズが一部の生物よりも大きなものがある。
②ウイルスの本体はヴァイロセル(ウイルス粒子に感染した細胞)である。ウイルス粒子は、ヴァイロセルが増殖するための生殖細胞に過ぎない。
③細胞性生物は、ウイルスの一部から生じた。というのが著者の主張の一部である。
人はどのように鉄を作ってきたか/永田和宏(講談社ブルーバックス+α 2017年5月発行 本体1,000円)
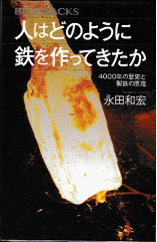 著者は現在、東京工業大学名誉教授、鉄冶金学の研究から「たたら製鉄」および古代製鉄の技術を研究し、「永田式たたら」を考案、「たたらを現在に」を掲げ、電子レンジ製鉄を発明。
著者は現在、東京工業大学名誉教授、鉄冶金学の研究から「たたら製鉄」および古代製鉄の技術を研究し、「永田式たたら」を考案、「たたらを現在に」を掲げ、電子レンジ製鉄を発明。
「たたら製鉄」とは、微粉末の砂鉄を使った世界の製鉄史でもユニークな日本古来の製鉄方法である。
言い伝えに基づいて当時の状況を再現した実験がなされてきたことは知ってはいたが、あまりにも距離がありすぎて、身近なものとしては捉えていなかった。著者は小型たたら炉による実験と鍛冶体験を基にたたら製鉄法の製鉄と鍛冶の理論を解明した。
著者は、耐火レンガで炉を作り、島根県斐伊川の砂鉄20kgから6kgの鉧(けら・鋼塊)を作ることに成功。レンガの炉作りに1時間、加熱に1時間半、砂鉄挿入は20kgにつき2時間半、炉内の木炭燃焼に1時間、最後に鉧(けら・鋼塊)出しと合計6時間でたたら操業を行う方法を確立した。
炉下の羽口(炉に空気を吹き込む)で炉底を加熱後、上の羽口に切り替え、砂鉄を入れ始めてしばらくして廃棄物の「ノロ」を流し出した。約3時間後に炉を解体して中から真っ赤に加熱した鉧(けら)塊を取り出し、清流に投げ入れて冷却した。金槌で固まった「ノロ」を取り去ると中に銀色に輝く鋼塊が現れた。著者はこのとき、あまりにも簡単に鉄が出来ることに興味をもち、炉の高さと炉下部の加熱がポイントであることを理解したとあり、
現代版「たたら製鉄」ともいうべき、僅かな時間、スペースでの再現を成し遂げ、古代の「たたら製鉄」が三日三晩炉の火加減を見守っていた大変さを改めて認識しました。
今までに気になっていた「たたら製鉄」に関する言葉の解説など、全く別の次元からの説明に興味深い一冊となりました。
というのも、私は古代歴史書「ホツマツタヱ」の解読を楽しんでいる身ですが、「たたら製鉄」に関連する言葉が出てきます。しかし、前後の話と区切りなく延々と五七調の歌で綴られているので、詳細が掴み切れずにいました。
この「たたら製鉄」に関する用語が、「ホツマツタヱ」に出てきたり、語源となっていると思われるものを見つけました。
「たたら」 「ふいご」
あらかねのあは すゞなまり すがははきかね ししろかね うびにあかゝね はくろかね
それはぎはき きりはしろ ひのきはきあか くりはくろ
でるあらかねを 「たゝら」なし 「ふいご」にねれよ はにうくる(ホツマツタヱ15綾)
粗金の泡は錫や鉛、清い埴(は)が黄金、「し」(白い埴)は白金(銀)、「うび」(混沌とドロドロしている)が赤金(銅)、「は」(濁泥の埴)が黒金(鉄)。
それぞれの色は、萩(山吹)は黄色が金、桐の白が銀で、檜の黄赤が銅で、栗の黒色が鉄。
これらの粗金(精煉前)を「たたら」の「ふいご」で溶かすと、炉に鉱塊が生まれます。
こしき(炉)溶解炉
キュポラの前身(巨大蒸し器・セイロのようなもの)本書の参考図をみて、六甲山の麓にある甑岩(こしきいわ)神社にある巨大な岩(磐座群)を思い出し、「こしき」の意味を実感した。
ホツマツタヱ本文には「こしき」の言葉はないが、甑岩(越木岩)神社の御祭神として祀られている神々はホツマツタヱに登場する人物である。
ほど(火窪)ホド穴(羽口)・「ホド突き」(先の尖った細い鉄棒でホド穴を突いて常に掃除する。そして、「ノロ」が初めに流れ出るようにする。
「たたら製鉄」の詳細を実感として知らないと、「ホツマツタヱ」に記載された内容は、生々しい真実を隠すために、物語風に改められており、文字通り解釈したとき、おかしいと思いつつも、明らかに誤訳されて独り歩きしているようです。
女陰を「ほど」というのは子供を生みだす新しい生命の誕生する場所を示しています。これは「たたら製鉄」の「ほど」穴から新たな銑鉄が生じるイメージに重なっています。
以前、ランダムトークに「ももそ姫、御陰(みほど)を突きまかる」を投稿しましたが、モモソ姫が自分の御陰(みほど)を突いて自害されたという記述があります。これは、たたら製鉄で炉の底を掃除しているとき(ホド穴を突いているとき)に誤って粘土で固められていた外壁が破れ、炉内の真っ赤な鉄塊が飛び出し焼け死んだことを直接的な表現を避けたからだと思いました。
「ほどこし」(施す)
効果・影響を期待して、事を行う。装飾や加工を加える。
事態を改善するようなことを行う。ある事態に対し、何らかの手段をとる。行う。
種などを蒔 (ま) く。田畑に肥料や種をまく。
広くゆきわたらせる。
などの意味合いですが、「たたら製鉄」での「ほど」と「こしき」が「ほどこし」の語源になっているように思われます。
ノロ (溶融FeO)スラグ=鉱滓・製鉄工程で生成する廃棄物➡「呪う」の語源になっていると思います。
みやいかり みちなくわれを なぜのろふ(ホツマツタヱ25-21綾)
(ジョンレノ・ホツマ 2017年7月21日)
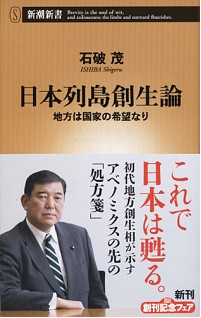 本書のオビに「これで日本は甦る。初代地方創生相が示すアベノミクスの先の『処方箋』」とある。題名は、著者が政治の師と仰ぐ田中角栄元首相の「日本列島改造論」にちなんだもの。
本書のオビに「これで日本は甦る。初代地方創生相が示すアベノミクスの先の『処方箋』」とある。題名は、著者が政治の師と仰ぐ田中角栄元首相の「日本列島改造論」にちなんだもの。
著者は、言わずと知れた大物代議士だが、防衛大臣などを歴任し、著書に「国防」「国難」「日本人のための『集団的自衛権』入門』などを持つ国防のエキスパート。しかし、農林水産大臣、初代地方創生・国家戦略特区担当大臣も務め、“地方創生”にも正面から真剣に取り組む。
オビ裏に、「国主導の金融政策、財政出動のみで地方が甦ることはない。地方が甦ることなくして、日本が甦ることはない。本気で日本を蘇らせるためには、新しい動きを地方から起こさなくてはならない。地方から革命を起こさずして、日本が変わることはない」とある。
さらに本書は、お任せ民主主義と決別し、地方から革命を起こさなければ未来は切り開けないとする基本姿勢から、「補助金と企業誘致の時代は終わった」「観光はA級を目指すべし」「官僚こそ地方で汗を流せ」「里帰りに魅力を付加せよ」―と提言し、『地方と中央、与党と野党、政官財、老若男女の別なく一致できる「創生への道」とは何か』について、初代地方創生大臣として収集した具体的なアイディアを基に示している。本書いわく「可能性と希望に満ちた日本論」である。
主な内容をみると、「はじめに」、日本は有事であると言う。国防の話ではなく、現在進行中の深刻な人口減少と地方消滅の危機を有事と捉え、アベノミクスの先にある成長戦略の「処方箋」は「地方創生」にかかっていると言う。
そして「補助金と企業誘致の時代は終わった」として、いまだに地方が元気だった時代を引きずって国の補助金を当てにし、企業誘致を夢見ていることに警鐘を鳴らし、地方は自ら新しい「創生」の道を切り開け、新しい仕事を立ち上げてPDCA(プラン、ドゥ、シー、チェック、アクション)の管理サイクルを厳しく実践せよと言い、国はそのやる気のある地方を人材と情報で後押しすると言う。
また「観光はA級を目指すべし」として、地方の強みを生かし、生産性を上げるという視点で観光を考えろ、代理店任せのような観光客誘致はやめろと言う。さらに「一次産業に戦略を」取り入れろとして、農業特区、林業や里山、水産資源の利用、生産性の向上を促し、「創生の基点はどこにでも作れる」として豊富な実例を紹介し、ケース・スタディを展開する。
地方行政にも『「お任せ民主主義」との決別を』求め、「勝ち組」になるために個人と地方が自信とストーリーを持って革新に取り組めと言う。
総じて本書は、提言と実例がマッチしていて、行政関係者のみならず、地方生活者、ビジネス開拓関係者などにも役立つ一書だろう。「ですます調」の柔らかい文体も読みやすい。
(山勘 2017年7月24日)
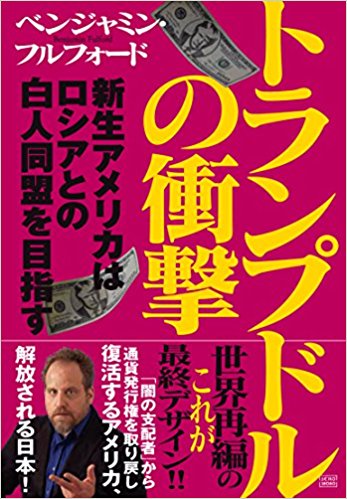 著者はカナダ生まれ。80年代に来日。上智大学比較文化学科を経て、カナダのブリティッシュコロンビア大学を卒業。その後再来日し、「日経ウィークリー」記者、米経済誌「フォーブス」アジア太平洋支局長を経て、現在はフリーランスジャーナリスト、ノンフィクション作家。
著者はカナダ生まれ。80年代に来日。上智大学比較文化学科を経て、カナダのブリティッシュコロンビア大学を卒業。その後再来日し、「日経ウィークリー」記者、米経済誌「フォーブス」アジア太平洋支局長を経て、現在はフリーランスジャーナリスト、ノンフィクション作家。
ドナルド・トランプが勝利した結果、2017年3月現在まで「ナチス派」の残党狩りが本格化している。それで「ジャパンハンドラーズ」(日本を手玉にしている影の人物)が消え、一種の無風状態になっているのだ。
トランプの大統領就任のお祝いに「日本の年金51兆円(4500億ドル)をアメリカへ投資します」と、安倍晋三首相が手土産を渡して喜ばせたように、日本の金融資産をアメリカにせっせと投資してくれれば十分なのである。
それを見事に象徴するのが、2017年2月、3月、突如、日本で吹き荒れた通称「アッキード」と呼ばれる「森友事件」であろう。このスキャンダルが大問題に発展したのが、トランプ政権の国務長官のレックス・ティラーソンが訪日した直後である。彼は石油メジャーの関係者であり、ロックフェラーの影響下にある。トランプ政権のメリットよりロックフェラーのために動いている節があるのだ。
そこで「森友事件」である。CIA筋によれば前から「森友学園がらみのスキャンダルは、小沢政権誕生の実現に向けた〝安倍おろし″キャンペーンの一環」との情報を寄せてきた。今回の「森友事件」は本命ではない。あくまでも「倒閣シグナル」のスキャンダルなのだ。ゆえにマスコミは異常とも言えるほど大騒ぎしていたのである。
おそらくだが、安倍晋三の政治家生命まで絶ち切る「本命」のスキャンダルは、かねてより噂になっていた「勝共連合」(世界統一教会)がらみであった可能性は高い。こんなものが表沙汰になれば、政治家を続けられるはずはない。というより数々の総理を輩出してきた政治家の名門「安倍家」(佐藤家、岸家)のお家崩壊であろう。ゆえに、この「森友事件」が発覚した時点で安倍政権は倒れると考えられていたのだ。
そもそも、たいした政治実績のない蓮舫が民進党の党首に選ばれたのも、この計画に基づき、華僑が資金や人材をバックアップしてきたからなのだ。実際、大手メディアは「日本初の女性首相へ」と持ち上げてきた。これも華僑マネーが流れていたからなのだ。
さて、この素晴らしいプランは、あっけなく破棄されることになる。その理由は本当に情けない。蓮舫の政治家としての器が小さすぎて、この計画を実行するのは絶対に無理だと判明したからなのだ。華僑の支援がなくなれば蓮舫はただの目立ちたがり屋の政治家に過ぎず、野党最大党首としての能力はない。それで、ますます安倍政権が安泰となり、安倍晋三の頭の中は「お花畑」が咲き乱れてしまい、思考能力がどんどん失われてしまった。日本の政治情勢は本当に悲しい状況に陥っている。
蓮舫は、ときに「R4」と称される。この名が付いたのは、蓮舫が自分の子どもにゲームソフトの不正コピーをする「マジコン」と呼ばれる機材を与え、「賢い倹約」とばかりにプログで自慢した。そのマジコンの機種の名前が「R4」だったことから、そう呼ばれるようになった。蓮舫の周囲には、この手の脇の甘い話がごろごろしている。そんな人物が総理になったところで政権が持つはずはない。それで華僑勢力は、いっせいに離反したのだ(エピローグより)
(ジョンレノ・ホツマ 2017年7月26日)
民度
義家弘介(ひろゆき)文部科学副大臣は、「便宜(べんぎ)」を「びんせん」と読み、宮澤洋一経済産業大臣は鹿児島の「川内(せんだい)原発」を「かわうちげんぱつ」と読んでしまった。島尻安伊子(あいこ)沖縄北方担当大臣は、重要な担当地域である「歯舞(はぼまい)」が読めなかった。彼女は、大学で新聞学を学んだそうである。
いずれも東京新聞の記事からの引用だが、「歯に衣(きぬ)着せぬ」を文字通り「ころも」と読んでしまった有名ジャーナリストや検察幹部もいて、日本語の読みは難しいとはいえ、とくに昨今の国会議員たちのあまりの無知無能と教養のなさは酷い。まず不適格であることはもちろんだが、担当者であるにもかかわらず基本用語すら勉強していないという二重の意味で当事者能力に欠けていて、他にもたくさんいるお粗末な失言大臣を含めると本当に情けない。漢詩にも通じていた昔の政治家とはえらい違いである。
誤解を恐れずにいえば政治家は誰にでもできる職業なので、資格や専門知識がなくても縁故や世襲でたまたま議員になってしまう人がいる。そんなのに限ってトンチンカンな言動が目立ち、頭が悪いのにちゃんと勉強しないからか、あるいは勉強しないから馬鹿なのか、とにかく世間の笑いものになりやすい。かくいう政治家の1人である亀井静香氏は「そんな議員を選ぶ選挙民も悪い」と嘯いているが、確かに一理はある。同じ言葉を彼の選挙区である広島の地元民に返したいくらいだ。
昔、ある講演会で、全国展開する古書買取店のオーナーが語った言葉を今でもよく覚えている。「これはオフレコですけど、持ち込まれる本の内容でその地域の民度や文化度がある程度わかるんですよ」。つまり、住民が普段どんな本を読んでいるかで、その地域の教育レベルや知的水準、教養度が判断できるというわけである。
だから、教養のない低レベルの選挙民はバランス感覚もなく、同じようなろくでもない政党や質の悪い議員を選んでしまう。その意味では、読み書きもできない愚昧な議員たちを選ぶ田舎者はもちろん、税金を無駄に使うだけの無能な知事ばかり選んできた東京都民も、全国的に知的レベルが相当低いといわれても仕方がない。愚かな政治家を嗤う前に、そんなのを選んだ私たちも大いに恥じ入るべきだ。
東京都が進めていた築地市場の豊洲移転が、新しい女性知事に代わって汚染処理が未解決だったという衝撃的な事実が明らかになり、それまでの3人の知事のガバナンスのなさ、これまたいい加減な東京都議会の無能ぶりがはっきりした。テレビのキー局や全国紙のお膝元でこんなことがまかり通っていたのだから、マスコミがいう“調査報道”だってどれだけ信用してよいものか。
民主主義国家は原則的に、代議員と彼らを選ぶ選挙民の質ですべてが決まってしまう。古くはヒトラーを生んだドイツ、最近では国民投票でEU離脱を決めたイギリス、あのトランプを選んだアメリカ…。真の選良を選び出すためにも、亀井氏がいうように国民が自らその民度の質を高め、正しい選択眼を養う必要があるのではないか。何しろ日本は、国会議員1人に5,000万円近い税金を使っているのだから。
話は少し違うが、かつてゴルバチョフ氏が日本の首相になってくれたらと思ったことがあった。知名度は抜群だし、日本が苦手な外交に手腕を発揮してくれるのではないかと期待したからである。真のグローバル化を目指すなら、国家の繁栄と国民の幸福と世界平和が実現できるのなら、指導者の人種や国籍など関係ない。今政界を騒がせているような女性党首の二重国籍問題は次元が低いにしても、いつの日か日本人がアメリカの大統領に、フランス人が日本の首相になる日がくると面白い。
(本屋学問 2017年7月21日)
読売新聞の特別編集委員 橋本五郎さんは、小池政治の手法を「越後屋政治」と名づけた(同紙7月8日付)。つまり、時代劇によく出てくるセリフ、「越後屋、お主も悪(ワル)よのう」の、あの越後屋である。それでいくと、このところ安倍首相も悪役ぶりがきわだって「越後屋」にされたきらいがある。
橋本さんのいう都議会での「越後屋第1号」は、ドンと呼ばれた内田茂前都連幹事長である。事実はともかく、なにやら後ろ暗いところがありそうだと選挙民に感じさせるだけで効果は十分だ。その内田氏が引退したら“賞味期限切れ”だから次に行く。「越後屋第2号」は東京五輪のトップ、森喜朗元首相である。こちらも競技会場問題が落着したら次だ。「越後屋第3号」は石原慎太郎元都知事である。たしかに目の付けどころがいい。「第4号」には下村博文自民党都連会長(当時)がなりかけたが、「越後屋にはカリスマ性と知名度が必要」で、その点では今一つ越後屋にはできなかったようだ。さらに、女性政治家は女性に好かれない傾向があるが、小池知事はこうして片端から「越後屋」を仕立てて「男社会のうさんくささ」を突くことで女性層の支持を得た、と橋本さんは見る。
先に私は「問われる活字マスコミの使命」と題するエッセイの中で、豊洲市場移転問題に対する小池知事の「論点はずし」を取り上げた。都議選を目前にした6月20日、小池都知事は突如「豊洲移転と築地再整備」案を発表した。この小池都知事の垂らしたエサにマスコミ各紙はモロに食いついた。たとえば読売は、21日一面トップで「豊洲移転
築地は再整備」と大見出しで報じた。
それまでは「豊洲移転問題」への小池知事の決断がどう出るかが注目されていたのである。ところが突然の「築地再整備」提案で、100%だった豊洲移転問題が50%に“稀釈”されたのだ。つまり小池流の巧妙な論点の拡散、論理のすり替えである。
仮に「豊洲移転」を都議選前に決断しなかったとしたら、決断しない知事として選挙で攻撃される。また「豊洲移転」だけを決断したとすれば、これまで知事が言ってきた安全性や費用の問題はどう解決されたのかを厳しく問われることが目に見えていたのである。そこで「豊洲移転
築地再整備」と出た。これでマスコミや世間は「築地再整備」の夢に釣られたり、再整備・再開発の是非で盛り上がったりして論点が拡散されたのである。結果、選挙の争点にもならなかった。
関連して、最新の文芸春秋7月号(6月発売)に、小池百合子「私の政権公約」と題する大型記事が掲載された。しかしその中に「築地再整備」の文言はない。「築地再整備」は間違いなく選挙直前にひねり出した小池氏一流の“策略アイディア”である。
あの手この手で“瞬間風速”を巻き起こして勝利した小池都政はこれからどうなるのか。頼りないのは小池チルドレンと称される相当数の素人くささがつきまとう新議員諸氏だ。この人たちは、これまでの日常で、身内や知人・友人に政治を語り、見識を示すなどという“習慣”があったのだろうか。
今のところ素振りにも見せないが、小池氏は「国政」を狙っているという見方が強い。しかしこれまでの、時の勢いで誕生した日本新党などいくつかの「知事新党」が、持って2年ほどで雲散霧消していることや、選挙民の気分の移ろいやすさ、歴代都知事の相次ぐ失墜を思えば、都政の勢力維持も国政進出もそう甘くないのではないか。少なくとも「越後屋政治」や論点外しのような「策略論法」では、長く都民の信頼をつなぎとめることは難しいだろう。
(山勘2017年7月24日)
人生おさらばの一言
気の早い6月のお施餓鬼に参加して、高僧の般若心経講義を聞いた。言うまでもなく般若心経はあの世の教えではなく現生の哲学だ。宇宙論的でもあり、唯物論的でさえある。そんな折りに、新聞ニュースで、極めて“醒めた死に方”の事例を知った。
読んだ人も多いだろうが、森鴎外の遺言書の話である(読売7月7日)。この鴎外の遺言書は、亡くなる3日前に鴎外が口述し、親友が代筆したもので、「死は一切を打ち切る重大事件で、どんな権威も反抗できないと信じる」と書かれ、死後の栄典を辞退し、墓には本名(森林太郎)以外は刻まないよう求めているという。「死は一切を断ち切る」という諦観には驚いた。どうやら私の抱いていた森閣下のイメージ、軍服にジャラジャラと勲章をつけた“栄典好き”で、八の字髭で威張っている権威の“権化”で、現世の名誉欲も後世の栄誉欲も強い人物、といったイメージは誤りだったらしい。
死に方と言えば、最後の幕臣、山岡鉄舟の最期がよく知られている。見舞いに訪れた勝海舟が「いよいよご臨終でござるか」と問いかけると、皇居の方角に向かい、白衣で座禅を組んでいた山岡が、「ただいま涅槃に向かうところでござるよ」と答える。勝が「よろしく成仏なされよ」と辞して、町をぶらついて屋敷に戻ったら、山岡死去の知らせが先回りして届いていたという。
今年は、この山岡鉄舟の130回忌に当たる。(臨済会「法光」271号に「鉄舟130回忌に寄せて」の玉稿がある)。慶応4年(1868)、鳥羽・伏見の戦いで幕府軍が惨敗、徳川慶喜は江戸に逃げ帰って上野寛永寺に謹慎した。鉄舟は、君主慶喜公の恭順の赤心を官軍側に伝えて江戸城攻撃を阻止し、江戸の町を戦火から守ろうと考えて、勝海舟に直談判する。
どうする気だと問う勝に、鉄舟は、駿府にまで迫っている官軍本営に乗り込むと言う。官軍としては鉄舟を「斬するか縛するか外なかるべし」と言い放ち、斬られる前に言上すると言った。結局、鉄舟の“蛮勇”が奏功して江戸城攻撃は中止となり、150万人の江戸が戦火を免れた。この鉄舟に、いつ詠んだか知らないが、「死んだとて損得もなし馬鹿野郎」の一句がある。含蓄に富む一句だが、皮相的に言ってしまえば、「でーじ(大事)なこたァ生き死にじゃ無エ、べらぼうめ」と言ったところだろう。
これはだいぶ以前のエッセイ「人生を締めくくる“一言”」に書いたことだが、どのように死の局面を迎えるかは人知の及ばざるところで、病院で死ぬか、自宅で死ぬか、路上で死ぬか、いつどこで、どんな死を迎えることになるのかわからない。死は予測も練習もできないから、けっきょくは出たとこ勝負で死を迎えざるを得ない。
凡俗の徒としては、鴎外先生、鉄舟先生のようにいかないのは当たり前だが、どんなかたちで死を迎える場合でも、私は単純に「ありがとう」と言おうと心に決めている。臨終を迎えたその時に、傍らに誰が居ようと、そして誰が居なくてもそう言おうと決めている。
ただしこんな単純な一言も、死に際に頭がボケていなくて口がきければ、さらにそれを口にできる一瞬、僥倖の一瞬に恵まれれば、の話である。たぶん実際は、呆けていたり慌てたりして、醜態をさらすかもしれない。だからこそ、つね日頃から「かくありたい」と念じている。
(山勘 2017年7月26日)