2017年3月24日(金)午後3時~午後5時(会場:三鷹SOHOパイロットオフィス会議
室、参加者:狸吉、山勘、恵比寿っさん、ジョンレノ・ホツマ、本屋学問)
今回も早々に書感を投稿した致智望さんが急な事情で欠席となり、残念でした。「語彙力…」は日常の会話や読書から思い当たることしきりです。「病から…」も、最新の西洋医学の限界から漢方を模索するテレビドキュメントを観たばかりで、これもタイムリーでした。「財務省と…」からの皆さんの共通の感想は、「増税する前に国がやるべきことはたくさんある」。社用族と役人、他人の金を自分の金のように無駄使いする2大悪です。
致智望さんの「日本がやばい」は、次回に発表をお願いします。
(今月の書感)
「語彙力こそが教養である」(狸吉)/「潰えた野望」(本屋学問)/「財務省と大新聞が隠す本当は世界一の日本経済」(恵比寿っさん/「大同類聚方」探索「病から古代を解く」(ジョンレノ・ホツマ)/「仁義なきキリスト教史」(山勘)
(今月のネットエッセイ)
「「正論」不要、「ポスト真実」の時代」(山勘)/「正月映画「沈黙」からの歴史的“雑念”」(山勘)
潰えた野望─なぜバーグマスター社は消えたのか/マックス・ホーランド著 三原淳雄・土屋安衛訳(ダイヤモンド社 1992年3月 本体2,718円)
アメリカの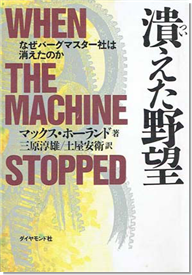 コングロマリット(複合企業)フーダイ社(当時)は1983年、日本政府が工作機械業界と共謀してアメリカに不公正な輸出をしているとして、関税障壁を設けるようアメリカ政府に要請した。1年後、当時のレーガン政府はこれを却下するが、このことが本書を執筆するきっかけになったと著者は書いている。というのは、著者の父親はフーダイ傘下の名門工作機械メーカー、バーグマスター社で30年間技術者として働き、父から聞いていたバーグマスター社の内情とフーダイ社の主張があまりにも違っていたからだ。
コングロマリット(複合企業)フーダイ社(当時)は1983年、日本政府が工作機械業界と共謀してアメリカに不公正な輸出をしているとして、関税障壁を設けるようアメリカ政府に要請した。1年後、当時のレーガン政府はこれを却下するが、このことが本書を執筆するきっかけになったと著者は書いている。というのは、著者の父親はフーダイ傘下の名門工作機械メーカー、バーグマスター社で30年間技術者として働き、父から聞いていたバーグマスター社の内情とフーダイ社の主張があまりにも違っていたからだ。
著者は大学でジャーナリズム、国際関係、経済学などを学び、「ヴォイス・オブ・アメリカ」などに勤務後、作家として独立した。バーグマスター社の社員始めアメリカ工作機械工業会(NMTBA)、工作機械専門誌「アメリカン・マシニスト」、商務省、証券取引委員会(SEC)など5年に及ぶ取材の後、最初は雑誌に掲載する予定だったが、長大すぎることとテーマの性格から書籍として出版したと「はしがき」に書いている。しかし、綿密な取材によってアメリカ工作機械産業衰退の原因を追ったこのドキュメントは、翻訳の良さも加わって実に読み応えのある見事な読物になった。
タレットボール盤やマシニングンタの先駆者として有名なバーグマスター社は、創業者バーグをはじめ職人気質の技術者集団だったが、1960年代になるとアメリカの工作機械産業全体が日本との熾烈な競争に入り、業績が悪化する。一方、無反動砲を発明したフランスのフーダイの特許と名前を買い取ったフーダイ社は、自動車用ショックアブソーバ始め自動車部品、建築資材、工具、工作機械、配合飼料まで手掛ける“コングロマリット”の代名詞ともいえる企業に成長した。
バーグマスター社の首脳以下従業員たちは、フーダイ社の傘下に入った1965年以降も工作機械づくりの現場主義を貫くが、手を汚すことが嫌いなフーダイ社幹部の発言力が増すたびに後退した。コングロマリットの生命は「報告書」、「予測」、「予算」、いわば数字による経営といわれ、バーグマスターの業績はフーダイの期待どおりには上がらない。そこで経営陣は、手動工具や事務機器で成功したMRP(原材料需給計画)という生産方式をバーグマスターの工作機械生産にも適用する。
一見先進的なこのコンピュータ管理システムは、生産性を上げ、在庫を圧縮し、技術調整が楽になり、多品種少量生産を可能にするという理想的な方式に思えたが、何千という高精度部品を必要とする工作機械の生産には適さず、逆にコスト上昇と性能低下を招き、競争力は一気に落ちた。
機械をつくる機械,“マザーマシン”と呼ばれて工業の発展に不可欠な工作機械産業はアメリカでも世襲が多いそうだが、熟練技能や技術、ノウハウといった古臭いが卓越した技能を支えるための伝統精神がとくに重要であり、ものづくりには欠かせない企業文化である。
1966年、アメリカの工作機械業界では22件のM&A(合併・買収)があったが、業界外からの参入が増えて機械の品質が下がり、「アメリカン・マシニスト」誌は「コングロマリットの経営陣は、この重要な部門(工作機械)に“鍋釜”との区別がしっかりできる役員を送り込んでほしい」と皮肉を込めて書いた。
かつて世界一の規模と技術力を誇ったアメリカの工作機械は、今日では軍事、航空宇宙などごく一部を除いて事実上なくなってしまっている。その衰退の大きな理由の一つに、国防総省(ペンタゴン)の工作機械購入が平和時でも国内生産の20~30%といわれたほど産業全体が軍需に依存し、その安定体質がリスクを避け、新技術開発への努力を怠ったことが挙げられる。
アメリカから“ノートリアスMITI”(悪名高き通産省)と呼ばれた通商産業省(現・経済産業省)は、日本企業にとっては繊維、家電、自動車、コンピュータまで日米貿交渉で国益を代弁する実に頼もしい存在だったが、著者は本書でMITIの存在よりも一般的な経済要因、つまり、健全に運営された日本の経済によって資本形成と投資が促進され、勤労意欲の高い、よく管理された労働力が輸出を高めたと書いている。1950年代初め、アメリカのダレス国務長官が吉田首相に「日本がアメリカ市場に輸出できる製品はないから、どこか他を探すべきだ」と語ったそうだが、まさに隔世の感といえよう。
本書には、当時は日本工作機械工業会(JMTBA)に加盟していなかったアウトサイダーの山崎鉄工所(現・ヤマザキマザック)が登場し、MITIの“行政指導”に反発しながら他社に先駆けてアメリカに進出してバーグマスター社と提携し、現在では世界的な工作機械メーカーになったことや、本格的にアメリカ進出を目指した工作機械大手の大隈鉄工所(現・オークマ)が、MITIの依頼で一時はバーグマスターを救済する話まであったことも紹介されている。
さらに、NC装置開発で有名なファナックの創業者、稲葉清右衛門氏や牧野フライス製作所の創業者、牧野常造氏のエピソード、通産省・工業技術院機械技術研究所などについても詳細に書かれていて、国内本以上に当時の日米の工作機械事情をよく知ることができる。
欧米に比べて工作機械の技術開発が遅れていた日本は、戦後アメリカとのライセンス契約によって技術を磨き、次第に他を圧倒していくが、これについても著者は、19世紀のイギリス以来、模倣はあらゆる近代工業国家の技術発展に不可欠で、ライセンスを得た日本が実力を蓄えてアメリカ市場に深く進出したことを評価し、キャッチアップにはどうしても必要なことだったと好意的である。
フーダイ社の強みとしては、傘下のバーグマスター社が海外からの挑戦には最強の部類のはずだったが、結果的にはトップ人事が弁護士や公認会計士で、工作機械はおろか生産にも精通しておらず、買収後のバーグマスター社の高利益も過去の成果から生まれたものであり、献身的で有能な従業員は排除され、会社の方針に忠実なイエスマンだけが残り、管理主義が開発力や高度の技術を枯渇させた。それが、バーグマスター社始めアメリカ工作機械産業の悲劇だったと本書は結論付けている。
終焉の日を迎えたバーグマスター社には設備機械を買い叩く他企業が押しかけたというが、かつての社員たちはどのような思いでそれを見ていたのだろうか。目標と情熱を失った企業の典型的な末路であるが、日本も明日は我が身、肝に銘じるべきである。
(本屋学問 2017年3月16日)
財務省と大新聞が隠す本当は世界一の日本経済/上念 司(講談社+α文庫 本体880円 2016年9月20日初版一刷発行)
 著者紹介 じょうねん・つかさ
著者紹介 じょうねん・つかさ
1969年東京都に生まれる。中央大学法学部法律学科卒業。
日本長期信用銀行、臨海セミナーに勤務したあと独立。
2007年、勝間和代氏と株式会社「監査と分析」を設立し、取締役・共同事業パートナーに就任。
2011年の東日本大震災に際しては勝間氏と共に「デフレ脱却国民会議」を設立し、事務局長に就任。
震災対策として震災国債を日本銀行の買いオペ対象とすることを要求。白川明総裁までの日本銀行の政策を強く批判してきた。著書に『「日銀貴族」が国を亡ぼす』(光文社新書)、『異次元緩和の先にあるとてつもない日本』(徳間書店)、『経済で読み解く大東亜戦争』(ベストセラーズ)などがある。2008年退官。
まえがき なぜ彼らは700兆円の政府資産を隠すのか
日本経済の実力と官僚・記者の実力
日本国の財政の嘘
税と金利と社会保障の真実
日本と中国とEUの近未来
あとがき 日本経済を貶める行為の本質
日本はGDPの2倍の借金を抱え、その金額は≒1000兆円、国民一人当たりにすると≒830万円。
ずっと以前から言われてきていることで、日本は破産するかもしれないと不安を駆り立てて、挙句の果てには消費税増税を煽り立てている節がある。
著者はいわゆる数字に強く、いろいろな角度から論じて、日本の経済は安泰だ、いや世界一強いと述べている。
特に著者が強調しているのは、大新聞(その傘下の民放も含め)が日銀や財務省の見解を無批判に報道し、日本経済の悲観論を垂れ流すのはなぜなのか?というところから、財務省の記者クラブ「財政研究会」や日銀の「日銀クラブ」のキャップを経験しないと出世できないからだと断言している。
新聞記者も、特ダネを掴むより、むしろ「特オチ」を嫌う。何故なら権力側から嫌がらせを受けて重大な情報を貰えず、自社だけ横並びのネタを乗せられないと上からどやされるからだ、と明快。
著者の師匠、イエール大名誉教授の浜田宏一氏は某紙のコラムの執筆の際、原稿を何度も突っ返されたと暴露しています。何故なら、原稿に「増税が景気に悪影響を及ぼした」とか「緊縮財政で却って財政再建は遠のく」という部分が財務省の意に添わず、編集者がこれを削ろうといろいろと難癖をつけたという。
マスコミが役所に対して自主規制をして、経済学的に全く根拠のないことを代弁している。
2章ではそれぞれQ&Aの形で、わかりやすく日本経済の強さを述べているが、そのうちの1つ。
借金が1000兆円と言うが、資産については触れていないのはおかしい。
日本の財政赤字は大変で、「消費税増税しないと日本は滅ぶ」ように言うが政府資産は679.8兆円ある2015年度末(財務省)。この時点での負債は1171.8兆円。
政府資産というとインフラなどで換金性は低いと思わせるが≒70%は金融資産なので、換金性は高い。政府資産は横ばいで推移しているが負債は漸増しているが、この中には国の子会社である日銀の数字が含まれていない。
統合資産としては≒900兆円。うち有形固定資産は179.6兆円なので≒20%。それ以外はすべて金融資産(有価証券139.5、
未収金など11.5、貸付金138.3、運用寄託金103.7、出資金70)。運用寄託金は国民のものなので除外して579兆円もの金が国庫に眠っている。取り崩しても良い金だ。
政府の借金は完済しないといけないものなのか。返す必要はない。
政府は死なないので続く。名目GDP成長率≻名目公債利子率であれば借金の増えるスピードよりも収入の増えるスピードが大きいわけだからいずれ完済できる。
(恵比寿っさん 2017年3月17日)
 「大同類聚方」探索「病から古代を解く」/槇佐知子著(新泉社 1992/8初版、2000/6改訂版発行)
「大同類聚方」探索「病から古代を解く」/槇佐知子著(新泉社 1992/8初版、2000/6改訂版発行)
「大同類聚方」とは、平安のはじめ、全国の神社や豪族などに伝わる医薬と処方を、勅命によって集大成された全100巻の日本最古の医学書だそうです。
明治(1912年)になり、偽書と断定され、歴史の闇に封印されてしまいました。槇佐知子氏による「全訳精解大同類聚方」が1985年に平凡社より刊行され、その後1992年に普及版が全5巻(各巻5000円)で刊行されたがいずれも絶版になっています。
原本の内容の一部は国会図書館へのインターネットで確認できましたが、著者の解説本がないと原本の漢文を解読することは私には不可能でした。
そんな状況で図書館に本著者の関連した本の存在(保存庫)を知りました。本書は、「大同類聚方」から読み取った彼女の解読本の一つですが、おおよその内容から当時の様子が伺えます。
「漢方薬」という名称は広く知れ渡っていますが、古代日本において「和方薬」ともいうべき処方があったが、消し去られていたことを知りました。漢方から伝わったものという考えがあったように見受けられます。
なぜ、「大同類聚方」に興味をもったかというと、ホツマツタヱの記述の中に、オオナムチ(大己貴命)とスクナヒコナ(少彦名命)が出会い、日本全国を巡り、薬草の記述が出てくる個所があります。
ホツマツタヱの記述には、ありとあらゆる分野の記述が織り込まれているので、専門分野や得意な分野の事であれば、おおよその解釈はできますが、それ以外のことについては思い込みで的外れの解釈をしてチンプンカンプンです。
全てを知り尽くしている人はいないと思います。そこで、解らないなりに解釈するために、先人者の解釈を良しとしてそのまま引用したりしています。100人いたら100通りの解釈があると言われるのも頷けます。
今回、本著者の解読書の中から、興味ある内容が伺えました。
病気の症状、草木や鉱物の薬効や薬名などの他に、多くの処方された人の名前などを読み解いていくと、新たな発見が見えてきます。
大陸から伝えられたものがあったにせよ、漢方とは違う日本古来のものがあったと解釈できるのではないかと思えます。
ホツマツタヱを解読するのに、この分野の記述を確かなものにすべき非常に貴重な本であると思いました。
多岐にわたるため、いくつかの記述のみ取り上げてみました。
花鎮(はなしずめ)薬
(花鎮祭) 桜の花が散るとき、疫病の気が四方に飛び散って流行すると考えた古代の人々が、これを鎮めるために、桜の花と桃の樹皮を用いた。
これは、大神(おおみわ)神社に伝わっている薬方で、ここの御祭神はオオナムチ(大己貴命)とスクナヒコナ(少彦名命)で、我が国の医業の鼻祖として広く知れ渡っている。
イザナギが亡くなったイザナミを追い求めて黄泉の国へ行ったくだりで霊薬が出ている。タケノコは渇きの病の薬、気力をつけ体内のすい液のめぐりをよくする食べ物だがたくさん食べることは禁じられている。ブドウやタケノコを死神の使いの黄泉醜女(よもつしこめ)が追うのを忘れて食べたという設定は、病勢が弱まった状態を示している。
桃の実(桃子・とうし)は薬用と同時に呪術的な力があると考えられていた。
桃は中国原産と言われていますが、ホツマツタヱ24綾の記述の中に、ウケステメ(後のニシノハハ神・西王母)が2回来日して、ミネコシ(峰でも使える輿)を寄贈されたお礼に桃を土産に持たせています。これが国に帰ってから貴重なものとして広まったことが原産地になってしまったと思われます。
硫黄を使った薬 酔い止め 精神安定剤 美肌薬などの効用と作り方などの記述。
阿可利薬(アカリヤク)は、 身痛くて、ほてり、たわごとを言うものに用いる。
やまごぼう・葛根・朴皮・はじかみ・セッコク(ラン科)を配合する。
カザホロシヤミは、現在で言う、風疹・ハシカやチフス、ツツガムシ、ジンマシンのように皮膚に発疹が出る病気、帯状疱疹を示していると思われる。
カハヤナギ(ネコヤナギ:解熱剤・下痢)・ツチタカラ(独活:解熱・鎮痛・発汗)・ハチスノミ・ヤマセリ・カラスクハヒ(滋養を与え虚寒の症状を正常に)の薬草を配合する。
古代の人が抱えていた病や、当時の薬草の名前やその処方の仕方から、当時の生活様式の一端が伺い知ることができました。
なお、著者は平安・鎌倉時代にかけての「医心方」全30巻の翻訳もされております。
「自然に医力あり」(スギ花粉症の治療法と杉の文化史・自然の癒し・医心方の世界・夏から秋にかけての健康法・古代人の健康法に学んで等々)や、「野菜の効用」(医心方4千年の知恵から)なども刊行している。
(ジョンレノ・ホツマ 2017年3月18日)
仁義なきキリスト教史/架神恭介(筑摩書房 880円+税)
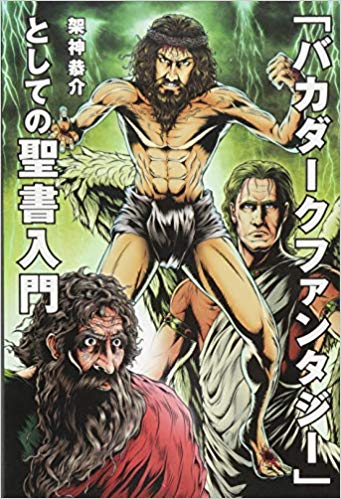
キリスト教は世界最大の宗教であり、その信者は23億人(イスラム教は17億人)。なんと世界の3人に1人がキリスト教信者だという。その偉大な宗教の歴史をやくざの歴史として描いたバチ当たりの一書がこれである。しかしキリスト教は、学校や病院を建設したり、美術・芸術・文化の振興に寄与したりする一方、十字軍の殺戮をはじめ、戦争、虐殺、人種差別など負の遺産も築いてきた。あながちやくざ的側面を否定することはできない。
本書のオビに「あいつら、言うてみりゃ人の罪でメシ食うとるんで」とある。本文は、磔柱のキリストが「おやっさん、おやっさん、なんでワシを見捨てたんじゃ~!」(エリ・エリ・レマ・サバクタニ)と、神なる大侠客・ヤハウェに訴えるシーンから始まる。本書はまさに大歴史エンターテインメントである。なぜか会話は全員名古屋弁だ。
主な内容は、やくざイエスの死、伝道師パウロの欺瞞、ローマ帝国とイエス組の相剋、第4回十字軍の非道、極道ルターの宗教改革など。「おまけ」として、出エジプト・若頭モーセ(一般にはモーゼとも)の苦闘物語がある。これを先に読んでもいい。
イエスの時代も厳然として影響力を及ぼしたユダヤ教の神は唯一神のヤハウェ。キリスト教の遠祖にして残忍な大親分である。推定BC13世紀、旧約聖書では親分ヤハウェに命じられた若頭モーセが、エジプトで奴隷状態になっていたイスラエル人(ユダヤ民族)を脱走させ、ヨルダン川のほとり、カナンの地に侵入し、先住民族を殺戮して定住した。
時は流れて推定AC30年。イエスはエルサレム神殿の支配体制(民衆からの搾取)を批判し、ローマ警察に捕縛されて死を迎えるに至る。イエスの死後、弟子たちは布教活動を再開する。官憲や他の組と抗争を続けながらキリスト組は広域任侠団体となっていく。
キリスト組の闘争の歴史において名を遺した1人にパウロがいる。組の財務部長を命じられたパウロの、各地の教会や信者からの金集めは、恐ろしく居丈高で傲岸不遜で恐喝的でまさにやくざである。信者に説くときは、時には幼子を育むように優しく、信者に苦労を掛けまいと自ら働いて日銭を稼ぎ、常に敬虔な態度で―といったイメージはすべて自らそちこちの関係先に出した手紙(パウロ書簡)に残る自画自賛である。
キリスト教の二大汚点は、魔女狩り(異端審問)と十字軍だ。人間の排他性、攻撃性、残虐性が容赦なく発揮された。十字軍も残忍だが、第四回の時は、遠征途上の財政破たんで目的の聖地にたどり着けず、事の成り行きで同じキリスト教徒の都であるコンスタンティノポリスを攻撃、占領してゼニを稼いだ。
宗教改革のルターは「(暴動の最中の農民を)打ち殺し、絞め殺し、刺し殺さなければならない」と「農民戦争文書」に書いた。激烈な男だった。宗教改革で信仰の自由を手に入れたのは領主階級だけ、民衆が信仰の自由を手に入れるのは、1世紀後の、カトリック陣営とプロテスタント陣営による大戦争-30年政争の後、1648年だった。
英国王ヘンリー八世は、離婚を認めてくれないカトリックと縁を切り、自ら「英国の教皇」を宣言。「俺を異端だというやつはぶち殺す」と言って、反抗したトマス・モアをぶち殺した。以来英国は国王が替わるたびに宗旨替えを続け、英国宗教界も右往左往した。
かくて本書は、恐れ気もなくキリスト教の裏面の闇を “照射”する。
(山勘 2017年3月20日)
語彙力こそが教養である/斎藤孝(角川新書 2015年 本体840円)
 本書は語彙の豊かさは教養に比例する。その語彙を増やすにはどうすればよいか、具体的に解説している。
本書は語彙の豊かさは教養に比例する。その語彙を増やすにはどうすればよいか、具体的に解説している。
著者はまず何故語彙力が必要かを説く。日本語の90%を理解するのに必要な語彙は約1万。これに対し英語は3千、フランス語。スペイン語は2千で大きな差がある。覚えるべき語彙が多いのは負担だが、複雑な内容を短く的確に伝えることもできるのだ。
話し相手との会話の中に気の利いた言葉が登場した際、それを生かした応答が続けば、互いに相手の教養レベルを同程度と理解し、以後有意義な時間を持てるであろう。逆に最初のやり取りが理解できぬと、「この人はレベルが低い」と判断され、以後蚊帳の外に押し出されてしまう。よって、相手にさりげなくこちらの教養レベルを知らせるため、常に語彙を増やしておく必要がある。
語彙は単に言葉の意味を知るのとは違う。どのような場面で使われるか、文章の要素として覚えこむ必要がある。そしていつでも使えるよう頭に叩き込まなくてはならない。そのために効果的なのはよい文章の素読・音読である。続いて、毎週3冊本を読め。難しい本も読め。ミステリーもいいぞ、インターネットも活用せよ、などいろいろ役に立つ助言が並ぶ。論語、三国志、徒然草、平家物語など具体的な書名が挙げられているのも有難い。
著者の説くところはすべて説得力があり、まことにもっともである。その一方、著者は語彙を増やすため、週末にNET配信の映画を9本も見て、録画番組は溜まる一方。買った本もつんどくが増えて行くと嘆いている。著者のようにモノ書きが本業ならばそれでもよいが、本業の合間に本を紐解く大方の読者にとって、そこまで徹しきれぬのではないか?
また、「同じ教養レベルの者同士でないと有用な情報交換はできない」こともよく分かる。しかし、話題によっては仕方の無いことであろう。たとえば囲碁、カラオケ、ゴルフなど趣味について一方がまったく無知な場合、相手は教えることに徹するか、話題を変えざるを得ない。本書の教えを生かすには、それが通用する世界を見定める必要があると感じた。
先日、カフェ「オモンパカル」なる店を名前の由来を聞いたら「慮る」!「慮る」は「オモンBAカル」と長年思い込んでいたが、何と「オモンPAカル」が正しいのだそうだ。歳をとってもまだまだ学ぶことはあるものだ。
(狸吉 2017年3月23日)
「正論」不要、「ポスト真実」の時代
私が所属する美術団体の委員会のあと、たいてい数人の仲間と一杯やる。メートルが上がると会議への不満が出る。意見が通らない腹いせから「正論は通らない」というグチが出た。これに「いや正論は必ず通る」と反論が出る。私は「通らないのが正論だ」と混ぜっ返した。そもそも「正論」とは何か。人生を長年やってくると?世論をリードする「正論」や、世の中で行われている一見「正しい」ことのうさん臭さが見えてくる。
どうやら、「正しさ」や「正論」を振りかざすのは今の世の中ではウケなくなった。9年ほど前に、硬派の論陣を張る月刊誌が相次いで休刊した。朝日新聞社の「論座」、講談社の「現代」、集英社の「PLAYBOY日本版」、自由社の「自由」などが売れ行き不振で廃刊に追い込まれた。そんな中で、ライバル朝日の「論座」を蹴落として、産経新聞社の「正論」が生き残った。右寄りに根強い購読者が多いということか。
あるいは、勝敗の分かれ目は朝日の理屈と産経のチエの違いか。ここで面白いのは、相当に主張の強い産経「正論」が、ネット情報によると、執筆者に原稿を依頼する際に、「大上段に正論を振りかざす論調ではなく、読者に分かりやすく書いてほしい」と頼んでいるという。いずれにしても、とんがった「正論」(産経「正論」ではない)はモテないということである。
素直に考えれば「正論」すなわち「正しい議論・意見」(日本語大辞典)が通用しないはずはない。しかし現実には人の集まりで正しく議論することは難しく、正しい意見(と思われる意見)が通らないこともしばしばある。しばしばどころかそれが普通だと言ってもいい。多数決による決定も、「正論」か否かより、多数の“常識的”な判断や、利害得失や付和雷同や無知や勘違いの足し算で決まることが多い。英国のEU離脱決定やアメリカのトランプ大統領選出もそれである。多数決で決まったことが、「正しい議論・意見」で決まった「正論」だという論証はおよそ不可能であり、逆に、少数派の主張、孤立した主張がしばしば正論であることは容易に論証できる。いまや多数決は民主主義の“欺瞞”である。
ついでに言えば、資本主義の欺瞞も明らかになりつつある。すでに数年前、ジョン・K・ガルブレイス著「悪意なき欺瞞」(佐和隆光訳、ダイヤモンド社)は、現代の政治経済体制は、「現実とはほとんど関わりがなくても、もっともらしくて信頼されやすいことが信頼されるという真実」に基づいて、自分達にとって都合のいいように創作されてきたと指摘した。この欺瞞者たちが、特定の利益集団に組みしたり歯向かったりするわけだが、欺瞞者たちには罪の意識がないどころか、むしろ自己満足に浸る。そこが「悪意なき欺瞞」たる所以である。その、「自己を利するために流布する信仰、わざとらしいナンセンス」を見破らなければならないという。「欺瞞」は「正論」とは真反対に位置する「曲論」の最たるものである。
問題の「正論」が、本当に「正しい」かどうかは時と場合によって異なり、正しい「議論・意見」も、時と場合によって判断や結論が真反対になることがある。たとえば多くの場合、「生かす」ことが正しいかもしれないが、時には「殺す」ことが正しいとされる場合もある。こうなると正論の「正」は正副の正で、「正論」とは「主として主張する意見」と解釈するのが妥当で、その内容が真実であろうとウソであろうと関係ないというのが現代風の解釈だと言えそうだ。その方が、「真実でない情報」が大手を振ってまかり通る「ポスト真実」の時代にふさわしい解釈だろう。「正論」の虚偽や多義性は、「正論」「正義」を振りかざして殺戮を繰り返してきた歴史が証明している。もちろんそれでいいはずがない。本来の「正論」が通じなくなった「ポスト真実」の時代は、これからどこに向かうのか。
(山勘 2017年3月20日)
正月映画「沈黙」からの歴史的“雑念”
正月には、いい映画を一本観たいと思って選んだのが、遠藤周作原作の「沈黙-サイレンス-」である。舞台は江戸初期。ポルトガルのキリスト教司祭2人が、先に渡日した師と仰ぐ司祭が棄教したという噂を信じられずに、真実を探るべく、キリシタン弾圧下の長崎に潜入する。そこでは、隠れキリシタンの日本人たちが棄教を迫られ、厳しい拷問を受けている。
ついに司祭たちも捕らわれて棄教を迫られる。ひとりは殉教の死を選び、もうひとりの、映画の主人公となる司祭は、役人によって師の司祭に引き合わされ、師が棄教して複雑な心理を抱きながら奉行所の翻訳仕事などをして生きていたことを知る。
映画には多くの魅力的な日本側のキーパーソンも登場する。その中の1人であるキチジローは、最初は司祭たちの日本潜入に手を貸しながら、役人に司祭を売り、やがて自分の弱さに苦しんで救いを求める。人間のズルさや弱みをさらけ出しながらドラマを盛り上げる。
主人公の司祭も、最後は捕らわれの身でのっぴきならぬ状況に追い込まれ、3人の信者が逆さ「穴釣り」の拷問に苦しむ様に耐えかねて「踏み絵」に足を置き、棄教に追い込まれるしかし、映画作品としては、拷問の場面などで緊迫感があるものの、すばらしい風景の中で展開する全体のストーリーにはさほどドラマチックな起伏がない。そこで原作の内容を確かめたくなり、正直あまり好みではない遠藤周作文学だが、原作を読んでみた。そこで、この映画が、主人公の棄教にいたる一本筋の心理ドラマであることが解る。そして改めて感じたのは映像と文学の違いである。たとえば棄教にいたるクライマックスの「踏み絵」で、キリストの顔に司祭が足をかけた瞬間の葛藤を原作ではこう描写する。
「その時、踏むがいいと銅板のあの人は司祭にむかって言った。踏むがいい。お前の足の痛さをこの私が一番よく知っている。踏むがいい。私はお前たちに踏まれるため、この世に生まれ、お前たちの痛さを分かつため十字架を背負ったのだ」。こうした心理描写の映像化が容易でないことは素人でもわかる。
そして棄教した司祭は江戸に移され、死去した人の戸籍と名前とその妻と子を当てがわれて、転びバテレンとしてひっそりと生きる。しかし「私はあの人(キリスト)を裏切ってはいない」と信じ、「今までと違ったかたちであの人を愛している。私がその愛を知るためには、いままでのすべてが必要だったのだ。私はこの国で今でも最後の切支丹司教なのだ。そしてあの人は沈黙していたのではなかった」と顧みる。30数年を生き、齢64でこの世を去る。
原作にはないが、最後の棺に収められる司祭に、妻が隠して入れた棺の中の十字架が感動的な映像の強みを発揮する。この映画の、米国を代表する巨匠といわれるマーティン・スコセッシ監督は、公開に先立って来日し、映画化に28年かかったと言い、原作をどう解釈し映像化すべきか、長年にわたって脚本化に苦心したと語っている(朝日新聞1月20日)。
話は飛ぶが、昨年の正月は「海難1890」を見た。これは、1890年、トルコの軍艦が紀伊大島沖で遭難し、大勢の乗組員が島民に救われた事件を描いたもので、物語の最後は、時を経て1985年、イラン・イラク戦争勃発時に、テヘランに取り残された日本人がトルコからの善意の救援機で脱出できた顛末を描いた感動作である。国や文化が違っても人間の「真心」が信じられる物語である。ところが現実社会では、この映画が封切られた昨年の正月(1月12日)、トルコのイスタンブールでイスラム国による自爆テロ事件が起きた。まさに歴史は変転し、連鎖している。変転しながら連鎖するのが歴史でもある。
「沈黙-サイレンス-」は、日欧の宗教や文化の違いを描き、時代や国策と信仰との相剋を描く。この映画が上映されているいま、トランプ大統領の米国やヨーロッパ、世界における宗教的な排除、人種の分断、排他的な国策など、時代の転換点を思わせるただならぬ歴史的・危機的風潮が高まっている。この映画は、そんなことも考えさせる。
(山勘 2017年3月20日)