戦後史の正体/孫崎 享(創元社 2012年8月 本体1500円)

第2次世界大戦後から今日までの日本の歴史を詳しく記述した書籍は意外に少なく、内容も客観性を欠いた偏ったものが多かった。しかし、読者は多くの情報を新聞記事から得ているため、多くの誤解をしていることが分かった。また、この「戦後史の正体」では比較的公平に各時期における日米のVIPの考え方と行動を紹介しているため、その実態をよく理解することが出来た。
以下に、其の主な人々の日米への対応と言動を紹介してみたい。
1 第2次世界大戦終結と日本と米国の対応
1945年8月15日正午、NHKを通じて昭和天皇が自ら戦争の終結を語られ、同時にわが国は米国、英国、中国とソ連の4ケ国が提示した共同声明を受け入れるというものであった。それから約2週間後の9月2日には、日本は降伏文書に署名し調印式を終えることになった。日本国内は余りに急な事態の展開に騒然とし、梅津参謀長や重光葵外務大臣は無謀とも思える米国の占領政策に反対したが、天皇が自ら終戦に対する国民の対応について語られた。更に、多数の戦争犯罪人が処刑されそうだという情報があったことを思い、天皇は「占領軍が必要とあれば沖縄を始め島々を長期にわたって米国に預けてもよい。戦争犯罪者の処分は慎重に行って欲しい」とGHQに打診されたことが今になって分かった。
2 日米関係の良好な維持には特殊の技法が使われていた
このような雰囲気で日米は良好な関係維持を何となく保ってきたが、今から思えば結果オーライ的に順調に推移し今日に至っている。終戦後50年を経過し、アメリカでは戦後トルーマン大統領からケネデイ大統領やニクソン大統領を経て今やオバマ大統領の世代になっている。日本では終戦直後の鈴木貫太郎首相でスタートしたが、特に評価が高いのは吉田茂首相であった。
「吉田首相はマッカーサーと対等の立場を自然にとることが出来る人物である」と評価されてきた。しかし、現実はそうでなかった。吉田首相は確かに表面的には貫禄も一流であったが、其の舞台裏では米国側から悪く思われないように神経質になっていた。前述の重光葵も其の例で、その他数名の有言居士が吉田の指示で追放されていた。そのようにして、アメリカの戦略にいい形で従う方法を示したものと見ることができる。
3 冷戦以降の主な政治問題とそれに対する日米の対応
第2次世界大戦が終わって数年後の1950年には朝鮮半島が南北に分断され、北朝鮮軍が国境を越えて南進してきた。これに対応する力を持たなかった韓国は国連軍の力を借りて北鮮軍を追い返したが、今度は中国がこの争いに介入し事実上中国対国連軍の戦いになった。この戦いのお陰で日本の産業はかなり復活した。同時に日本は利用できるという見方に変化したので、マッカーサーはトルーマン大統領から解任させられることになる事件にまで大きくなった。
次いで1951年には日米講和条約が締結されると、日本は更に米国からの経済支援にたよるようになり、他方、日本では独自発展を望むグループとの意見の対立がでてきた。其の中で親米派の吉田首相は米国の支援による経済発展の意見を採用したが、其の後石橋首相に替わって吉田案が通用しなくなってきた。むしろ、日本における米軍駐留問題と中国に対する日本の対応に食い違いが大きく取り上げられた。この問題は広く日本中の関心となり、遂に1960年の100万人を超える反対デモに発展した。しかし、まもなくデモは鎮圧され終結したが、全学連学生や労働者に政治関心が強まった事件であった。
その後、1970年にも安保闘争が起きたがグループ数も減り、比較的穏やかに終結した。それにアメリカでは、ベトナム戦争での対応で日本の問題は影を潜めた。
4 其の後の日米関係と問題点
1970年以降も日米関係に限っても多くの問題が起きていたが、その間にも担当のアメリカの大統領も日本の首相も入れ替わってきた。あまり組み合わせが上手くなかった例としては竹下登首相とブッシュ大統領とがあり、池田勇人首相とライシャワー大使は大いに意気投合し、所得倍増計画などが実行されたりした。
5 結び
色々な事件、色々な人物が登場してくるが、この本の特徴は、われわれが新聞ラジオで入手する情報では誤った認識を持ってしまうことが分かった。この資料は、貴重な文献や会話が多く出てくるが、年代的に話題が度々前後するのでまとめ難い所があった。
(六甲颪 2012年11月1日)
シモネッタの男と女/田丸公美子(文芸春秋社 定価1,429円)
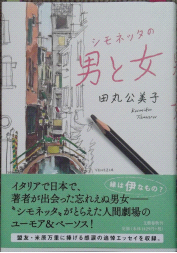
下品な内容を連想する書名であるが、決してそのような内容では無い。「シモネッタ」と言う名前は、イタリアでは良く使われている名前である。本書は、イタリア語通訳を職業とする女性の田丸久美子氏の著によるもので、通訳の仕事上で知り合った人達との人間関係や、イタリア人との交友関係を題材にしたイタリアでの生活環境などが主な内容のエッセイ集である。
著者は、亡くなった名ロシア語通訳の米原万理とも親しく、と言うよりも、真の友人であったのであろう。彼女との事も「はかなき露の字に代えて」と言う表題で語っているくだりは何となく泣けてくる。その中の文章を紹介してみると、『彼女に「エ勝手リーナ女帝」と言うあだ名を献上したことからも分かるように、私にとって万理は親友ではなかった』と言いつつ、米原万理の闘病生活を書き続け、そこには、これぞ親友と言うべき行動が記されている。そして、病床でのやりとり、『「万理、いやだー。わたしを残して逝かないで」甲高い声に驚いて目を見開いた彼女は、私を見ながら最後の力を振り絞って声にした。今度は、はっきり聞こえた。「そんなに泣くなよ」これがエ勝手リーナ様の最後の命令になった』心の通う友人であったことが偲ばれる。
私も大学の友人を48歳の時に肺がんで失った。彼の逝く2時間前まで彼の家族と一緒に病床にいたが、私は我慢の限界を超えて退散してしまった。家に着くなり訃報が届いて、何と冷たい友人なんだと自省した事を思いだし、同じ友でもその深みの違いに反省しつつ読み終えた箇所である。
最初から湿った話になってしまったが、この表題の「はかなき露の字に代えて」は、7つある表題の最後である。前の6つの表題は楽しくもあり、イタリア人の普段の生活や金持ちの日常、観光地の情景など、日常生活のありふれた様子が味わえる。
その6つの表題で一番印象にのこったのが、「ローマの白い奴隷」の表題である。この表題、何か悪いイメージを連想するが、決してそのような内容では無く、この人の特徴を表している。
こんなクダリから始まる。『不思議な縁で結ばれた親友がローマにいる。三十年あまり友情を育んでいるクララだ。』。その不思議な縁と言うのは、団体旅行で日本に来た観光客のガイドをつとめた際、最後の別れ際に感謝の気持ちを込めて、「今度、イタリアに来た時は私を訪ねて」と言う決まり文句を言って分かれるのが常とのことで、所謂外交辞令的な別れの挨拶との事。
60名のイタリア人ツアーのガイドをやっているとき、別れ際に貰った名刺のデザインが気になり、手帳にはさんで置いたとの事、仕事でローマを訪れた際、その顔や人物の印象も薄いままに、名刺を頼りに彼女の経営するお店を訪ねた事から、このエッセイが始まる。
その縁が良い方向に発展すると、神様のお導きであったとか、何かオーラに惹かれたとか、非科学的な事を言うものであるが、この出会いは著者にとってまさしくその様なものであったといっている。このクララと言う女性は、イタリアの名門ブティクブのブランドを家族で経営している女性で、そこに勤める経理担当のイギリス人女性と著者との3人コンビが生まれ、とても愉快で人間味溢れるイタリア生活が始まるのである。
我々の知らないイタリアの中産階級の社会とこの人たちの日常生活、そして3人での別荘生活や観光地などでの生活から、自ずと紹介される形となり、読者に訪ねてみたいと思う情景に巡り合わせてくれる。
これで、2つの表題に触れた事になるが、残りの5表題については触れる紙面も無いし、書感の使命を外れるので記す事をやめるが、著者が通訳の仕事上で知り合った人たちとの関係や通訳の仕事上のミッションを越えて、クライアントの事業に首を突っ込んだ経験なども記されている。たとえば、ビジネスマンとして有能であり、周りの人や家族に優しい人であるが、仕事となると気が短くて誤解され、一時は金持ちになるが、やがて没落していく人のこと。或いは、貴族の家庭で育った女性を妻に迎えたビジネスマンの生活など興味の尽き無い話題で満ちている。
読後感であるが、我々の知らない世界を知ってみると、私のビジネスの糧となり得るものが有ったような気がする。それは、観光案内に無いイタリアを知り、そしてその文化を安直に知る事が出来た事などである。
中国共産党 支配者たちの秘密の世界/リチャード・マグレガー著・小谷まさ代訳(草思社2011年6月6日 第1刷発行 本体2,300円+税)
著者はオーストラリア・シドニー生まれ。英「フィナンシャル・タイムズ」誌記者、元北京支局長。20年にわたって中国報道に携わる。ロンドン在住。
第1章 赤い機械 党と国家
第2章 中国株式会社 党とビジネス
第3章 個人情報を管理する者 党と人事
第4章 われわれはなぜ戦うのか 党と軍隊
第5章 上海閥 党と腐敗
第6章 皇帝は遠い 党と地方
第7章 社会主義を完成させた鄧小平 党と資本主義
第8章 「墓碑」 党と歴史
共産主義政権は今や完全に腐敗している。党は国民の平等を語るが、その政策はアジアのどの国よりも所得格差を生んでいる。党のイデオロギーは権力のそれであり、権力を守るためのそれに他ならない。人事・宣伝活動・人民解放軍を党が完全に支配しているが、党は秘密主義を貫いている。本書は党の機能と構造について、更にそれを用いてどのように権力を行使しているかを説明しようと試みている。党員は7500万人(09年)で12人に1人の割合。社会主義市場経済は市場経済ではない(党があらゆる場面で関与する)とは言え、中国の台頭は巨大潮流。今日の党は国家を変容させ世界をも作り変えようとしている。
第1章 9人の常務委員は誰がどんな序列で選ばれるか国民は誰も知らず、総書記は人気の終わりに近づくにつれ権力を強める(という不思議な国)。50余の国有大企業のトップの机上には真っ赤な電話(赤い機械)が置かれ、国を統括する集団の1人を意味する究極のステータスシンボルで中央とのホットライン。暗号システムにより傍受を防止。3権分立だが、その舞台裏は全て党が牛耳っている。党の権力の根拠は「共産党の指導のもと」(憲法前文)の一文だけ。裁判官は党に忠誠を誓い、次いで政府、国民、そして最後は法律に従うべき(09年 最高人民法院)という社会。しかし、民主化要求に悩み多い。
第2章 瀕死の国有企業を合理化し、党の管理下に置いて経済の牽引役! グローバル企業に成長しても共産主義と商業主義の二面性ある企業への対応は世界が困惑。「政治は厳しく、経済には甘く」が鄧小平の方針。金融機関も党が支配。中国で成功するには党と問題を起こさず優れた経営手腕を発揮する必要がある。多くの企業が上場されているが、その裏でも実態は党が管理出来るように工夫されている。
第3章 人事を握るのは中央組織部(表向きは党の人事だが)。すべての国家機関や(名目上)民営とされる組織の中まで関与する権限を持っている。中央政治局は北京トップの人事を司るが、組織部はその全ての候補者を篩にかけている。毛沢東が疑心で作ったのがこの組織の始まり。「会社を経営するのは役員会という考えは、言論・宗教の自由が憲法で保障されている、という考え方と同じで、中国では現実には起こらないことだ」(という某銀行家の幹部の良い方は当意即妙と感じました)。
とはいうものの、地方では中央の指導を無視して「地方の繁栄」に向けて様々な経済活動も行われているのも事実。
第4章 略
第5章 略
第6章 略
第7章 今の中国の社会主義(党の独裁と市場経済の並立)を完成させたのは鄧小平。中国でビジネスを急成長させるには、①紅帽子(政府を株主として受け入れる)、②国との連携なしに会社を大きくするのは危険を伴うと知ること、③政治に立ち入らない、ことだとある成功した企業家の言葉を紹介している。(やはり市場経済ではないのだ!!)
「猿を従わせようとするなら、鶏を殺すところを見せよ」と言うように、見せしめのメッセージを出すことも。江蘇鉄本鋼鉄公司は事業を手広く広げ過ぎて「当然の報いを受けた悪徳企業家」の物語として語られている(これは、中央政府の意向を無視して地方政府と手を結び、大型の高炉建設を計画したが、「政府の規制」違反で刑事訴追されて挫折。最後は「不正請求書発行」で起訴。市場経済に基づいて動いた企業が「中国が政治経済に基づいて動いている」ことを無視したための制裁)。
第8章 党にとっては、政府とビジネスを支配するだけでは不足で、権力を維持(体制維持)するためには、中国の歴史をも支配する必要があると党は知っている。毛沢東の大躍進政策の結果、3年間で3500~4000万人が餓死した(58年~60年)が、隠蔽(最近では天安門事件を隠蔽している)している例を挙げている。これらは中央宣伝部が主導してメディアに干渉している。歴史は党が国民を統制する手段。そして党の決定は国民13億人の総意とされている。
書感: かねがね「あらゆることが党の支配下」にあるというのが、私の実感です。そして、著者は中国共産党の機能・構造・権力行使の実情を説明しようと取材活動をしたことがうかがわれ、淡々とした記述ながらも説得力のある1冊と思います。しかし、私は優秀でありながらも入党を拒む若者に会ったりします。現在の中国で、成功しようと思えば「党員」であることが最大の必要条件と思える私には不思議な現象です。勿論、大多数は入党希望者が圧倒的に多い筈ですが、こういうところに中国の矛盾した実態があると思います。
これからも党の利益を優先した運営は続くと思いますが、これがいつまでも続くとは思えません。民主化活動は、党が軍を握り、法を私物化している現状では「天安門」のように抑え込むことが出来るでしょう。我々が中国と付き合う場合は、市場経済という言葉に惑わされないための知恵が必要ということも分かるので、ビジネスマンにとっても良い参考書と言えると思います。
しかし、汚職の実態にもっと迫って欲しかった、というのも私の感想です。また、真実を知らされない歴史教育というものも国民を不幸にするし、とばっちりを受ける日本はとんだ迷惑です(尖閣)。
(恵比寿っさん 2012年11月7日)
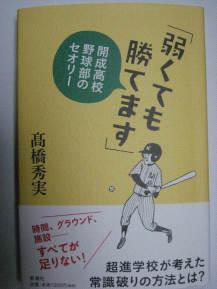 昨今では進学校と位置づけられている開成高等学校の硬式野球部が甲子園大会に出場をめざし、特異の理論で予選のベスト16位まで奮闘した様子を密着取材した書である。強いもの同士が戦うのを前提にした世で、弱くても一矢をむくいて意地を見せる哲学はなにか、現代社会での生き方として参考になる。
昨今では進学校と位置づけられている開成高等学校の硬式野球部が甲子園大会に出場をめざし、特異の理論で予選のベスト16位まで奮闘した様子を密着取材した書である。強いもの同士が戦うのを前提にした世で、弱くても一矢をむくいて意地を見せる哲学はなにか、現代社会での生き方として参考になる。
開成へ入学してくる生徒は運動が苦手、逆上がりができない、フライの方向がつかめない、ゴロは二重にトンネルする、球を投げたことがない、硬式は初めてで球がくるとこわい。これに加えて、他の部と共用のグラウンドを使えるのが週にわずか3時間である。
結果として野球が異常に下手である。率いる監督の青木は東京大学野球部出身、東大大学院で修士号を取得後、開成高校の保健体育科教諭となった。修士論文のタイトルは「投球動作と上半身の筋肉の活動」である。「開成は普通ではないんですね」と問うと「いや、むしろ開成が普通なんです」と何を話しても理屈っぽい。
「相手はセミプロ級、実力がぜんぜんちがう。普通の戦略ではむなしく餌食になるだけ」
「守備の練習はしません。一人の野手に一試合にくる球は4、5回、練習しても勝敗の逆転につながらない」
「強打中心、爆発によるコールドゲームをねらう。ドサクサ野球」
「打率はうまくても3割、どうせダメなら全部フルスイング」
「ナイス 空振り と声援する」
「細かく1点とっても、守備が下手だからとりもどされる。野球の勢いで土砂降りに圧倒する」
「打順は強打順に並べる」
「打撃で大切なのは球に合わせない」
「あの開成に打たれた、相手投手の動揺をさそう」
「打撃は個人プレー、練習は各自研究しろ」
「誰も監督のほうを見ないので、サインは出さない。必要なら声で出す。
相手チームをかく乱する場合も」
「投手は、自分から流れを始められる」
「ピッチャーは、とにかくストライクに投げられる人」
開成がベスト16入りした際の戦績
1回戦 開成10―2都立科学技術高校(7回コールド)
2回戦 開成13―3都立八王子高校(5回コールド)
3回線 開成14―3都立九段高校(7回コールド)
4回戦 開成9―5都立淵江高校
5回戦 開成3―10国士舘高校(7回コールド)
(高幡童子 2012年11月9日)
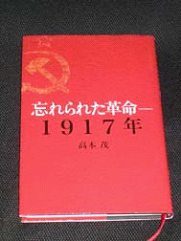 ロシアの小話にこんなのがある。モスクワ中央テレビがレーニン生誕100年祭の式典を中継していると天上からマルクスがやってきて、一言でいいから話させてほしいと熱心に頼む。手短にとマイクを渡すと、マルクスは叫ぶようにいった。「万国の労働者諸君! どうか私を許してください」
ロシアの小話にこんなのがある。モスクワ中央テレビがレーニン生誕100年祭の式典を中継していると天上からマルクスがやってきて、一言でいいから話させてほしいと熱心に頼む。手短にとマイクを渡すと、マルクスは叫ぶようにいった。「万国の労働者諸君! どうか私を許してください」
ロシア革命以後、20世紀の世界は社会主義という新しい思想の波に翻弄され続けた。本書の著者自身、若い頃はマルクス・レーニン主義を掲げる学生運動に身を投じたそうだが、総本山のソヴィエト連邦はその後変貌し、真の社会主義蘇生を目指したペレストロイカは挫折した。結局、崩壊後のソ連は革命を総括しないまま社会主義を捨て、市場経済に移行する。ペレストロイカが10月革命の本質を明らかにしなかったこと、革命の真相をまとめてみたいという思いが本書執筆の動機だったと著者は書いている。
「ソヴィエト」とは立法権と行政権を備えた直接民主主義統治機関のことだが、歴史的にはロシアの伝統的な地方自治機関、村落共同体まで遡るといわれる。ツァーリ(皇帝)の圧政による当時のロシア国民の不満は頂点に達していて、そうした社会情勢からすれば政権奪取は“腐った木戸を蹴破るくらいたやすい”ことだった。レーニンの偉業は権力を握ったことにあるのではない、自然発生的に湧き起こった民衆の反政府運動と巧みに同期し、新国家建設という幻想を抱かせて組織的に扇動したことだと本書は紹介している。
今日では、ロシア革命はスターリン主義によって裏切られ、変質させられたと認識されているが、本書によれば革命の第1日目から間違っていた。レーニンらのボルシェヴィキ(多数党)革命政府は、少しでも自分たちと考えを異にする人々や無政府主義者を容赦なく弾圧していった。革命的思想はもちろん、あらゆる自由の権利、活動までも「社会革命」の地でたちまち“歴史”(つまり過去のもの)にしてしまった。革命は一体誰の権利を守るのか、党かそれとも革命的大衆かという最大の命題に答を出さないまま、早くも自由と人権の抹殺が始まっていたというのである。
アメリカのジャーナリスト、ジョン・リードはその著書「世界を揺るがした10日間」で、この革命がレーニンとトロツキーの整然とした指導下で行なわれたように書いているが、権力を握った彼らが最初にしたことが反対派新聞の発行停止と宣伝活動の独占だったことを、この大金持ちの道楽息子は故意か無知か取り上げていない、と本書は手厳しい。
10月革命の真の担い手たちは、彼らによって直ちに“反革命”の烙印を押され、その存在を抹殺されていった。ソ連は輝かしい共産主義社会の前夜にあり、世界中の人々に生きる勇気と力を与えたかに見えたこの壮大な虚構の下で、実は2億の人々の人権が蹂躙され、拘束状態に置かれてきた。これこそ20世紀最大の逆説であり、悲劇であるとも指摘する。
レーニンは「国家と革命」のなかで、社会主義下ではプロレタリア国家運営に複雑な機構や高度の知識や技能は不要だといっているが、実際の国家建設と運営にどれだけ高度な理念と見識と技術が必要であるか。レーニン、スターリン、ヒトラー、毛沢東、ポルポト…、およそ常識や教養を持ち合わせない、政治家としても2流の指導者たちの革命の末路がどうなったか。なぜか、日本の最近の政党政治の現実とイメージが重なる。
著者は、やや情緒的ながらロシア革命の本質を次のように表現し、若き日の自らの社会主義活動と重ね合わせて総括している。
「ツァ―リの圧政やボルシェヴィキの欺瞞に対して決起した幾万の無名の民衆と同様、その後の社会主義闘争の過中で死んだ者は、皆純粋で心優しい人たちだったと信じている。しかし、その拠り所となったロシア10月革命が当初から裏切られ、変質させられていたのだとすれば、生死を賭けた闘争は人間解放と輝かしい理想社会のためでなく、世界全体を強制収容所やプリズン国家と化し、全人類を奴隷化するための運動だった。無謀な侵略戦争で戦死した無数の兵士たちと同様、まったくの犬死にだった」
先の小話ではないが、赤色全体国家群を生み出したマルクスの連帯責任は免れないとも書いている。ロシア革命の発生と破綻の始まりを、明快にかつ端的に理解するうえで格好の書といえる。
小話をもう1つ。マルクスとエンゲルスは科学者といわれるが本当だろうか。いや、違うだろう。科学者だったら、社会主義をまずモルモットで動物実験していただろうから。
(本屋学問 2012年11月11日)
2013年の中国を予測する/宮崎正弘+石平(ワック 本体933円)
対談形式で綴る本書の語り手二人は共に評論家で、共に気鋭のチャイナ・ウオッチャー。話をリードする宮崎正弘は世界経済やニューヨーク、北京の内幕をえぐる著作が多い。石平(せきへい)は中国生まれ。北京大学卒。神戸大学大学院修了。2007年日本に帰化。
今、中国は、国策で煽ってきた土地開発とビル建設が限界に来て、とっくにバブルがはじけていることを具体例で解説する。たとえば内蒙古省に百万都市を作ったが実人口は二万八千人だといった具合に、全国に鬼城(ゴーストタウン)が現出している例を挙げる。
バブル経済が行き詰まっても中国は、中国銀行など五大国有銀行と一万社におよぶ開発公社を潰すことができない。それを生かすために、債権処理機構を使った日本流の不良債権処理もやった。さらに長期貸し出しの土地に掛ける中国式の固定資産税導入の動き、早晩大幅の破産が見込まれる中産階級の不動産投資のローン負担をチャラにする徳政令の可能性、インフレと不良債権処理を狙った新札切り替えなど、何でもありの経済政策を予測する。
また、最大の輸出先であるユーロ圏への輸出の頭打ち、ヨーロッパや米国への輸出の鈍化などを分析し、付加価値の高い自動車なども数十万台では中国経済を牽引することはできないといい、中国独自の力で製造・輸出できるものはアパレル、革製品、玩具、日用雑貨、加工食品などだとして、高い経済成長は終わりだとする。
奥の手の、造幣局の輪転機をフル稼働させ、財政出動で支える「造幣局経済」もいずれは破綻すると見る。「中国は二十年以内に最貧国に転落する」と予言したのはヒラリー米国務長官だというが、本書もそれを肯定する。
中国社会では、農村からの出稼ぎで都市戸籍を持たないまま近郊に住み着いた者が流民化している。出稼ぎ労働力を吸収してきた不動産業、建設業、輸出用加工業が衰退していく。農村に帰っても開発公社に取り上げられて耕す土地がどんどん無くなっている。土地の砂漠化が急速に進み、水と食糧が無くなれば中国人の国外流出が拡大し、いずれ国際問題になる。
中国共産党では、ひとりの独裁パワーが衰えてきたという。共産党政権のトップは、二十五人からなる政治局員の中から選ばれる九人の常務委員だ。ここだけが民主化されていて多数決でことを決める。その中で毛沢東の独裁がもし九割だったとすれば、鄧小平は七割ぐらい、江沢民が五割ぐらい、いまの胡錦潯が三割あるかないかで、後はみんな合意で決めているという。すでに決まっている習近平総書記については、カリスマ性のない八方美人型で特権階級の利益を損なわない人物として選ばれたとみる。
民主化する中国として、武装警察官に向かって抗議する庶民、五人組など相互監視制度の崩壊、横の連携が出てきた暴動を描き、中国はますます乱世の様相を呈してくるとみる。国内を押さえきれなくなった時、国民の目を外に向けるために、軍による尖閣列島占拠などの暴挙も起こり得るとする。
軍事では、中国の海洋進出戦略にフィリピン、ベトナムなどASEAN諸国が苦慮している。日本では、中国海軍が対馬と津軽の南北二つの海峡を同時封鎖できる海軍力を誇示している。米国、ASEAN諸国との連携強化を説く。
最後に、中国人と付き合うには中国人になりきること。人を騙す。平気でウソをつく。良心・常識を捨てる。責任感を持たない。恥ずかしさを忘れる。そうでなければ、中国人と付き合っても騙される。と、これは元中国人の石平氏の言である。
(山勘 2012年10月)

 はなはだ不謹慎な想像だが、人型ロボットの最適分野は性愛用途(セクロイド)ではあるまいか? 主人の要求をすべて適えるだけでなく、時には逆らったり拗ねたり、本物の人間と同じように振舞うのだ。かつ
はなはだ不謹慎な想像だが、人型ロボットの最適分野は性愛用途(セクロイド)ではあるまいか? 主人の要求をすべて適えるだけでなく、時には逆らったり拗ねたり、本物の人間と同じように振舞うのだ。かつ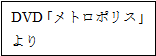 て、アダルトビデオが家庭用ビデオデッキの普及に貢献したように、人はこの種の支出にあまり金を惜しまない。価格が千万円台では無理かもしれぬが、百万円台に下がれば小さな市場が生まれ、百万円以下になれば急速に市場が拡大すると想像する。二足歩行、なめらかな手足の動作、音声合成、表情制御、自立的な対応など、セクサロイド実現に必要な技術は揃いつつある。後は価格低下と市場拡大の発火点がいつ来るか待っている状態と思う。
て、アダルトビデオが家庭用ビデオデッキの普及に貢献したように、人はこの種の支出にあまり金を惜しまない。価格が千万円台では無理かもしれぬが、百万円台に下がれば小さな市場が生まれ、百万円以下になれば急速に市場が拡大すると想像する。二足歩行、なめらかな手足の動作、音声合成、表情制御、自立的な対応など、セクサロイド実現に必要な技術は揃いつつある。後は価格低下と市場拡大の発火点がいつ来るか待っている状態と思う。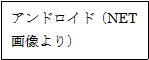 たれた夫が、亡き妻の面影を写したロボットと会話する場面もあるだろう。また、長年可愛がったいペットと生き写しのロボットも需要が多かろう。クローンペットより簡単にできそうだ。これらのロボットは初めの持ち主が不要になれば、外見やソフトを入れ替えリサイクルできるので、案外経済的に成り立つかもしれない。
たれた夫が、亡き妻の面影を写したロボットと会話する場面もあるだろう。また、長年可愛がったいペットと生き写しのロボットも需要が多かろう。クローンペットより簡単にできそうだ。これらのロボットは初めの持ち主が不要になれば、外見やソフトを入れ替えリサイクルできるので、案外経済的に成り立つかもしれない。